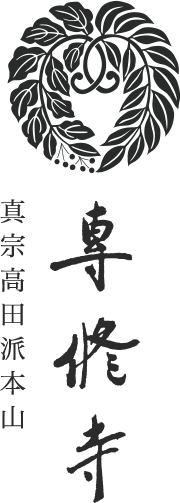ひとくち法話

ひとくち法話 1~9話 にんげん
第1話 人身受けがたし ―誕生の不思議―
私が、いまここにいることが、摩訶不思議(まかふしぎ)です。広い地球の、広い日本の、広い三重県のここに、人のいのちを享けて、いまを生きています。
この父、この母を縁にして生まれてきました。この父が別人だったら、この母と夫婦の契り(ちぎり)がなかったら、私は永遠に生まれてくることはありませんでした。
この不思議としかいいようのない因縁は、親と子という二世代だけのものではなく、無始以来の先祖までさかのぼっていきます。
報恩講に拝読する『式文(しきもん)』の中に「盲亀浮木(もうきふぼく)」のたとえ話があります。
いつも大海の底にいて、100年に1回海面にあがってくるという盲目の亀がおりました。その浮き上がってきた時にたまたま穴のあいた浮木(うきき)にぶつかって、その穴に亀の首がはまったという話です。人間にうまれてくること、ほとけの教えにあうということは、これほどのできごとだというたとえであります。実際こんなチャンスがありましょうか。ありえないということがあったという話です。その証拠が、いまここに生きている私たちであると教えられています。
『法句経(ほっくきょう)』に
人の生を うくるはかたく
やがて 死すべきものの
いま いのちあるは
ありがたし
という聖語があります。
再び生まれてくることのない私、1回きりのいのちを「どう生きるのが本当か」がわからなくては、永劫(ようごう)に迷っていかねばなりませんと、親鸞(しんらん)聖人はお念仏の教えを生涯説いていかれました。
ひとくち法話No1 ―にんげん1― より

第2話 老いを華やぐ
としどしにわが悲しみは深くして
いよよ華やぐいのちなりけり(岡本かの子)
私たちは暮らしながらに老けていきます。だんだん歯が抜け、腰やひざが痛くなり、耳も遠くなっていく。老いていく悲しみばかりなのに、岡本かの子は「いよよ華やぐ」と歌っています。限られた人生を歩き、人生を生きる。求めざるに、老いに「オイ」とポンと肩を叩かれて仰天する。仰天するでなしに、後ろから近づいてくる老いを静かに眺めて、来るんならいつでもどうぞと言える生き方ならすばらしい歓びです。
私たちはそのためには、自分の老いを作り上げねばなりません。体の老いに抗することはできませんが、私の人生の生きようまで老いに押さえられてはなりません。人間の脳細胞は使わなければますます退化していくと言われています。七十過ぎてからでも何かをする、新しいものに意欲を燃やす、趣味にいきる、みな老いを転換する方法です。しかし所詮この転換も本質的解決にはなりません。
岡本かの子は、実は親鸞聖人から華やぐいのちの歓びを頂いて生きていかれました。すばらしい芸術的素質を持ちながら、自己の煩悩にさいなまれ、夫一平の愛欲にも翻弄されていた彼女は、聖人の苦悩と煩悩に満ちた生涯、人間的な人柄にのめりこんでいきます。聖人の徹底した自己否定と自己批判、そこから生まれる凡夫の自覚を通してこそ他力念仏の道が開かれると教えられます。
人生の後半、望まずして必ず対面する老いにしろ、人間は与えられた宿命を背負いながら、自分の人生を歩く以外にどうすることもできない存在ですから、素直にそのままうなづいていくことが老いを超えていくことになると言えましょう。
ひとくち法話No2 ―にんげん2― より

第3話 病とのおつきあい
日本は世界最高の長寿国だと言われています。その理由は医学の発達と食物等生活環境の良いことがあげられます。
しかし長寿なるが故に反面、複雑で多様な病にめぐりあわねばなりません。巷には病院や診療所などに病人が溢れています。病気になっても、なかなか死なせてもらえずに、病に苦しまねばなりません。
病気にはかかりたくない、かかっても早く治りたいという気持ちは人情の常ですが、お医者さんだって治せない病は治してくれません。病はいやだ、きらいだと逃げまわっていても、余計に悪くなる場合もあります。
真宗の教えの重要なことのひとつは、自分が凡夫であるとの自覚によって「自力無効(じりきむこう)」とめざめることです。お医者の施療活動も、栄養や保健管理等も一種の自力のはたらきです。自力のはたらきには限界のあることを自覚せねばなりません。
ある名僧は次のように語られました。
「病気になるのは何かのたたりではない。病気は煩(わずら)わさせてもらうもの、病気になったおかげで、娑婆(しゃば)がわかり、人間そのものがわかり、自分の弱さや醜(みにく)さもわかるのです。そして他人様の親切さもわかるのです。病気は自分の凡夫性(ぼんぶせい)に気付く絶好の機会なのです。病気も仏作仏行(ぶっさぶつぎょう)、如来様(にょらいさま)のおはからいと申せましょう。」
このように病とおつきあいをすれば病も軽くなり、病の苦もへるのではないでしょうか。お念仏をいただくと、三世の重障(さんぜのじゅうしょう)が軽くなるという、ご和讃(わさん)が改めて深く味わえます。
ひとくち法話No3 ―にんげん3― より

第4話 生もわれら 死もまた われら
死ぬのはこわい、いつまでも生きたい、死なない方法はないものでしょうかとの願いに、ある人が1つあるよ、それは「生まれてこないこと」と言ったそうです。まことに明快な答えといえましょう。
この世に生を受けた以上必ず訪れるのが死であり、例外は許されません。文字どおり死亡率は100%です。あの一休禅師はこんな歌を残されています。
門松は冥土の旅の一里塚
めでたくもありめでたくもなし
おぎゃあと生まれた時から、すでに死に向かって私たちは進んでいるといっても過言ではありません。
志賀直哉さんの小説『城の崎にて』は作者が温泉で療養中、動物の生きざま、死にざまを目にして、その体験からつかんだ、生と死に対する感慨を述べたものですが、その結びとして「生きていることと、死んでしまっていることと、それは両極ではなかった」と述懐しています。
丁度、紙に表と裏があって、表を生、裏を死と考えますと、表と裏はひっついており、切り離すことができません。それとおなじように、人間の生と死も別々のことではなく、死を抜きにしては生が考えれないわけです。つまり生を解決するには死を解決せねばなりません。
清沢満之師も「生のみが我らにあらず、死もまた我らなり」と述べられています。とかく私たちの日常は生きることばかり考えて死ぬことを考えないで生活しているように思います。いかがでしょう。
何といっても人生における最大の事件は死であって、後生の一大事と受け取らせてもらいたいものです。
ひとくち法話No4 ―にんげん4― より

第5話 煩悩具足のままで
人間の心の中には、さまざまの欲望が渦巻いています。食欲・性欲・睡眠欲は、動物としての生きる本能でしょう。これに人間だけがもっている金銭的な欲望と他人に対する優越感や虚栄心から起こる名誉欲があります。これらをひっくるめて『貪欲(とんよく)』といいます。
次に自分の思惑と違って誤解されたりすると腹の虫がおさまらない、いわゆる「怒り、腹立ち、そねみ、ねたむ心」が湧いてくる。これを『瞋恚(しんに)』といいます。それに、もろもろの不平不満やいつまでも執着してあきらめきれない心を『愚痴(ぐち)』といいます。
以上の三つのものを総合して、「三毒の煩悩(さんどくのぼんのう)」といっています。
これを細かくわけていくと実に多くの煩悩がでてきて、昔から「百八の煩悩」とか「八万四千の煩悩」とかいってきました。一般に「仏道修行(ぶつどうしゅぎょう)」というときは、その煩悩を退治するための修行のことをいいます。きびしい修業によってひとつひとつの煩悩を断ち切って仏の悟りにいたるのです。これは聖者(しょうじゃ)の道であります。
しかし今、私たちは、親鸞聖人のお導きで、阿弥陀如来(あみだにょらい)の本願のお力を聞信(もんしん)することによって、煩悩のままで救われていくという、他力念仏のみ教えをいただきました。煩悩具足の私たちにとっては、これがほとけになる唯一の道なのです。そして生きながらにして仏に等しい位につくと教えられ、これを『平生(へいぜい)往生』といい、また『現生正定聚(げんしょうしょうじょうじゅ)』とも『不退の位』ともいいます。
ひとくち法話No5 ―にんげん5― より

第6話 御同行は法の友
「あんた宗旨(しゅうし)は」「私は真宗です」「ご本山は」「一身田の高田本山です」「うれしいね私も同じや」電車の中で隣り合わせた見知らぬ人が同じ念仏の御同行であったということで、互いに意気投合して話に夢中になってしまい、ついつい乗り過ごしてしまったという人がありました。お念仏の友という所で人々は真に通じあえるのでありましょう。
寺の法会に遠いところから参ってくださる奥さんが2人います。1人は電車とバスで、もう1人はマイカーで。ある時、「おなじ方向なのですから私の車にお乗りになったら」ということから、以来申し合わせてお参りされるようになり、今では寺参り以外のいろいろの交際をされています。本当によき友が出来たと喜んでおられます。
富める中での貧しさは、人間関係そのものの上にますます顕著に現れています。地域社会や職場に於いてだけでなく、家族の中でも親子の断絶、家庭内離婚等々家族そのものが崩壊しつつあります。人は真に心の通じ合った間柄がなければ生きて行けないから人間といわれているのです。
ご開山親鸞聖人は、御同行(おんどうぎょう)、御同朋(おんどうぼう)と、お念仏のもとで結ばれる心の友を目ざして僧伽(そうぎゃ)の形成に力してくださいました。先ずは夫婦、兄弟、家族がかくあって、それを多くの人々へと広げて生きたいものです。
「み仏の恵みをいただき、念仏のお同行として、世のため人々と共に歩みます」と、生活の指針にありますが、御同行は即ち法の友であり、暖かい人間関係がうまれてくる源であります。
同一に念仏して別の道なければ四海のうち皆兄弟なり。 親鸞
ひとくち法話No6 ―にんげん6― より

第7話 恭敬のこころに孤独なし
「好きな釣りだけではなく、旅行や地域活動にもできるだけ参加してきた。けど、なぜかいつも心は重く、あまり人と話をする気にはなれんかった」と嘆かれたお年寄りがありました。
奥さんに先立たれ、家族からも何となく疎外されるようになって、孤独な思いをもったのでしょう。それを振り払おうとして努力してみたが、心の空洞は益々深まって「何のために生きてきたのか」と自問自答するばかりだというのです。
本願力にあひぬれば むなしくすぐる人ぞなき 『高僧和讃 天親讃第3首』
これは親鸞聖人が和讃の中でのべられたものです。本願力とは苦しみ悩み続けている私たちを「必ず救う」という仏さまのお働きです。この教えにめざめると「何のために人のいのちをうけて、いきているのか」という理由がわかります。
ひとりで生きているという思いこみは疲れます。私だけが、うちだけが何故という自問自答では、道は開けてきません。私のいのちは、天地自然のめぐみ、社会の相互扶助、我が身の不思議な働きなど、すべて『おかげ』で生かされて生きていたということに気がつくと肩の荷が軽くなるでしょう。
そして、このおかげさまが、恭敬のこころです。
『おかげさま』といただく生活から、たくさんの人々との暖かい出会いが開かれてまいります。
ひとくち法話No7 ―にんげん7― より

第8話 四苦八苦
そのお爺さんは九十二歳で亡くなられました。体の大きな人でした。晩年、手足が弱り長女の世話を受けていました。彼女は華奢(きゃしゃ)で、大きくて重いお父さんのお世話は大変だったらしく、よく腰が痛いと言っていました。
葬儀は穏やかな雰囲気のうちに行われました。しかし、いよいよ荼毘(だび)に付(ふ)されるという時、彼女はお棺にとりすがり、泣き伏してしまいました。親しい人の情でありましょう。
いかに、若くありたい、丈夫でありたい、生きていたいと思っていても、時がくれば、老い、病(や)み、死んでいかねばなりません。
それは、この世に生を受けた者にとって避けてとおることができないことです。お釈迦(しゃか)さまは、生・老・病・死の四苦を説いておられます。
さらにその上に、愛別離苦(あいべつりく)(いとおしい人と離れなければならない苦しみ)・怨憎会苦(おんぞうえく)(怨み憎む人と会わなければならない苦しみ)・求不得苦(ぐふとっく)(求めて得ざる苦しみ)・五陰盛苦(ごおんじょうく)(私たちの身心を構成する五つの要素から生ずる苦しみ)があります。先のものと合わせて八苦といいます。そこに私たちの現実があります。
苦しみは、しかし、ただ苦しみに終わるものではないのです。老いてはじめてわかること、病気になってはじめて気づくこと、また死に直面してはじめて見えてくることがあるのです。そのために、私たちは聞法にいそしまなねばなりません。
ひとくち法話No8 ―にんげん8― より

第9話 ほとけさまのこころ わたしのこころ
花屋さんの店先は、色とりどりの花で一杯です。
見とれていると『阿弥陀経(あみだきょう)』のことばがうかびます。
「池中蓮華(ちちゅうれんげ)大如車輪(だいにょしゃりん)青色青光(しょうしきしょうこう)黄色黄光(おうしきおうこう)赤色赤光(しゃくしきしゃっこう)
白色白光(びゃくしきびゃっこう)微妙香潔(みみょうこうけつ)(お浄土はいろいろの蓮の花が咲き乱れ香り清らかで、調和しています。)」
お浄土とは、阿弥陀さまが私たちに安らぎを与えたい、流転輪廻(るてんりんね)から解脱(げだつ)されたいと願われて完成された世界です。
この願いには、必ず往生成仏(おうじょうじょうぶつ)させるとの阿弥陀さまの確信がこめられています。この確信を他力の信心といい、その願いを南無阿弥陀仏と聞いて歓喜(かんぎ)することも他力の信心です。
店先の花々は、見ている私のこころを明るくしてくれます。
ところで、どれか1輪をと思ったとき、私は落ち着けなくなります。どれにしよう、どれがいい、値段はいくらだろうという具合です。
お浄土のようだと思っていた私が大混乱です。
花屋の店先はもう「お浄土」に見えないのです。
美しい花があるのに、こころがゆれうごきます。
この定まりのない私たちの心のうごきを「自力のはからい」といいます。
「南無阿弥陀仏」を聞きながら「自力のはからい」がはたらくのです。
もっともっと阿弥陀仏の願いを聞き続けなければと思います。
ひとくち法話No9 ―にんげん9― より

ひとくち法話 10~15話 三尊仏
第10話 三国伝来の仏さま
お釈迦(しゃか)さま在世の時でした。インドに月蓋(がっかい)長者という貪欲(どんよく)な長者がいました。50歳をすぎてやっと娘が授かりましたが、流行病を患い、臨終を待つ程になりました。長者は気も狂わんばかりになってお釈迦さまに救いを求めたところ、「西方世界に阿弥陀仏(あみだぶつ)、観音(かんのん)、勢至(せいし)がいます。直ちに五体投地(ごたいとうち)して名号を称えなさい」と教えられ、娘は奇跡的に一命をとりとめました。
長者は大喜びをして、お礼にと私財を投げだし国中から閻浮檀金(えんぶだごん)(白金)を探し求め、三尊仏をおつくりしたのです。
時がたち、この三尊仏は、月蓋長者の生まれ変わりといわれる百済国(くだらのくに)(朝鮮)聖明王(せいめいおう)のもとにこられ、さらに百有余年後我が国に渡来されました。
欽明(きんめい)天皇13年の時で、これが仏教伝来の最初です。
当時、朝廷では物部(もののべ)氏と蘇我(そが)氏の勢力争いがあり、三尊仏は、そのご難(なん)にあわれましたが、のちに伊那(いな)の本田善光(ほんだよしみつ)に「善光よ、前生(ぜんしょう)、月蓋長者なりし汝(なんじ)の国に我を負(お)いて帰るべし」と告げられ、信濃(しなの)におちつかれることになりました。これが、長野の善光寺のはじまりといわれています。
そして、その度お迎えする一光三尊仏は、親鸞聖人(しんらんしょうにん)のご感得で、善光寺からお迎えした一躯分身(いっくぶんしん)の尊像です。
お経に「摂取不捨(せっしゅふしゃ)」という阿弥陀さまのお心が説かれています。迷いの世界に流転(るてん)しているあなたを救うためには、どこまでも追いかけてお念仏の声を届けますというお働きです。以上、三尊仏の三国伝来の物語を聞いていますと、このような、仏さまのお心が伝わってくるように思えます。
ひとくち法話No10 ―三尊仏1― より

第11話 聖人直拝の三尊さま
聖人53歳(1225)の4月「師の願い満足す。速やかに善光寺に来るべし。我が躯を分かちて汝に与えるなり」との如来のお告げがあり、弟子2人と信濃(長野県)の善光寺に赴かれました。
善光寺でも、聖人が来られるというお告げがあったので、直ぐに一躯分身(いっくぶんしん)の一光三尊仏をお受けすることができました。聖人のお喜びはいかほどだったでしょうか。聖人は、この三尊仏を本寺の如来堂のご本尊として安置(あんち)されました。これが聖人直拝(じきはい)の三尊さまです。以後、60歳を越えて京都にお帰りになるまで、聖人みずからお仕えしてご尊崇(そんすう)されましたので、お弟子や近在の人々も歓喜(かんぎ)してお参りされました。
直拝とは、聖人が直接お参りされたということです。こうして、本寺専修寺(ほんじせんじゅじ)は直弟子真仏上人(じきでししんぶつしょうにん・高田派第2世)に受け継がれて関東における念佛弘通(ぐつう)の拠点となりました。このように聖人直拝の一光三尊仏は現在唯一無二のご尊像(そんぞう)であり、わが派だけに伝承(でんしょう)されているほとけさまです。
4月1日から一身田の本山へ一光三尊仏がお出ましになっています。ご開扉(かいひ)中は、御影堂(みえいどう・正面の大きなお堂)の中央に一光三尊仏が、その隣に聖人の尊像が、共に安置されて法会(ほうえ)が営まれました。
お参りしていると聖人が南無阿弥陀仏とお念仏を申されながら三尊さまにお仕えされていた往時(おうじ)の情景が偲ばれて大変ありがたいことであります。
ひとくち法話No11 ―三尊仏2― より

第12話 右にお立ちの観音菩薩
親鸞聖人(しんらんしょうにん)が直拝(じきはい)された現存唯一の仏像が、いま本山にご滞在中の一光三尊仏です。1つの光背(こうはい)に、三体の尊い仏さまがお立ちになっているので一光三尊仏と申し上げています。光背とは後光(ごこう)のことです。三体の尊い仏さまとは、中央に「阿弥陀如来」とその阿弥陀如来のお心〔慈悲(じひ)・智慧(ちえ)〕を「観音菩薩」「勢至菩薩(せいしぼさつ)」として弥陀の両脇に表現された二菩薩のことです。
聖人は、関東にご在住の8年程もの間、この三尊仏を本寺のご本尊として厚くお恭敬(くぎょう)されました。右にお立ちの観音菩薩は慈悲心をお示しになって『皇太子聖徳奉讃(こうたいししょうとくほうさん)』第42首に
この像(ぞう)つねに帰命(きみょう)せよ 聖徳太子(しょうとくたいし)の御身(ごしん)なり
この像(ぞう)ことに恭敬(くぎょう)せよ 弥陀如来(あみだにょらい)の化身(けしん)なり
と和讃しておられます。十七条憲法をはじめとして仏の大慈悲心を行じられた聖徳太子を観音菩薩として尊とばれ、また、弥陀如来の生まれかわりとしても、観音菩薩を特に敬(うやま)えと勧められるのです。
私たちの悩みや不安を、慈(いつく)しみ悲しんでくださる観音さま。苦悩の本質を見極めて、あるがままの姿にたちかえらせようとしてくださる観音さま。「おかげさま」と、共に生きられる世界を開いてくださる観音さま。
このような慈悲深い観音さまのお姿を通して阿弥陀如来さまのお心を私に届けてくださるのであります。ご先祖の方々も、心を込めて手を合わされた「三尊さん」。今、私たちもご縁にあわせていただきましょう。
ひとくち法話No12 ―三尊仏3― より

第13話 お浄土へと勢至さまのお導き
阿弥陀(あみだ)さまをまんなかに、右側に観音(かんのん)さま、左側に勢至(せいし)さま、1つの光背(こうはい)に三体ならんで「一光三尊(いっこうさんぞん)の阿弥陀さま」です。
観音さまは「慈悲(じひ)」のこころです。勢至さまは「智慧(ちえ)」のこころです。ともに阿弥陀さまのおこころをこの二菩薩(ぼさつ)のお姿で具体的に示されました。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は『浄土和讃(じょうどわさん)』で勢至さまのおこころを
われもと因地(いんじ)にありしとき 念仏(ねんぶつ)の心(しん)をもちてこそ
無生忍(むしょうにん)にはいりしかば いまこの娑婆界(しゃばかい)にして
念仏のひとを摂取(せっしゅ)して 浄土(じょうど)に帰(き)せしむるなり
大勢至菩薩(だいせいしぼさつ)の 大恩(だいおん)ふかく報(ほう)ずべし
(大勢至菩薩和讃 第7首 第8首)
とうたわれました。
「お念仏を申す人は、必ずお浄土に往生(おうじょう)させていただきます」と勢至さまが自ら救われた証人となって阿弥陀さまのおはたらきを明らかにしてくださいました。私たちはこの勢至さまのお導きに深くお礼を申しましょう。
また、恵信尼さま(えしんにさま・聖人の奥さま)は、お便りの中で聖人は師の法然(ほうねん)上人を勢至菩薩の化身(けしん)であると堅く信じておられると記されています。
私たちは今このみ教えにあい、お念仏を申させていただいています。このうえないご縁に、ただただ合掌するばかりです。
ひとくち法話No13 ―三尊仏4― より

第14話 『観無量寿経』と三尊さま
真宗の所依(しょえ)の教典は浄土三部経(じょうどさんぶきょう)で、そのひとつが『観無量寿経』です。
このお経は、葦提希夫人(いだいけぶにん)一家をモデルにして、凡夫救済のすじみちを示された壮大な仏教ドラマとも言えましょう。
葦提希夫人は実子の阿闍世(あじゃせ)に、父王頻婆娑羅(びんばしゃら)ともども虐待迫害をうけ、苦悩のあまり釈尊(おしゃかさま)に救いを求めたのでした。釈尊は葦提希に諭されました。「葦提希よ、心して聞きなさい。そしてよく思念するのですよ。それ、ごらんなさい。あなたの苦悩を救うために空中に無量寿仏(阿弥陀仏)がお立ちではありませんか。しかも右には観世音(かんぜおん)、左に大勢至(だいせいし)の二菩薩が侍(はべ)ってみえます。その光明はひかり輝いて、つぶさにこの目で見えないほどですね。」
葦提希は釈尊に言いました。「釈尊、わたしはいま仏の威力によって、阿弥陀仏と観音・勢至の二菩薩を見奉(みたてまつ)ることが出来ました。しかし、わたし以外の未来世に生きるものたちはどうしたらこの三尊さまに遭(あ)えるのでしょうか。」
この問いに、釈尊は懇切丁寧(こんせつていねい)、更に微に入り細にわたり説法を続けられたのでした。そして、どんな凡夫でも1人残らずお浄土に救われるお念仏の道をしめされたのでした。
親鸞聖人が善光寺如来である一光三尊仏をいただかれたのは、この『観無量寿経』の中の凡夫救済の具体的なみちすじをこの世に於いても実現したいためだったのでしょう。
ひとくち法話No14 ―三尊仏5― より

第15話 観音勢至もろともに
一光三尊仏(いっこうさんぞんぶつ)について、最もわかりやすい和讃(わさん)に
弥陀(みだ) 観音(かんのん) 大勢至(だいせいし) 大願(だいがん)の船に乗(じょう)じてぞ
生死(しょうじ)の海にうかびつつ 衆生(しゅじょう)をよぼうてのせたもう 『正像末和讃 第52首』
があります。「迷える者、罪障(ざいしょう)深き者すべてをお浄土にすくう」という阿弥陀如来(あみだにょらい)の大きなお心が、慈悲(じひ)の観音菩薩となり智慧(ちえ)の勢至菩薩と形をあらわして説法(せっぽう)されました。私たちにわかりやすく教えを届けようという阿弥陀如来の親心です。その願いも約束もすべて仏さまの手もとで成就(じょうじゅ)していることをわざわざお浄土から娑婆(しゃば)までお出ましになって説かれました。そして、その証拠が「南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)」のお名号であるとお示しくださいました。
「衆生をよぼうて のせたもう」は、救いの目当てはあなたですという確かなお声であり、片時も休むことなく呼びかけてくださいます。
観音 勢至もろともに 慈光世界(じこうせかい)を照曜(しょうよう)し
有縁(うえん)を度(ど)してしばらくも 休息(くそく)あることなかりけり 『讃阿弥陀仏偈和讃 第17首』
であります。このような仏さまのお誓いに対して私たちはどうすればよいかといえば、ただ「南無阿弥陀仏」と称うるばかりです。
南無阿弥陀仏をとなうれば 観音 勢至はもろともに
恒沙塵数(ごうじゃじんじゅ)の菩薩と かげの如(ごと)くにみにそえり 『現世利益和讃 第13首』
観音・勢至両菩薩さまも無量の菩薩がたと共に、その人の身に付き添ってくださるのであります。
本山だよりNo15 ―三尊仏6― より

ひとくち法話 16~27話 真宗の教え
第16話 仏説無量寿経
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、お釈迦(しゃか)さまが説かれたたくさんのお経の中から、次の3つのお経を「浄土の三部経」といって大切にされました。
◎仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう)
◎仏説観無量寿経(ぶっせつかんむりょうじゅきょう)
◎仏説阿弥陀経(ぶっせつあみだきょう)
この三経のうち、とくに『仏説無量寿経』を「真実の教」とお示し下さいました。
このお経には、すべてのわたしたちを苦悩の境界から救うのだという「阿弥陀仏」の大きな慈悲とお念仏のおはたらきが説かれています。
阿弥陀仏は自ら「南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)」と名告(なご)り、私たちに救いの道を開いて下さいました。この心を私たちの親しんでいるご和讃に
生死(しょうじ)の苦海(くかい)ほとりなし ひさしくしづめるわれらをば
弥陀(みだ)の悲願(ひがん)の船(ふね)のみぞ のせてかならずわたしける 『高僧和讃龍樹讃第7首』
とうたわれています。
生きているということは、そのまま苦海の中にあるのです。その中に沈みあえいでいる私たちは弥陀の悲願の船(阿弥陀仏の本願)以外に救われる道はないのです。
人間の根源的な救いが南無阿弥陀仏であると教えてくださっているのが『仏説無量寿経』です。
ひとくち法話No16 ―真宗の教え1― より

第17話 本願
永年の目標が達成(たっせい)したとき「ついに私の本願(ほんがん)が成就(じょうじゅ)しました」と使うことがあります。この本願という言葉は、仏教からきています。
真宗のご本尊(ほんぞん)は、阿弥陀仏(あみだぶつ)ですから、いま、いうところの本願は、阿弥陀仏が誓われた根本の願いのことをいいます。本願は、十方(じっぽう)の衆生(しゅじょう)をめあてに誓われました。
1人も漏らさずに仏の国に救うというおこころです。そしてこのお心が南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)というお名号となって私たちに届けられました。
また、この阿弥陀仏の本願は、摂取不捨(せっしゅふしゃ)だからこの世で仏縁のなかった者に、次の世までも見放すことなくお念仏を届けますという現世来世(げんぜらいせ)にわたる大変なお誓いであります。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、20年間も比叡山で修業して、仏になろうと努力、精進されたのに、結果は「私は、悟(さと)りをひらくために修行をしてきたが、修行すればするほど、私自身が罪悪生死(ざいあくしょうじ)の凡夫であり、無始よりこのかた常に沈没し、常に流転(るてん)して迷いの世界から抜け出ることができない私であることを知らされました」と告白されたのでした。
そして師、法然上人(ほうねんしょうにん)から、かかる浅ましき衆生を浄土に往生させるために阿弥陀仏の本願が成就されてあったことを知らされたのでありました。
だから、この真宗のご本尊である阿弥陀仏のご本願は、私やあなたをめあての本願であり、私やあなたが仏の国に生まれる唯一の大道です。
弥陀(みだ)の本願(ほんがん)信ずべし 本願信ずる人はみな 摂取不捨(せっしゅふしゃ)の利益(りやく)にて 無上覚(むじょうがく)をばさとるなり 『正像末法和讃』
ひとくち法話No17 ―真宗の教え2― より

第18話 名号
「名号」とは「南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)」のことです。阿弥陀さまの「み名」です。阿弥陀さまは私たちに、「どうかお願いだから私の名をよんでおくれよ。必ず救うから。南無阿弥陀仏を受け取って安心しておくれ。きっと浄土(じょうど)へ迎え取るから」と呼んでくださいます。
今、私たちが、その呼び声に応えて「南無阿弥陀仏」と称えたら、もう浄土へ生まれていく人生が決まるんです。もう迷わないでいい。何故なら、南無阿弥陀仏のみ名は、われわれの往生(おうじょう)に何の心配もないと言って下さる如来さまの言葉ですから。
「お前たちの、名をあげたい、得(とく)したい、人に勝ちたいという煩悩(ぼんのう)や、迷いは障(さわ)りにならぬから、安心して南無阿弥陀仏を受け取っておくれ」との呼び声が南無阿弥陀仏です。
体から噴(ふ)き出る欲や、怒りや、愚痴(ぐち)などをいっぱい抱えている私たちですが、なに1つ自分で処理することが出来ない。その出来ない私たちをそのままに如来さまが抱き取って下さるから、今の私のままで浄土への道を歩ましていただくことが出来るのです。迷いのない人生がそこに開かれるのです。
私たちが、南無阿弥陀仏と称える時、阿弥陀如来が、お浄土から6字の言葉にまでなって、私たち1人1人のいのちの底にまで届いてくださるのです。「今日も命を頂いてありがとうございます。南無阿弥陀仏」「他人の昇進を恨んだこのあさましい私でした。南無阿弥陀仏」「嫁にどぎつく言い過ぎた恥ずかしい私でした。南無阿弥陀仏」
お念仏(名号)を称えるということは、いつも如来さまと一緒に日暮らしするということであり、教えに遇(あ)っていることであり、光に遇っていることです。
ひとくち法話No18 ―真宗の教え3― より

第19話 本尊
真宗のご本尊は「阿弥陀仏(あみだぶつ)」です。お仏壇の中央・正面に安置されている仏さまです。木像・絵像・名号(南無阿弥陀仏)とお姿の違いはありますが、すべてきまりによってあらわされた「阿弥陀仏」です。
この阿弥陀仏は、私たちを「無明煩悩(むみょうぼんのう)、われらがみにみちみちて、欲も多く、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころ、多くひまなくして、臨終の一念にいたるまで、とどまらず、きえず、たえず(一念多念文意)」の衆生とみぬかれて、仏さまの方から、お浄土へ迎えとる道をひらかれた仏さまです。
親鸞聖人は和讃で
十方微塵世界(じっぽうみじんせかい)の 念仏(ねんぶつ)の衆生(しゅじょう)をみそなわし
摂取(せっしゅ)してすてざれば 阿弥陀(あみだ)となづけたてまつる(浄土和讃弥陀経意第1首)
と、うたわれたました。「十方微塵世界」とは、全宇宙ということです。「衆生」とは生きとし生けるものです。すなわち、この世に生きるあらゆる念仏を申す私たちを仏さまはご覧になって、必ずお浄土に迎えますと誓われたので、「阿弥陀仏」と申し上げるのです。聖人はこのように教えてくださいました。つまり「阿弥陀仏」は、この約束で世に出られた仏さまです。
さらに、阿弥陀仏以外の仏さま(諸仏)は、この「阿弥陀仏」のお誓いがまちがいないことを証明するために出られたのだとのべられています。『観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)』には「念仏衆生摂取不捨(ねんぶつしゅじょうせっしゅふしゃ)」と阿弥陀仏が念仏を称える人々を平等に救いとるご本尊のおこころをお示しくださっています。
「阿弥陀仏」は私たちが救われる唯一の仏さまなのです。
ひとくち法話No19 ―真宗の教え4― より

第20話 念仏(重誓偈)
「我建超世願(がごんちょうせがん)」で始まる偈文(げもん)があります。これは『大無量寿経(だいむりょうじゅきょう)』において、法蔵菩薩(ほうぞうぼさつ)が、自らおこされた48の誓願(せいがん)を、師の世自在王仏(せじざいおうぶつ)にむかって表白(ひょうびゃく)され、その表白が終わった後、頌(じゅ)(詩句)として説かれているものであります。48願で述べられていることを重ねてうたっておられることから、『重誓偈(じゅうせいげ)』と呼ばれています。
この偈文は、その始めのところに「誓不成正覚(せいふじょうしょうがく)」という句が3回おかれています。そこからこの偈文は『三誓偈(さんせいげ)』とも言われています。
三誓のなかの第一は「必至無上道(ひっしむじょうどう)」というものです。この上ない道とは、おさとりの道であります。必ずおさとりの道に至させたい。もしこの願いが満足されることがないのならば、私は仏にならないという誓いです。
第二の誓いは「普済諸貧苦(ふさいしょうびんぐ)」というものです。もろもろの貧しき人々、苦しんでる人々を救っていきたい。もし、そのことができないのならば、私は仏にならないという誓いです。
第三の誓いは「名声超十方(みょうしょうちょうじっぽう)」というものです。「名声」とは、お念仏の声です。私が仏になりました時にはお念仏が広くいきわたりますようにという願いであります。
この三つの誓いのうち、第一の誓いと第二の誓いとは、第三の誓いの中にあらわれているのでしょう。お念仏の中には法蔵菩薩の「必至無上道」という自利(じり)の願いと「普済諸貧苦」という利他(りた)の願いがこめられているのであります。
聖人は、「大小の聖人、重軽(じゅうきょう)の悪人、みな同じく斉(ひと)しく選択(せんじゃく)の大宝海に帰して、念仏成仏すべし(教行証文類行巻)」とすすめておられます。
ひとくち法話No20 ―真宗の教え5― より

第21話 他力
何もしないで、他人まかせで甘い汁を吸うような事を表現するのに、他力本願という言葉が使われています。真宗の他力の救いをこのように理解している人はいないでしょうか。これは、間違いであり誤解です。
親鸞聖人は、比叡山における20年間の自力修行(じりきしゅぎょう)によっては、どうしても生死(しょうじ)出(い)ずべき道が得られず、苦悩の末に吉水の法然上人を尋ねて、他力念仏に転入されました。
そのことを自ら「雑行(ぞうぎょう)をすてて、本願に帰す」と述べられました。
本願とは阿弥陀仏が誓われた根本の願いです。私たちを救わずにはおかないという誓いです。この阿弥陀仏のお誓いを疑いなく素直に信じて、お任せすることが肝要(かんよう)であります。これを他力といいます。
聖道門(しょうどうもん)の人(ひと)はみな
自力(じりき)の心(しん)をむねとせり
他力不思議(たりきふしぎ)にいりぬれば
義(ぎ)なきを義とすと信知(しんち)せり 『正像末法和讃 54首』
と、聖人が和讃されておられます。
「義といふことは、はからうことなり、行者のはからひは自力なれば義というなり、他力は本願を信楽(しんぎょう)して往生決定(おうじょうけつじょう)なるゆへにさらに義なしとなり」と聖人のお手紙にも度々書かれております。すなわち真宗の教えでいう他力は、他人(ひと)まかせのことではなく、また、物理的な自然現象でもなく、阿弥陀仏のお働きをいうのです。仏力(ぶつりき)です。
ひとくち法話No21 ―真宗の教え6― より

第22話 現生正定聚
念仏往生(ねんぶつおうじょう)の願因(がんにん)により
必至滅度(ひっしめつど)の願果(がんか)をうるなり
現生(げんしょう)に正定聚(しょうじょうじゅ)に住(じゅう)し
必ず真実報土(しんじつほうど)にいたる 『浄土三経往生文類』
親鸞聖人(しんらんしょうにん)がお念仏の功徳(くどく)、お念仏の喜びの極致をしめされました。念仏者の力強い確信をあらわしてくださいました。
さて、どうでしょうか。この聖人のお言葉を声に出して読んでいただけませんか。何回も大声で読んで下さい。さらに、たくさんの人と一緒に唱和(しょうわ)したら、なおすばらしいと思います。
読み上げていると、静かに喜びがわいてまいります。
阿弥陀仏(あみだぶつ)の念仏往生(ねんぶつおうじょう)のご本願(ほんがん)のおかげで、浄土(じょうど)へ往生し、仏さまになります。このご本願を聞いて、念仏し、確かな、確かな人生をすごさせていただくのです。そして、必ずお浄土へと往生させていただくのです。
私たちは、今の今まで、煩悩(ぼんのう)に狂って生き、迷ってきました。過去の罪障(ざいしょう)に悩み、苦悩の連続でした。だが、今この文を聞いています。私に、この文を読ませてくださっています。
阿弥陀仏の願いは、私をこの世において、必ず成仏する仲間に入れて、不退(ふたい)の位につかせようと言われるのです。
南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)の六字は、その阿弥陀仏からの、呼び声です。
ひとくち法話No22 ―真宗の教え7― より

第23話 往還二廻向
「廻向(えこう)」という言葉は、「廻転趣向(えてんしゅこう)」という意味で、人間の心をひるがえして、仏に帰依(きえ)することをいいます。それがすべて菩薩の自力の働きですが、阿弥陀仏の働きのお手まわしであります。この廻向に2種あって、ひとつは往相(おうそう)の廻向、ふたつは還相(げんそう)の廻向といいます。
往相の廻向とは、阿弥陀仏(あみだぶつ)のお力で浄土に生まれていくことです。阿弥陀仏の手もとにおいてできあがった救いの手だてなので「廻向成就(えこうじょうじゅ)」といいます。
それが「南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)」の名号となって、私たちの心に「真実(まこと)の信心」となり、口にご恩報謝(おんほうしゃ)の「お念仏」となってあらわれて下さいます。いいかえればこの心〔信心(しんじん)〕行〔念仏(ねんぶつ)〕は、ほとけさまの慈悲心(じひしん)が、私たちに届けられたという証拠なのです。
次に還相の廻向とは、浄土(じょうど)に往生してのちに再び娑婆世界(しゃばせかい)に還(かえ)ってきて、阿弥陀仏の活動に参加させていただくことをいうのです。還相の菩薩(ぼさつ)として活動をさせていただくということは、阿弥陀仏の慈悲心の極(きわ)まりといえましょう。
「往(ゆ)く」も「還る」も、ただ「南無阿弥陀仏」です。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、七高僧(しちこうそう)などすべての善知識(ぜんぢしき)を、浄土からお迎えにこられた方々〔還相廻向の菩薩(げんそうえこうのぼさつ)〕として仰がれたのでした。
ひとくち法話No23 ―真宗の教え8― より

第24話 二種深信
辶(しんにょう)のままで迎(むか)える米寿(べいじゅ)かな
ある寺の伝道掲示板にかかれていました。「迷ったままで88歳にもなりました」というほどの意味でしょう。はじめは何とも寂(さび)しく空(むな)しいことだなと思いましたが、何度も口ずさんでいると阿弥陀仏のご本願にあえた喜びが伝わってきました。
中国の善導大師(ぜんどうだいし)が「わが身は、現にこれ罪悪生死(ざいあくしょうじ)の凡夫(ぼんぶ)にして、昿劫(こうごう)よりこのかた、常に没し、常に流転(るてん)して出離(しゅつり)の縁あることなし」(機の深信 きのじんしん)と現在、過去、未来の3世を通して救われようのない自分であることを深く表白(ひょうびゃく)されています。その大師のお心に通じるものをこの句から感じました。
大師は、続けて「阿弥陀仏のご本願は、かかる衆生(しゅじょう)を摂受(しょうじゅ)したもう。疑いなく慮(おもんばか)りなくかの願力(がんりき)に乗ずれば、定めて往生を得る」(法の深信)とのべられ、阿弥陀仏のお誓いを仰がずにおれない心の確立(かくりつ)こそ大事であると教えられました。
思うに私たちの日常生活は、勝った負けた、損した得した、好きや嫌いやの日送りであり、これが迷いであるとは考えてもみないことです。これが最も救いようのない生き方です。罪悪生死の身であることの自覚は、阿弥陀仏の光にあった証(あか)しです「迷のままで迎える米寿かな」は、この二種深信という教えを通して、すでに仏さまの呼び声を聞いておられるよろこびの歌だったのです。
迷い続けているままが、仏の光に照らされているということでありました。
ひとくち法話No24 ―真宗の教え9― より

第25話 凡夫
アメリカの青年が「アメリカ人は、どんなに自分が悪くても、ごめんなさいとは謝らない。ひとこというと、裁判は負けるし、お金を出さねばならぬから」とテレビでいっていました。私はこれがアメリカ人の生き方かと驚きました。
詩人の相田みつをさんが「損か得か 人間のものさし」といいました。私たちは、心で思うこと、身で行うこと、口で言うことすべて、どんなささいなことでも、自分の都合に立って、損か得かを判断して、ことに処しています。それが当然と思っていたのに、「うそかまことか ほとけのものさし」に照らしてみると、私たち人間のエゴ丸出しの汚い根性と映し出されてきます。
家族の間にも、子どもは子どもの考えで、親は親の権威で、夫は夫の立場で、妻は妻の都合でものをいうので、意見が違うのが当たり前です。そして、自分こそが正しいと張り合うのです。
一般に凡夫というと、愚か者、平凡人、迷えるものなどの意味で使っていますが、親鸞聖人は
「凡夫」というのは、無明煩悩(むみょうぼんのう)、われらが身にみちみちて、欲もおおく、
いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころ、おおくひまなくして、
臨終の一念にいたるまで、とどまれず、きえず、たえず 『一念多念文意(いちねんたねんもんい)』
と、くわしく凡夫という者の心の千変万化(せんぺんばんか)をお示しくださいました。いいかえると、特別なものを凡夫というのではなく、自分の都合を片時もはれることのできない私やあなたのことです。
真宗はこの「凡夫」がお目当ての教えです。
ひとくち法話No25 ―真宗の教え10― より

第26話 歓喜会
真宗では、お盆を「歓喜会(かんぎえ)」といっています。高田本山では、8月14日から16日までの3日間「歓喜会」がつとまります。そして、この期間は、境内で地元のみなさんによる盆おどりがあって、たくさんの人々が集まって賑やかなひとときをおくります。
なぜ盆会のことを「歓喜会」というのでしょう。親鸞聖人は「歓喜」というは、「歓」は身のよろこびです。「喜」は心のよろこびですと解説されています。身も心もよろこぶという、大変なよろこびようを「歓喜」と教えられました。
では、こんな喜びはどんなときにあらわれるのでしょう。親鸞聖人は「私たちが、仏さまの本願(私たち凡夫を必ずお浄土に救いますという願い)を信じて、お念仏を申す心になったとき、このような大きな喜びが自然にでてきます」と申されました。
すなわち、仏さまからいえば、本願が確かであったという証明になり、私たちからいえば、すべておまかせできたという安堵(あんど)であり、仏と私がともに喜ぶさまが歓喜といえます。また「歓喜」というのは、私の自力の限りを尽くしても不可能であった人生課題が、仏さまの願いによって氷解(ひょうかい)した時の喜びですから、日常生活上の喜怒哀楽(きどあいらく)とは次元の違う大きな喜びでもあります。
盆会を「歓喜会」というのは、このような深い大きな意味がこめられているのです。人と生まれ、しかも仏法に遇い得た(あいえた)という不思議ないのちの因縁は、ただただ仏さまからの賜わりものですと「歓喜会」のご縁を通してよろこばせていただきましょう。
ひとくち法話No26 ―真宗の教え11― より
第27話 お浄土
「人は死んだらしまいさ、地獄や極楽なんてありはしないさ。生きている間に、好きなことをしなくては・・・。」
よく世間で聞く話ですが、このような人は、「生死(しょうじ)」の問題を他人のこと、世間のことと考えて、自分のこと、自分の問題と本気に考えていないからではないでしょうか。
世はまさに何が起きるかわかりません。私自身は常住ではありません。いつか必ず命も傷つき終わります。明日がその日にならんとも、です。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は「弥陀五劫思惟(みだごこうしゆい)の願(がん)をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞1人がためなり」と言われました。浄土があると信じることは、他人事ではなく私自身の信心の問題です
私たちは死んだらお浄土に往生させてもらう以外にないのです。
お浄土とはどんな所でしょうか。
阿弥陀仏が成就された世界で、阿弥陀経(あみだきょう)や観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)には、実に美しくて、すがすがしく、にぎやかな世界であると説かれています。
この頃の仏教学は理屈が多く、浄土の有無(うむ)を論じたり、いろいろ経典の比較論考をしたがり、理論や知識に溺れがちですが、お浄土のことについていえば、お浄土は私にとって、なくてはならない仏さまの世界であるのです。
『世尊我一心(せそんがいっしん) 帰命尽十方(きみょうじんじっぽう) 無碍光如来(むげこうにょらい) 願生安楽国(がんしょうあんらっこく)』なのです。
このようにいただけば、この世〔現生(げんしょう)〕の生き方も浄土への道程と領解できましょう。
ひとくち法話No27 ―真宗の教え12― より
ひとくち法話 28~34話 七高僧
第28話 龍樹菩薩
龍樹大士(りゅうじゅだいし)よにいでて 難易(なんい)ふたつのみちをとき
流転輪廻(るてんりんね)のわれらをば 弘誓(ぐぜい)のふねにのせたもう 『高僧和讃龍樹讃第4首』
龍樹菩薩は、お釈迦さまが亡くなってからおよそ500年後に南インドで生まれました。仏教に精通され、多くの書を著されたので「八宗(はっしゅう)の祖」「千部の論師(せんぶのろんし)」等と言われました。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)が、七高僧の第一に挙げられたのは、ほとけになる道を「難易(なんい)のふたつ」にわけて、凡夫のわれらにも、ほとけになる道があるとお説き下さったからです。
そのひとつは難行道(なんぎょうどう)です。これは陸路の歩行のようなもので、山あり谷あり、体力の限りをつくして苦行(くぎょう)するという聖者の道です。もうひとつは易行道(いぎょうどう)といい、阿弥陀如来の本願を信じ念仏を申すというわたしたちが救われる道です。それはちょうど陸路の歩行が困難であるのに対して「水路の乗船」のようなものだという巧みな比喩(ひゆ)で解説されました。
聖人は比叡山での20年間にわたる自らの難行苦行の体験を通じて「流転輪廻のわれら」には易行道であればこそ、ほとけになれるということを明かされました。
「弘誓のふね」は阿弥陀如来の本願をいいます。私たちのただひとつの救いの道であるから、深く信ぜよと聖人は導いてくださいます。
※「難行は、いわゆる仏心(禅宗)・真言宗・法華(天台宗)・華厳宗等の教えであり、易行は真宗である」『愚禿鈔』と聖人は説明されています。だからこの「難易ふたつのみち」は今日でも日本仏教の中に脈々といきづいていることに留意しましょう。
ひとくち法話No28 ―七高僧1― より
第29話 天親菩薩
釈迦(しゃか)の教法(きょうほう)おほけれど 天親菩薩はねんごろに
煩悩成就(ぼんのうじょうじゅ)のわれらには 弥陀(みだ)の弘誓(ぐぜい)をすすめしむ 『高僧和讃天親和讃第1首』
この和讃は高田派の同行ならば誰でも暗唱できる親しみ深いご和讃で、浄土高僧和讃の天親讃の第1首の和讃です。
天親菩薩は世親(せしん)とも言い、七高僧の第二祖です。天親菩薩は今から1600年頃前、北天竺(きたてんじく)でお生まれになりました。お釈迦さまが亡くなられてから900年頃でしょう。
兄の無著(むちゃく)さんと共に仏門に入り、初めは小乗(しょうじょう)仏教を学んでおられましたが、龍樹(りゅうじゅ)菩薩などからの影響もあり大乗(だいじょう)仏教に入られました。
主著『浄土論』は、天親菩薩以後親鸞聖人に至るまで、浄土教の指針になったのでした。
お釈迦(しゃか)さまの説かれた教法は多いけれども、煩悩いっぱいの私たち衆生(しゅじょう)は、阿弥陀如来の私たちを救わねばならぬという誓願以外に救われる道はないと言い切られたのです。
天親菩薩の帰命一心の教えは、現代も生き続けています。
信心すなはち一心なり 一心すなはち金剛心(こんごうしん)
金剛心は菩提心 この心すなわち他力なり 『高僧和讃 天親讃第9首』
なんと1600年も以前(4世紀)の頃の人とは思えない程の的確な言葉で「真実」が現代人に迫ってまいります。
ひとくち法話No29 ―七高僧2― より
第30話 曇鸞大師
斉朝(せいちょう)の曇鸞和尚(どんらんかしょう)は 菩提流支(ぼだいるし)のおしえにて
仙経(せんぎょう)ながくやきすてて 浄土にふかく帰せしめり 『高僧和讃曇鸞讃第1首』
七高僧の第三祖は曇鸞大師と申し上げます。今から1500年程前、中国の雁門(がんもん)、今の山西省太原(さんせいしょうたいげん)あたりのご出身です。
近くの霊地五台山(れいちごだいさん)で出家されました。仏教をはじめ多くの書物を学ばれたので、後に四論(しろん)の始祖と仰がれるようになりました。
しかし、病にかかり、まず長生きの方法を身につけねばと考え、当時の道教の権威であった陶弘景(とうこうけい)から不老長寿の法を学んで、仙経十巻を授けられました。
喜ばれた大師はその帰途、洛陽(らくよう)で菩提流支(ぼだいるし)に出会ったので「仏教の中に、道教で説くよりも立派な不老長寿の法はあるのか」と尋ねましたところ、菩提流支は大地に唾をはいて、その愚かさを笑い「そんな仙経が何になるか、永遠のいのちを身につけるのはこのお経ですよ」といって、『観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)』一巻を曇鸞大師に授け、長生不死の法は、仏教にまさるものはないということを力説されました。
菩提流支の教えに深く感ずることのあった大師は、せっかく持ち帰った仙経を焼き捨てて、深く浄土の教えに帰依されたのでした。
それからの大師は、道教はもちろんのこと自力修行の仏道をすべて捨てて、浄土の教えを明らかにすることに精進されました。
この曇鸞大師のお導きで自力(じりき)と他力(たりき)の教えが明確になり、一層はっきりとお念仏がいただけるようになりました。
ひとくち法話No30 ―七高僧3― より
第31話 道綽禅師
道綽禅師(どうしゃくぜんじ)(562~645)は、曇鸞大師(どんらんだいし)が亡くなられてから、20年目に中国の大原にお生まれになりました。当時は釈尊の没後1500年以上経過していましたから、禅師の教えの根底には、末法(まっぽう)の世に生まれたという意識が流れていました。
禅師は48歳の時、玄忠寺(げんちゅうじ)で、曇鸞大師の功績を讃えた碑文(ひぶん)を読まれ「大師のように知徳(ちとく)のすぐれたお方でさえ念仏門(ねんぶつもん)に入られたのだ。自分のような愚鈍(ぐどん)なものがどうして自力修行(じりきしゅぎょう)の聖道門(しょうどうもん)にとどまることができようか」と感動され、阿弥陀如来(あみだにょらい)のみ教えに入られました。
そして『観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)』を明らかにするため、『安楽集(あんらくしゅう)』を著(あらわ)されました。同時に田舎の7歳以上の子どもたちまでよくわかるように、お念仏を勧められたので、お念仏の声は天地にあふれるほどの盛況でありました。
その道綽禅師を親鸞聖人は、次のようにご和讃しておられます。
本師道綽禅師(ほんじどうしゃくぜんじ)は 聖道万行(しょうどうまんぎょう)さしおきて
唯有浄土一門(ゆいうじょうどいちもん)を 通入(つにゅう)すべきみちととく 『高僧和讃道綽讃第1首』
この末法の時代の私たちにあっては自分の努力で悟りを開き、仏になろうとする聖者(しょうじゃ)の道を通るのはとても難しいから私たちの進むべき道ではないとされました。そして、阿弥陀如来の願いに「はい」と、信順(しんじゅん)する他力念仏門こそが、仏にならせていただく唯一(ゆいいつ)の道であることを明らかにされました。このことを「ただ浄土の一門あり」と主著『安楽集』におっしゃっています。
ひとくち法話No31 ―七高僧4― より

第32話 善導大師
善導大師は、613年(隋の時代)に生まれ、681年、69歳で往生されました。当時、中国では『仏説観無量寿経(ぶっせつかんむりょうじゅきょう)』の研究が盛んでした。大師は、29歳のとき、道綽禅師(どうしゃくぜんじ)を玄忠寺(げんちゅうじ)に訪ねて浄土の教えを学び、その中でも特に『観経(かんぎょう)』を深く学ばれました。
『観経』は、精神を集中して(定善 じょうぜん)仏を観ることや、人さまに親切(散善 さんぜん)する功徳などが説かれていることから、人々に広く親しまれた経典で、大師以前までは、聖者のための経典という理解が主流でした。
しかし大師は、道綽禅師の導きで『観経』の真意は、自力(じりき)で悟りを開くことのできる聖者のためのものではなく、自分の努力では、仏になる縁のない罪悪生死(ざいあくしょうじ)の凡夫(ぼんぶ)がお目当ての教えであることを見抜かれたのです。
従って著書の『観経疏』では、『観経』の今までの誤った解釈を正すものが主となっています。そして、阿弥陀如来の願力によって、罪さわりの多い迷いの生活をしている凡夫(私たち)が、浄土に往生できることを、いろいろな角度から明らかにされました。
親鸞聖人はその功績を「善導独明仏正意(ぜんどうどくみょうぶっしょうい)」
善導ひとり 仏の正意を明らかにせり と讃(たた)えられました。
大師は「真実の仏とは迷える人を救わずしてどうして仏といえようか、十方の衆生を往生させなければ仏にならないと誓って、大慈悲(だいじひ)(めぐみ)を完成された仏が阿弥陀仏です。この仏こそ真実の仏である。」と明言されたのでした。
ひとくち法話No32 ―七高僧5― より

第33話 源信和尚
源信和尚(942~1017、76歳)は、不思議なお坊さまです。『往生要集(おうじょうようしゅう)』という大部な書物を著わされましたが、その書き出しは、地獄の話ではじまっています。
最も恐ろしい地獄を「無間地獄(むげんじごく)」といいます。五逆罪(ごぎゃくざい)や四重禁(しじゅうきん)を犯した者が落ちていく地獄です。五逆罪は家族同士の殺し合いの罪であり、四重禁とは、殺生(せっしょう)、偸盗(ちゅうとう)、邪淫(じゃいん)、妄語(もうご)です。殺し、盗み、淫(みだ)らな行為、うそいつわりです。この世で、こんな悪事を働いた者は、みんな無間地獄に落ちていきます。
頭を下に足を上に吊されて、真っ暗闇の地底へ一人で吸い込まれていきます。どん底には、大蛇が毒を吐き、炎を吹き上げています。落ちた瞬間、体は八つ裂きにされ、その繰り返しで1万年もの責め苦に遭(あ)うと話されています。
昔の子どもたちは、お寺や両親からこのような話をきいて育ちましたが、現在は仏さまの教えを聞く場がなくなって、自分が一番えらいとおだてられて育っていますから、地獄の恐ろしさを知りません。
昨今のニュースをみると、そのつけが来て、家族バラバラで家庭は崩壊していくし、殺生罪の最たる残酷料理がもてはやされ、盗みぐらいは罪とも思わず、みだらな話は日常茶飯事(にちじょうさはんじ)化し、妄語で堂々と歩く世相となりました。
源信和尚の説法は、まことです。親鸞聖人は、邪教が広まっている世をなげいて、是非手を合わせてお念仏が申せる世になってほしいと、源信和尚を高僧さまの1人に加えられたのでありました。
ひとくち法話No33 ―七高僧6― より

第34話 源空上人
源空上人は法然上人(ほうねんしょうにん)の名で親しまれています。
上人は平安時代の末、崇徳天皇(すとくてんのう)の長承2年(1133年)4月、美作(みまさか)の国(現在の岡山県久米南町)でお生まれになりました。親鸞聖人より40年前のことでした。
ご幼名は勢至丸(せいしまる)と申されましたが、勢至菩薩(せいしぼさつ)に似て、よほど智慧のすぐれたお方だったのでしょう。御父君は明石の代官の夜襲を受けて、亡くなられたのですが、その時、枕元に勢至丸を呼んで「父の恨みで代官を『敵討ち』してはならぬ。次はお前も敵対されて、これが代々続いて永遠に恨みとけないものであるぞ」とさとされました。
この遺言が法然上人を仏道に向かわされたと伝えられています。
上人の御事績は数多くありますが、中でも特筆すべきことは『選択本願念仏集(せんじゃくほんがんねんぶつしゅう)』を著されたことでしょう。ここで老若男女や身分の上下に関係なく、お念仏一つでまちがいなくお浄土まいりができると説かれたのでした。
比叡山を去り東山の吉水(よしみず)を拠点に説法される法然上人の許には、庶民も含めて群衆が門前市をなすようでした。ここへ親鸞聖人も観音菩薩の夢告をうけて馳せ参じられました。親鸞聖人は『教行証文類(きょうぎょうしょうもんるい)』の中の「正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ)」に
本師源空明仏教(ほんじげんくうみょうぶっきょう) 憐愍善悪凡夫人(れんみんぜんなくぼんぶにん)
真宗教証興片州(しんしゅうきょうしょうこうへんしゅう) 選択本願弘悪世(せんじゃくほんがんぐあくせ)
と讃歎されたのでした。わが師法然上人がこの世に現れなかったら、浄土の真宗の教えを、庶民に届けることもできなかったと、上人の徳を称讃されたのでした。
ひとくち法話No34 ―七高僧7― より

ひとくち法話 35~44話 高田派
第35話 一光三尊仏
親鸞聖人(しんらんしょうにん)のご一生をたずねると、信心の大事な転機には必ず「夢」の話がでてきます。「夢のような話」といえば、現実離れした架空の出来事の意味になってしまいますが、聖人の夢は「夢告(むこく)」という表現で語られています。
夢を媒介として仏さまが聖人におっしゃる。もう一歩信心を深めて申すなら、聖人自身が仏さまですから、夢告は仏さま同士のお話ということになります。これを「仏々相念(ぶつぶつそうねん)」といっています。
一光三尊仏という尊像は、本寺(ほんじ)(栃木県真岡市高田)のご本尊です。聖人53歳の時「夢告」によって信州信濃の善光寺からお受けされました。
私たちは、この尊像を拝して「阿弥陀仏のお心がどこまでも『われらごとき凡夫(ぼんぶ)のすくい』にあることのお示しである」と伺うことが大切です。すなわち「すべての衆生を浄土に救う」とのお約束はあっても、教えだけでは理解が不十分だから、阿弥陀仏の「慈悲(じひ)の心」を観音菩薩(かんのんぼさつ)と立たれ、「智慧の心」を勢至菩薩(せいしぼさつ)とあらわされて、かたちにまでお示しになり、凡夫の思いが深まるようにとのおはからいが三尊仏となってくださったと思えるのです。
『仏説観無量寿経(ぶっせつかんむりょうじゅきょう)』には「仏心(ぶっしん)というは、大慈悲これなり」と説かれ、『浄土和讃(じょうどわさん)』には「念仏のひとを摂取(せっしゅ)して 浄土に帰せしむるなり 大勢至菩薩の 大恩ふかく報ずべし」と教えられています。
ひとくち法話No35 ―高田派1― より

第36話 本寺と本山
わが高田派には、他派にはない特別な歴史があります。それが、本寺と本山と言うふたつの専修寺(せんじゅじ)です。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)が流罪(るざい)を解かれて関東に行かれたのは42歳(1214)でした。以後60歳を越えて京都に帰られるまでの約20年間を関東で布教活動をされました。中でも53歳の時の夢告によって本寺(栃木県真岡市高田)を建立し、一光三尊仏を信州の善光寺からお迎えしてからは、ここを念佛弘通(ねんぶつぐつう)の拠点として後半の10年間をすごされました。聖人が帰洛されてからは、第2世真仏(しんぶつ)上人、第3世顕智(けんち)上人が中心となって関東で最大と言われる高田門徒を継承されたのでありました。
第10世の真慧上人は、関東だけでなく東海北陸に教線を拡げられました。特に伊勢の念仏者たちの懇請(こんせい)にひかれて、ここ津市一身田(いしんでん)に大伽藍(だいがらん)を建てられました。それが現在の本山です。
その後1526年に本寺の専修寺が兵火のために焼失したこともあって、第12世堯慧上人以降は一身田に住まわれて今日にいたっています。そのため、現在では栃木県の専修寺を本寺と、一身田の専修寺を本山と称して区別しています。
本山の御影堂(みえいどう)は木造の建造物にしては京都の東西本願寺に匹敵し、全国でも五指に入る規模といわれています。大昔のこと、こんな伊勢の地にこれほどの大伽藍が建立されたことは、大きな驚きです。お念仏の教えこそが、ただひとつの浄土への道であるというわれらの祖先の深い信心のあかしでありましょう。
ひとくち法話No36 ―高田派2― より

第37話 高田本山の法宝物
私たちの「真宗高田派本山 専修寺(せんじゅじ)」には、親鸞聖人にかかわる法宝物がたくさん残されています。
親鸞聖人直筆の『三帖和讃(さんじょうわさん)』や『西方指南抄(さいほうしなんしょう)』等は国宝です。重要文化財としては、著書関連の他に只今大修理を行っている建物の御影(みえい)堂や美術品など計20数点に及びます。この他、三重県や津指定の文化財も史跡も多くあります。
高田本山にはなぜこんなに多くの法宝物があるのでしょうか。
高田派は、聖人が関東の高田に本寺専修寺を建立されたことがはじまりで、直弟子の真仏上人や顕智上人が「真宗の法義」を正しく相続されて関東最大の教団となりました。したがって、その当時の法宝物が当然のことながら高田派にこのように多く残されているのです。
そして第10世真慧上人がここ伊勢一身田に本山を移されたときに法宝物も一緒に移されたのです。
以上の法宝物はいわば「形のある財産」ですが、その中には真宗の教えが流れていることを忘れてはなりません。いずれも、真宗のお念仏を後世に伝えるためのものであり、また750年の歴史の中では、善知識(ぜんちしき)をはじめ多くの先輩やお同行たちがこれを守ってこられました。私たち現世に生かされる者は、この法宝物とそのご法義を後世に相続しなければならない義務があると思います。
ひとくち法話No37 ―高田派3― より

第38話 念仏高田
高田派の宗風をいいあらわす言葉のひとつに「念仏高田」があります。みんなに親しまれている「不退(ふたい)のくらいすみやかに」の和讃の中に「弥陀(みだ)の名号称(みょうごうしょう)すべし」という一行がありますが、この心をいいあてた言葉でしょう。
親鸞聖人は、真宗のすくいを「念仏成仏 これ真宗(ねんぶつじょうぶつ これしんしゅう)」とのべられました。「凡夫(ぼんぶ)である私たちがほとけになる道はただひとつ、他力の念仏による」との教えです。
念仏を申すといっても、普通一般には「自分の願いごとがかないますように」とか「罰があたりませんように」などと、心の中で自分の都合のよいことを考えて、その実現を願いながら口でもナモアミダブツを称えていますが、これは欲の念仏、勝手な念仏、呪文の念仏といって、間違った念仏理解だと聖人はきびしくいましめられました。
そして、同じ念仏でも真宗は他力の念仏です。他力とは、ほとけさまのおはたらきです。ほとけさまが「われにまかせよ。われを信ずるものは必ず救う」と約束された。その私たちへの呼び声がナモアミダブツだと聖人は明かされたのです。
だから、わが高田派に「念仏高田」という宗風があるといわれることは、この聖人がおっしゃる正しい「他力の念仏」に立った教団ということでありましょう。
私たち、この高田派に身を置く者にとっては、常にこの大事な伝統の教えに立ち返って、「弥陀の名号称すべし」とほとけの呼び声を聞いていくことが大事であります。
ひとくち法話No38 ―高田派4― より

第39話 文類偈
私たち高田派の勤行は、お朝事は「帰命無量寿如来(きみょうむりょうじゅにょらい)」の『正信偈(しょうしんげ)』です。お夕事は『文類偈(もんるいげ)』の「西方不可思議尊(さいほうふかしぎそん)」です。みなさん幼い頃に、お夕事は家族が仏前に座って、大きな声でゆっくりと節をつけて「西方不可思議尊」を勤行した記憶はありませんか。「私は正信偈より文類偈の方を早く覚えてしまいました」というお方の話を聞いたことがあります。現在でも私たち高田派の者は、たいてい『文類偈』を諳んじています。
真宗十派のうちで、毎日の勤行に『文類偈』を申すのは、わが高田派だけですから、このこともわが派の伝統の一つに挙げることができるでしょう。
両偈文とも1行7字で120行という構成です。教えの内容は、共に"信心の偈(しんじんのうた)"ですから同じです。それなのになぜ『正信偈』は朝に、『文類偈』は夕べに勤めるのでしょう。『正信偈』は、聖人が栃木の高田専修寺でご生活の頃に著された『顕浄土真実教行証文類(けんじょうどしんじつきょうぎょうしょうもんるい)』の中で書かれたものであり、『文類偈』は晩年に書かれた『浄土文類聚鈔(じょうどもんるいじゅしょう)』の中に出てきます。そこで、後で書かれたものを夕事に勤めるようになったというのです。
『文類偈』は「西方」で始まっています。西方極楽世界(さいほうごくらくせかい)〔観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)〕といわれるように仏教では西方は、阿弥陀如来の仏国土を指します。自然界でも西方は太陽が沈みゆくところであり、夕焼けの情景は私たちに絶対の安息を約束する世界のようです。これは人間の純粋感情と申してもよいでしょう。
聖人が、西方から筆を染められたところに『文類偈』の深いお心を汲み取ることができるようです。お夕事にはぴったりの偈文です。
ひとくち法話No39 ―高田派5― より

第40話 御書
私ども真宗高田派では、お寺やお同行のおうちで勤行〔おつとめ(ごんぎょう)〕をすると、最後に必ず『御書』を拝読します。
『御書』という呼び方は、お便りを書かれたお方が親鸞聖人や高田派歴代の上人なので、敬って『御書』の一字をつけて『御書』と申します。
私ども高田派の『御書』は、第14世堯秀(ぎょうしゅう)上人によって編集されたのがはじまりで、巻一から巻七まであり、それに『報恩講御書』を加えて、全部で83通が納められています。
東西本願寺の御文、御文章が蓮如(れんにょ)上人というおひとりが書かれたものであるのに対して、「御書」は親鸞聖人をはじめ真慧上人(第10世)以降の歴代上人方が書かれたお便り(弟子やお同行へのご消息)で成り立っているのが大きな特色です。
よく「高田の『御書』はありがたいですね」と言われるのは、このような内容の違いからであろうと思われます。
ご承知の通り親鸞聖人は晩年に京都から関東のお同行や弟子たちにこまめにお便りを書かれており、また歴代の上人方もお便りの中へ親鸞聖人のお聖教(しょうぎょう)を引用されて、私どもにわかりやすくお示しくださっていることは、誠にありがたいことです。
文章の終わりに「あなかしこ」で結ばれているのは「ああ恐れ多いことです。勿体ないことです。」との領解のこころをあらわした言葉です。
ひとくち法話No40 ―高田派6― より

第41話 野仏と野袈裟
中興上人(ちゅうこうしょうにん)と仰がれている真慧上人(しんねしょうにん)(第10世)は伊勢の地を精力的にご巡教(じゅんきょう)されて、沢山の寺院や念仏道場を作られました。そして布教の重要な手だてとして「野仏」と「野袈裟」という葬儀式の要具を下付けされました。
「野仏」は今でも「野仏さん」と敬称されている阿弥陀如来のお軸で、死者の枕元にかけ、葬列のときには箱に入れて棺の前を歩く習わしになっていました。このことは、阿弥陀如来のお導きでお浄土に往生するということのお示しです。
また「野袈裟」が使われる以前は死骸を村境の墓地に置いてくるだけで、せいぜい土をかぶせる程度だったので、腐乱した死体を鳥獣がつつく光景が人々に地獄を実感させました。真慧上人はこれでは、死者に申し訳ないことと、真宗の教えから「野袈裟」を遺骸の上にかけ、やすらかな死後の往生を念じられたのです。
当時の「野袈裟」は縦1メートル20センチ、幅40センチの絹3枚を横につないだ大きさで、その中央に「南無阿弥陀仏」、その周囲に経文を記したものでした。
このように「野仏」も「野袈裟」も阿弥陀如来さまは、亡くなった方に、どこどこまでもついて離れず、お浄土までお導き下さるということを形をもってお示し下さっているのです。この伝統は高田派だけに遺されているもので、念仏者の願いを如実に具現化してくださった真慧上人のご功績であります。
ひとくち法話No41 ―高田派7― より

第42話 証拠の如来
如来堂(にょらいどう)のご本尊(ほんぞん)は、「証拠の如来」といわれています。
第10世真慧(しんね)上人の時代のこと、本願寺(ほんがんじ)の中興上人といわれている蓮如(れんにょ)さんが、教団を拡張する手段として「帰命尽十方無碍光如来(きみょうじんじっぽうむげこうにょらい)」という名号を同行に配っていました。しかし、同行の中にはこの「無碍(さしさわりのない)」という意味をはきちがえて「この名号を称えておれば、どんな悪事を働いても、往生の障りにはならぬ」といって、集団で乱暴するものがでてきたのです。そして蓮如さんも押さえがきかなくなりました。そこで真慧上人が比叡山に登って無碍光如来の正しい意味を説明し、7日間に亘って真宗の正意を講ぜられましたところ、その博識(はくしき)、弁舌に加えて確かな正意安心(しょういあんじん)に全山の僧侶が感動し、親鸞聖人の再来ではないかとうわさされたといいます。そして、わが高田派こそ真宗の教えを正しく受け継ぐ教団であるといい、その証拠にと慈覚(じかく)大師一刀三礼の阿弥陀如来尊像を真慧上人に献じられました。このことが「証拠の如来」といわれる由縁です。
のちに上人は『顕正流義鈔(けんしょうりゅうぎしょう)』を著して、色々な邪義をくだいて一流の正義を明かされました。
親鸞上人は「無碍というは、如来のおはたらきは衆生の煩悩や悪業に障えられることがない」からだと解説しておられます。
古来から、わが高田派は、真宗の法灯集団だといわれていますが、この証拠の如来にまつわる史実もまた、その証のひとつともいえます。
『高田山証拠如来縁起』より
ひとくち法話No42 ―高田派8― より

第43話 法脈
わが高田派を「法脈」の教団といっています。法脈とは、真宗の教え(法)を「一器の水を一器に移す」ように、正しく継承していくことを第一義とする教団という意味です。
親鸞聖人は栃木県高田に念仏道場(一光三尊仏のお寺)を建立され、ここを拠点にして布教に専念されました。京都に帰られてからは直弟子の真仏上人(しんぶつしょうにん)(第2世)、顕智上人(けんちしょうにん 第3世)が高田教団を相承されました。そして、本山を一身田に移された真慧上人(しんねしょうにん)(第10世)は御書の中で、「肝要は、阿弥陀如来の願力不思議を聞きえて、名号(みょうごう)を唱うべきなり。これ相承直説(しょうじょうじきせつ)なり」と他力信心のこの一点を押さえてご教示なさいました。
この真慧上人については、「証拠の如来」のお話(第42話参照)があります。訳あって正しい真宗の教えを比叡山で講義されたとき、上人を『親鸞聖人の再来ではないか』と全山の僧侶が讃歎されたといいます。
また、堯朝上人(ぎょうちょうしょうにん)(第15世)が幕府の命令に抗して宝法物を死守された事件も、法脈の伝統を天下に示された尊い歴史でもあります。
このような歴代上人の法脈教団としてのお導きは、現在のご法主(第24世)にも受け継がれ、「ひろめよう 念仏のこえ」「深めよう 恭敬(くぎょう)のこころ」と戴くばかりです。
弥陀の本願信ずベし 本願信ずる人はみな
摂取不捨(せっしゅふしゃ)の利益(りやく)にて 無上覚(むじょうかく)をばさとるなり
『正像末和讃 夢告讃』より
ひとくち法話No43 ―高田派9― より

第44話 ほっとするに!寺内町
一身田(いしんでん)の町の電柱に「ほっとするに!一身田町」という看板があちこちに見られます。
一身田の町のことを「寺内町」と言います。寺内町とは大きなお寺を中心に形成された町で、日本の中でも原形を止めている寺内町は数カ所あるあるだけで、一身田は数少ない貴重な寺内町なのです。この寺内町が成立したのは天正8年(1592)頃だと言われ、本山を中心にして、本山へ参詣する人たちに土産物や仏具を売ったり、本山を警護する人や本山の建築物などを保全する役職人が住まいしていました。遠方から参詣する人のために旅籠(はたご)も軒を並べていました。
寺内町の周囲には「環濠(かんごう)」という堀で防衛された、自治都市であったのです。現在もこの「環濠」が完全な形で残っているのは、この一身田だけです。
16世紀頃に出来た寺内町も4~5世紀を経て今日を迎えましたが、昨今はこの町を再び賑やかにしようと、毎年11月に「寺内町まつり」というイベントをして、市や文化財関係者や地元の商工会等によって多彩な行事が行われていることは高田本山にとっても歓迎すべきことでしょう。
しかし、この寺内町がほんとうに「ほっとする」町になるためには、本山にお参りする人が増え、お念仏の声が高まるよう、教団・住民ともどもに精進する課題にとりくまなくてはなりません。
ひとくち法話No44 ―高田派10― より

ひとくち法話 70~83話 お釈迦様のご生涯
第70話 花まつり
釈尊(しゃくそん)は今からおよそ2500年前、北インド(現在はネパール)にお生まれになりました。
釈尊の教えは、どれほど世の中が変わっても、人間というものの本質には変化がないということを示され、今もなお、人々の心に深い感動を与え、生きていくための指針となっています。
伝説では、釈尊がお生まれになる前のある夜、母の摩耶夫人(まやぶにん)は、不思議な夢をご覧になります。「真っ白い大きな象が天から降りてきて、夫人のお腹に入った。」と伝えられています。
夫人と父の浄飯王(じょうぼんのう)は、さっそく、この夢の意味を学者に尋ねました。学者は「これはおめでたい。やがてすばらしい男の赤ちゃんがお生まれになるにちがいありません。」と言いました。
それから1年ちかくたちました。夫人は、おともをつれてカピラ城の東方のルンビニー園に行かれました。夫人は池で沐浴し、枝もたわわに咲き匂う無憂樹(むゆうじゅ)という木の下に立たれた時、男の赤ちゃんが誕生されました。その時、天から「甘露(かんろ)(甘い水滴)」の雨が降り注ぎました。不思議なことに、赤ちゃんは7歩(迷いの世界を超えることを表す)歩き、右の手で天を左の手で地を指して、「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)(1人ひとりの命の尊厳)」と言われました。この赤ちゃんが成長されてお釈迦様になられたのです。
これは4月8日のこととされていて、この日を記念して「花まつり」のお祝いをするようになりました。
ひとくち法話No70 ―お釈迦様のご生涯1― より

第71話 世の無常を痛まれる
シャカ族のカピラ城では、王子さまがお生まれになったという知らせに、人々は大よろこびで、宮殿へお祝いにまいりました。アシタ仙人は王子を見た瞬間、「こんなに立派な王子さまを見たことがない。きっと世界の人々を救われるすばらしいお方になられることでしょう」と言って涙を流して喜びました。
王子さまはシッダッタ太子(目的を達成した人)と名づけられました。
しかし、大変悲しいことがおこりました。太子がお生まれになってから7日後、母の摩耶夫人(まやぶにん)が突然病気で亡くなってしまわれたのです。
こうした悲しみも乗り越えられ、父の浄飯王(じょうぼんのう)や義母や、その他の人々の慈愛をうけて、立派に成長されてゆかれました。
ある日、太子は、なにげなく田んぼの方に目をやりました。農夫が掘りかえした土の中から、ミミズやカエルなど、小さな生き物が出たり入ったりしていました。すると空から鳥が舞いおりて、サッとくちばしにくわえて飛び去っていきました。きっとあの鳥に喰い殺されることであろうと心から悲しまれました。
そして、人間も動物もどうしたら争いがなくなるだろうかと、深くお考えになりました。心のやさしい王子さまであったのでしょう。だから、すべての人々を救わなければならないと、太子は自分自身が苦しまれ、やがて、このお心が、私たちへの願い、お念仏(ねんぶつ)の教えとなって今に伝えられています。
ひとくち法話No71 ―お釈迦様のご生涯2― より

第72話 四門出遊のお話
19歳になったシッダッタ太子(たいし)は、王様のはからいで、ヤショーダラー姫と結婚されました。しばらくの間、夢のような楽しい月日を過ごされましたが、世の無常や弱肉強食(じゃくにくきょうしょく)の世の争いの姿をみることによって、心の中に世のはかなさが、いっそう広がっていきました。父王も太子の心を明るくさせようと、いろいろ苦心されました。
ある日のこと、太子は、お供をつれて東の門から出られました。途中でシワだらけの老人に出会いましたが、その姿を見て、老いることの現実に驚かれました。数日して、太子は、南の門から出ることがありました。そこには髪(かみ)を乱し、顔色は土のようで、手足をふるわす病人をご覧になりました。また西門から出たときは、見慣(みな)れない行列に出会いました。それは葬式(そうしき)の列でした。太子は、私の一番恐ろしいものに出会ったといって、城の中に逃げ帰られました。
「人とは歳をとり、病人となり、そして、死んでいくものなのか、このようなつらい悲しいことのない世界はないのだろうか」と、考え込みました。
最後に北の門から出たときは、質素(しっそ)だが、気高く、堂々とした修行者に出会いました。その姿にうたれた太子は、「そうだ、私の求めている道もあそこにあるのだ。この修行者のように、自分も城を出て修業をつもう。そうすれば、老・病・死の苦しみから逃れる道が見つかるかもしれない」と、心に決められ、ただひとり、悟りの世界に向かって大きな歩みを開始されたのです。
ひとくち法話No72 ―お釈迦様のご生涯3― より

第73話 苦行
お釈迦(しゃか)さまが29歳のある夜。いとしい、妻(つま)と子どもにそっと別れを告げ宮殿をあとにされました。お供には愛馬カンタカと馬の世話係のチャンナだけです。夜通し走り続け、朝方にアノーマー川につきました。そこで、身につけていた宝石や衣服をぬぎすて、カンタカやチャンナとも別れ、ひとり川を渡られました。
この時、お釈迦さまは、どうすれば「生老病死(しょうろうびょうし)」という四つの苦しみから逃れることができるのか、過去未来現在(かこみらいげんざい)の三世にわたる道理を見極めるまでは城には戻るまいと決心されたのでした。
お釈迦さまは、粗末な小屋で雨露をしのぎ、巨樹(きょぼく)の下や、洞穴、岩の上など瞑想(めいそう)する場所を変えながら断食(だんじき)をして、自ら苦行に向かって精進されました。この頃、道理を見極め、悟りをひらく道は自らの苦行しかないと信じられていたのです。骨と皮ばかりになって幾度も生死の境をさまよったといわれます。
このような修業(しゅぎょう)が6年間続きました。「ゴーダマ(当時、お釈迦さまはこう呼ばれていました)は死んだぞ」という噂さえたったのでした。
ひとくち法話No73 ―お釈迦さまのご生涯4― より

第74話 苦行の末に新しい道を
すっかり衰弱しきったお釈迦(しゃか)さまは、「いま自分は、人の世の苦しみをのり越えるまことの道を求めて修業してきたが、こんな弱った体では到底その願いを成就(じょうじゅ)することはできない。体力をつけて健康を回復せねば、真理に到達することはできない。」ということに気づかれました。
そこでお釈迦さまは、6年にわたった苦行(くぎょう)を捨てて、新しい道に進もうと決心され、尼蓮禅河(にれんぜんが)に入って沐浴(もくよく)をし、体を癒して菩提樹(ぼだいじゅ)のほとりに休まれました。ちょうどその時、村長の娘スジャータが通りがかりました。スジャータは衰弱(すいじゃく)しきった中にもおごそかなお姿のお釈迦さまを見て、牛乳で炊いたお粥(かゆ)をささげられました。
そのおかげでお釈迦さまの体力は徐々に回復し、心の疲れも次第にとれて落ち着きがでてきました。そして、お釈迦さまは、今までの長い苦行を振り返りながら、ひとり静かな森の中へ入っていきました。
時代こそ違いますが、親鸞聖人(しんらんしょうにん)もよく似た体験をしておられます。比叡山で20年間修業に励まれましたが、修行すればするほど煩悩にまどわされて、安心の生活ができませんでした。そこで、山を降り、六角堂に参籠(さんろう)され、その結果、吉水(よしみず)におられた法然上人(ほうねんしょうにん)を尋ねられ、「念仏より他に往生の道はない自分」に気づかれました。
お釈迦さまも、親鸞聖人も、いよいよ人間苦悩の世界を乗り越え、真実の道へと進んでいかれたのです。
ひとくち法話No74 ―お釈迦さまのご生涯5― より

第75話 さとり
6年間の山中における苦行によって、心身ともに疲れ切っていたお釈迦(しゃか)さまは、スジャータから乳粥(かゆ)の布施(ふせ)を受けて再び生気をとりもどされました。そして、今度はブッダガヤにある大きな菩提樹(ぼだいじゅ)のもとで瞑想(めいそう)に入られました。
悪魔は相変わらず押し寄せてきて、精神統一をしているお釈迦さまの邪魔をしました。悪魔とは、私たちの眼(げん)・耳(に)・鼻(び)・舌(ぜつ)・身(しん)・意(い)〔六根 (ろっこん)〕から入ってくる誘惑のことです。例えば、美味しい食物の匂いがすると食欲がそそられるといった具合です。自分に都合のよい意見や話には耳を傾けてしまうし、世間の学説や評判を常に気にすることなどは、修行しているものにとってはすべて悪魔なのです。
しかし、お釈迦さまは、今度こそ見事に、これらの悪魔に動ずることもなく誘惑を断ち切って、遂にさとりを開かれたのでした。
さとりとは、
あらゆるものは、縁によって生まれ、縁によって変化し、
縁によって滅するという「縁起(えんぎ)の道理」によることを
明らかにされたのです。
お釈迦さまは、このようにさとられて、私たちに救いの道を説かれることになりました。
さとりをひらいて仏陀(ぶっだ)となられたとき、お釈迦さまは35歳でした。また、さとりをひらいた日が12月8日だったので、この日を「成道(じょうどう)の日」と呼んでいます。
ひとくち法話No75 ―お釈迦さまのご生涯6― より

第76話 梵天勧請
インドでは、さとりを開いた人を仏陀(ぶっだ)(ほとけ)といいます。お釈迦(しゃか)さまが仏陀となられました。
縁起(えんぎ)の法則があらゆる変化、現象のもとになっている。人間はすべて老い、病み、死んでいく。これも縁起の法則によって変わっていく姿なのだ。また、苦の原因がどこからくるのか。貪欲(とんよく)(むさぼり)、瞋恚(しんに)(いかり)、愚痴(ぐち)(おろかななげき)の三毒(さんどく)の煩悩(ぼんのう)もまた、縁起の法則に依って起きてくるのだが、これを人間自身の力で失わせるかどうか。ここまで確かな実証の裏付けがないと人間の救いはありえない。果たして自分の力でできるかどうか。たとえできないとしても仏陀は、この縁起の法を自分だけにとどめておけるものではない。すべての人々に伝え、浄土に救いとるのが仏陀の役割ではないか。
お釈迦さまは、仏陀となられてからも、7週間という長い間瞑想(めいそう)を続けて、仏陀としての使命についてお考えになったといいます。
「自分が悟った真理は、非常に奥深く、極めて難しい。たとえ人々に説いても、理解する者はほとんどいないだろう。」と躊躇(ちゅうちょ)していると、梵天(ぼんてん)(天の神の代表)が現れて、「真理はいかに難しくても、それを理解するものは必ずいます。どうか、真理を説いてほとけになる道を明らかにしてください。」と頼みました。これを「梵天の勧請」といいます。
そこで、仏陀は、この梵天の声に強くゆり動かされて、ようやく立ち上がり、以後45年間の苦難の多い伝道の旅に出発されることになりました。
ひとくち法話No76 ―お釈迦さまのご生涯7― より

第77話 最初の説法
梵天(ぼんてん)(天の神の代表)の強い勧めにより、お釈迦(しゃか)さまは7週間にわたる菩提樹(ぼだいじゅ)下の法悦(ほうえつ)のあと、いよいよ教化伝道(きょうけでんどう)の旅に出られました。35歳の時であります。教法を説く最初の相手を誰にするか。かつて苦行(くぎょう)を共にしていたが、お釈迦さまの苦行放棄を堕落(だらく)と勘違いして去っていった5人に思い付かれました。
ガンジス川を渡りベナレスの町外れ鹿野苑(ろくやおん)に着かれました。5人は、はじめお釈迦さまを堕落僧として無視しようとしたのですが、お釈迦さまの堂々たる威容に接し圧倒され、しらずしらずのうちにひざまずき、み教えに耳をかたむけはじめました。
お釈迦さまは5人に向かって説かれました。
「人間は老い病み死んでいく。すべての存在するものは、因縁(いんねん)によって生まれ、因縁によって移ろい変わってゆくものだ。人間が本当の幸福に到達する道は欲望を捨て、自分に対する執着(しゅうちゃく)を棄て、清らかに生きることだ。私が苦行を棄てたのは決して世俗に還ったのでも、精進努力を怠ったのでもない。私が覚(さと)れる法をあなたたちに教えるでしょう。教えられた通りに行えば出家の目的は達せられて無上の覚りを得ることができるでしょう」と。ここで、5人はいよいよお釈迦さまの説法に随喜(ずいき)し弟子となりました。
この説法を初転法輪(しょてんぽうりん)といいます。転法輪(法輪を転ずる)とは、法を説くことで、教えの輪がだんだんと世の中にひろまっていくことをいいます。それが最初の説法でした。
ひとくち法話No77 ―お釈迦さまのご生涯8― より

第78話 精舎の建立
最初の説法地鹿野苑(ろくやおん)を発たれたお釈迦(しゃか)さまは、各地で説法をつづけられ、多くの人々がみ教えに帰依(きえ)してお弟子となりました。そうしてあの成道(じょうどう)(さとり)の地ウルベーラを目指され、やがて千人の弟子たちを率いて王舎城(おうしゃじょう)に入られました。ここは頻婆娑羅(びんばしゃら)王の領地で6年ぶりの再会に王はもとより王妃韋提希(いだいけ)も大変喜ばれました。それは成道の暁には必ずお会いしますとの約束をはたされたからです。
感激された王は、城の近くの竹林の地を選び、釈尊やお弟子たちのためにお寺(精舎)を寄進されました。これが有名な竹林精舎(ちくりんしょうじゃ)です。
以後ここを拠点としてみ教えは益々広がってゆきました。
そして、舎利弗(しゃりほつ)や親友の目?連(もっけんれん)をはじめ多くの弟子たちもお釈迦さまのもとに入門しました。
更に忘れてはならないのが祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)です。お釈迦さまの故郷カピラ城に近いコーサラ国の首都舎衛城(しゃえじょう)に給孤独(きっこどく)という長者がいましたが、彼は熱心な信者で釈尊にお寺を献上したいと考えました。そうして舎衛城近くの森が最適と思い、地主のジェータ王子に交渉しましたところ、黄金を敷き詰めたら売ってやろうとの難題をもちかけました。しかし、長者は早速に牛車で黄金を運び敷き詰めたのです。地主もその行為が尊いも のと気付き自分も協力したいと申し出たのです。
こうして見事な精舎は、ジェータ王子の樹園〔祇樹(ぎじゅ)〕・給孤独の園という2人の名を冠して祇樹給孤独園(ぎじゅきっこどくおん)、略して祇園精舎として釈尊最愛のお寺となりました。長者こそ初期仏教教団を物心両面で支えた代表的在家信者といえるでしょう。
ひとくち法話No78 ―お釈迦さまのご生涯9― より

第79話 王舎城の悲劇
王舎城はインドの東部にあるお城です。2、300メートルの高さの岩山で、その城壁は今でも残っています。この王舎城で大変な悲劇がおこったのです。
王舎城等を中心にお釈迦(しゃか)さまの弟子は数え切れないほど増えてきました。その中に提婆達多(だいばだった)という人がいました。お釈迦さまの従弟にあたり、頭の鋭い反面、嫉妬心が強く、教団を乗っ取ろうと企み、お釈迦さまを亡き者にしようと恐ろしい計画を立てました。山から岩を落としたり、象に酒を飲ませて踏み殺そうとしましたが、いずれも失敗しました。
そこで、王舎城の頻婆娑羅王(びんばしゃらおう)と韋提希夫人(いだいけぶにん)に阿闍世(あじゃせ)という王子がいるのに目をつけた提婆達多は、その出生にまつわる指の傷が、父王があなたを殺そうとした証であるとそそのかしたのでした。
怒った阿闍世は直ちに父王を牢に入れ死を待つことにしました。しかし、一向に亡くなる気配のないことを不審に思って牢番に尋ねると、夫人が隠し持った食物をしばしば運んだことが分かり、母といえども我が敵であると剣を抜いて殺害しようとしましたが、大臣や侍医にいさめられ、やむなく母も王宮の奥深く幽閉したのでした。
韋提希夫人は阿闍世を産んだ宿業(しゅくごう)の深さを嘆き、身悶えながらお釈迦さまに救いを求めました。そこでお釈迦さまは夫人や未来悪世の衆生のために、極楽世界に生まれるための様々な方法があること、しかし最も大切なことはお念仏を喜ぶ身になることだと教えられました。この教えが『観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)』であります。
ひとくち法話No79 ―お釈迦さまのご生涯10― より

第80話 一所不住のご生涯
お釈迦(しゃか)さまの究極の目的は、真実の智慧(ちえ)を得ること【正覚(しょうがく)】、心の悩みの炎を消すこと【涅槃(ねはん)】、迷いの世界から抜け出すこと【解脱(げだつ)】、でした。そしてその生活は、み仏の心をいただき、それを人々に説き広めるためのものでした。
毎日の生活も、その目的にそって、朝早く起きて瞑想(めいそう)し、托鉢(たくはつ)し、求めに応じて法を説くことでした。質素な衣と托鉢用の鉄鉢(てつはち)だけで、履き物を用いず、乗り物にも乗らず、雨季の3ヶ月は祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)などに滞在された以外は、町から町へ、村から村へと旅をして、み教えを説き廻られたのです。1カ所にとどまらず、足の赴くままに旅をする、いわゆる一所不住のご生活だったのでした。
しかし、さとりを開かれてからの45年間は、ことに因縁の深かった場所で説法されることが多かったようです。たとえば『阿弥陀経(あみだきょう)』はお釈迦さまが最も好まれた祇園精舎で説かれたと、お経の最初に述べられていますし、『無量寿経(むりょうじゅきょう)』や『法華経(ほっけきょう)』などは王舎城(おうしゃじょう)、耆闍崛山(ぎしゃくせん)〔霊鷲山(りょうじゅせん)〕で説かれたと、やはりお経のはじめに出ています。
その耆闍崛山は、『観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)』が説かれた王舎城の牢獄(ろうごく)から歩いて3、40分のところにある岩山でした。
こうしてお釈迦さまのご生涯をたずねてみますとき、親鸞聖人(しんらんしょうにん)もまた、京都から越後へ、越後から関東へ、そして帰洛(きらく)へと一所不住のご一生であったように思います。
ひとくち法話No80 ―お釈迦さまのご生涯11― より

第81話 お浄土への導き『阿弥陀経』
お釈迦(しゃか)さまのご一生はガンジス河流域を巡って各地で教えを説かれました。インドには3ヶ月も雨季がありますから、そんなときには祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)などで説法をされ『阿弥陀経』もそこで説かれました。
『阿弥陀経』は私たちには大変親しいお経です。これはお釈迦さまが74歳のときに、舎利弗はじめ1250人の弟子や、生きる苦しみ、悩み、死んでいく不安にさいなまれている人々に、たとえ死んでいっても、お先真っ暗ではないよ、こんなすばらしい世界があるんだよと、大きく三つのことを説かれました。
第一は、お浄土には池に車輪のような蓮の花が一杯命を輝かせ、すばらしい音楽がどこからともなく聞こえ、こよない鳥の鳴き声が聞こえてくる。それはみな如来(にょらい)が今も説法していてくださることなんだよ。第二は、そのお浄土に生まれるには、ただ仏さまが「南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)」と言葉になって呼びかけてくださる、それに応えて私が「南無阿弥陀仏」と申す時、その声は私からでたのではなく、仏さまの声の山彦と考えてお念仏しなさい。そうしたら、お浄土に生まれることができる。第三は、以上のことは私の独断ではなく、東、南、西、北、下、上方のあらゆる世界の諸仏がたも、私の説いたことをほめたたえてくださっています。
これらを聞いていた人々は、心に一杯の歓びをいただき、お釈迦さまにお礼をして去っていきました。
ひとくち法話No81 ―お釈迦さまのご生涯12― より

第82話 自灯明、法灯明
お釈迦(しゃか)さまは悟(さと)られてから40数年、ガンジス河の流域で教えを説いてまわられましたが、最後は故郷のカピラ城を目指しての教化の旅でありました。
今その疲れ切った老躯(ろうく)をおし、なおインドの大地を歩むお釈迦さまの姿に、私たちは言いようのない畏敬(いけい)と真実への燃えるような熱情に驚嘆し、かえってそこにまた親愛の情さえおぼえます。お釈迦さまはガンジス河を北にわたり、そしてバイシャリーという街へはいられました。そして、阿難をはじめとする弟子たちに、説法をして過ごされましたが、お釈迦さまはここで激痛をともなった重い病気にかかられました。その苦痛を堪え忍ぶ中で、最後の教えを請う阿難に「私は誰彼の差別なく教えを説いてきた。私は年月を重ねて老衰し、このお身はあたかも古ぼけた車が皮紐の助けによってようやく動いているよう なものだ。阿難よ、それゆえ私の死後も他を頼りとせず、誰もが、ただ自己と法とのみをよりどころとせねばならない」と説かれました。これが「自らを灯明とせよ。法を灯明とせよ」と言う有名な教えです。親鸞聖人もこの教えを心とされ、「自灯明」のこころを「南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)によって、仏のいのちを我が命とする輝かしいいのちを果たす人間となれ」、また「法灯明」のこころを「仏の教える真実の道を、己の計(はか)らいを捨てて教えのままに生きよ」と教えられました。
ひとくち法話No82 ―お釈迦さまのご生涯13― より

第83話 釈尊御入滅
雨季がすんで、バイシャリーの街で托鉢(たくはつ)から帰り食事をすませるとお釈迦(しゃか)さまは、バイシャリーに住むすべての修行僧を集め、「自分 は余命いくばくもないが、残された僧たちはおこたることなく修行をしなさい」と諭されました。そしていよいよこの街を去られる時に、はるかにバイシャリーの街を見て、「これがバイシャリーの見納めになるだろう。さあ、阿難(あなん)よ、旅に出よう」といって出発されました。
かねてからお釈迦さまを尊敬していた鍛冶屋チュンダの供養を受けられたお釈迦さまは、多くの美味しい食事の中のきのこ料理が禍して、激しい下痢と腹痛を伴う重い病になりました。お釈迦さまはこの痛みをこらえつつ、阿難とともにクシナガラに入られましたが、ついに「阿難よ、私は疲れた。休みたい」と言われ、サーラ樹の間に身を横たえ、頭を北に、顔を西に、右脇腹を下にして足を重ねられました。その時、サーラ樹は時ならず色が変わったといわれます。お釈迦さまの臨終が迫った時、悲しみの極みにあった弟子たちに「もろもろの事象は移ろい無常である。放逸に堕することなく、修行せよ」と諭され、悲痛な思いで号泣する阿難に対し、これまでの奉仕を謝しそのまま静かに80年の生涯を終えられました。時に2月15日の満月の日でした。
完全な煩悩の滅したさとりのことを涅槃といい、お釈迦さまの入滅を涅槃会(ねはんえ)として、3月15日には高田本山では大きな涅槃図を掲げてお勤めをいたします。
ひとくち法話No83 ―お釈迦さまのご生涯13― より

ひとくち法話 84~92話 聖徳太子
第84話 聖徳太子と親鸞聖人
真宗のお寺には、本堂右余間に「七高僧(しちこうそう)」と「聖徳太子(しょうとくたいし)」の画像が並んで安置されています。これは親鸞聖人(しんらんしょうにん)が聖徳太子を日本のお釈迦(しゃか)さまと仰がれ、太子の仏徳(ぶっとく)を讃歎(さんだん)されたからです。
『皇太子聖徳奉讃(こうたいししょうとくほうさん)』には
大慈救世聖徳皇(だいじくぜしょうとくおう)
父のごとくにおはします
大悲救世観世音(だいひくぜかんぜおん)
母のごとくにおはします
と、あります。聖人は幼少の頃、父と別れ、母と別れられました。けれども聖徳太子さまを父のように、観音菩薩さまを母のようにお慕いして、父母にあっていますと尊ばれたのでした。
御 生 涯
太子は574年、用明天皇(ようめいてんのう)の御子(みこ)として生まれました。その名を厩戸皇子(うまやどのおうじ)、あるいは豊聡耳命(とよとみみのみとこ)といわれました。祖父は欽明天皇(きんめいてんのう)であり、母は蘇我稲目(そがのいなめ)の子の堅塩媛(きたしひめ)でした。
稲目は欽明天皇以上に熱烈な仏教の崇拝者でありました。そのようなご縁で太子は幼い頃から父や母によって仏教崇拝の心を深く植え付けられました。父の用明天皇が即位されて、まもなく亡くなられると、崇仏派の蘇我氏と、排仏派の物部氏(もののべし)との間に戦争が起こったのです。
この時、太子はまだ14歳でしたが、四天王の木像を作り、戦勝を誓われました。戦争は蘇我側の勝利に終わり、崇峻天皇(すしゅんてんのう)が皇位につかれたのでした。
ひとくち法話No84 ―聖徳太子1― より

第85話 日本最初の摂政
太子が15歳の時、「法興(ほうこう)」と年号が改まりました。仏教の教えからつけられたのです。
しかし、崇峻天皇(すしゅんてんのう)5年(592)、執政の衝突から蘇我馬子(そがのうまこ)に天皇が暗殺される事件が起こりました。このような複雑な時代の中で、太子は成長されていかれたのでした。
次に即位されたのは、女帝の推古天皇(すいこてんのう)です。そこで太子(20歳)が摂政として選ばれました。
『皇太子聖徳奉讃(こうたいししょうとくほうさん)』(第56首)に
儲君(ちょくん)のくらいをさづけしに 仏法興隆(ぶっぽうこうりゅう)のためにとて
再三固辞(さいさんこじ)せしめたまひしに 天皇(てんのう)これをゆるされず
とあります。「儲君」とは皇太子におなりになる位です。太子は仏法興隆のためには役立たないと「再三かたく辞退されましたが、天皇はこれを許されず」ということで、摂政(天皇をお助けするお役目)になられたのです。我が国では聖徳太子が最初です。
太子には「豊聡耳(とよとみみ)」というお名前があります。よきさとい耳を持っておられたという意味です。また一度に8人の訴えを聞かれたので「八耳(はちじ)」の王ともいわれました。人々の訴えを正しく理解するためにしっかりと本音を聞かなければならないとして、私たち人間の心を照らし出すほとけの教えに、いつも耳をかたむけられたのでした。
このような聖徳太子の善政によって当時の内乱は見事に治まったのでありました。
ひとくち法話No85 ―聖徳太子2― より

第86話 太子のご功績
憲法17条の第2条に「篤く三宝を敬え、三宝とは仏法僧なり(あつくさんぽうをうやまえ、さんぽうとはぶっぽうそうなり)」とあります。聖徳太子(しょうとくたいし)は三宝を敬うことによって、みんなが平和に生きる世界、仏国をめざされたのでした。
太子の仏教に対する功績としては、四天王寺(してんのうじ)や法隆寺(ほうりゅうじ)などを建立されたことと、もうひとつは勝鬘経(しょうまんぎょう)と法華経(ほっけきょう)を講経され維摩経(ゆいまきょう)を加えた注釈書、三経義疏(さんぎょうぎしょ)を書かれたことは特筆すべきことであります。
太子が政治的に活躍されたのは28歳から39歳ごろまでであります。三経義疏を書かれたのは、36歳から42歳までの間であると伝えられています。太子は49歳で亡くなられますが、晩年は法隆寺の夢殿(ゆめどの)にこもられ、この三経義疏の著述に没頭されたと言われています。
最澄(さいちょう)が法華経を中心とする日本天台宗(てんだいしゅう)を開宗されたのも、太子の思想を受け継ごうとされたものでした。そして親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、太子を「和国の教主」と仰がれ讃えられました。
『皇太子聖徳奉讃(こうたいししょうとくほうさん)』第1首に
日本国帰命聖徳太子 仏法弘興の恩ふかし (にっぽんこくきみょうしょうとくたいし ぶっぽうぐこうのおんふかし)
有情救済の慈悲ひろし 奉讃不退ならしめよ (うじょうくさいのじひひろし ほうさんふたいならしめよ)
と、あります。聖徳太子は阿弥陀仏(あみだぶつ)が、日本の地に現れてくださったのです。その仏さまの教えである念仏に出会って私たちは救われていくのですと親鸞聖人が導いてくださいました。私たちは太子のご恩を讃え、おこたらずに念仏を称えましょう。
ひとくち法話No86 ―聖徳太子3― より

第87話 和国の教主 聖徳王
仏教の開祖は、紀元前5世紀頃にインドで出生されたお釈迦(しゃか)さまです。この仏教が日本に伝来したのは、百済(くだら)(朝鮮半島にあった国)の聖明王(せいめいおう)が、仏像と経論を日本の朝廷に贈ったという欽明(きんめい)天皇の538年でした。
聖徳太子は、この経論を読んで、仏教こそ国境や民族の違いを越えた人類共通の世界宗教であると、自ら法華経(ほっけきょう)、勝鬘経(しょうまんぎょう)、維摩経(ゆいまきょう)という三経を注釈されました。しかも太子は推古(すいこ)天皇のご前で、自らそれを講讃(こうさん)されるという力のいれようでした。
親鸞聖人は、太子がこのように生涯かけて仏法興隆(ぶっぽうこうりゅう)に尽力され、わが国を仏教国として推し進められた功を
和国の教主聖徳王 広大恩徳謝しがたし (わこくのきょうしゅしょうとくおう こうだいおんどくしゃしがたし)
一心に帰命したてまつり 奉讃不退ならしめよ (いっしんにきみょうしたてまつり ほうさんふたいならしめよ)『皇太子聖徳奉讃』
と讃歎(さんだん)されました。このおこころをわかりやすくいえば
聖徳太子は日本のお釈迦さまです。仏の教えを我が国の宗教として定着させるために、自ら経典を註釈し法隆寺や四天王寺を建立し政治の中に仏の教えを正しくとりいれて下さった努力や功績は広大で、報謝のすべさえないほどです。
この上は、私たち国民は挙げて仏法をたずね、一心に阿弥陀仏の本願を聞信(もんしん)して、お念仏をよろこぶ身にならせていただきましょう。太子のご恩を忘れてはなりません
という意味であります。
ひとくち法話No87 ―聖徳太子4― より

第88話 お寺に太子のお軸があるわけ
親鸞聖人は、修行が行き詰まると、聖徳太子のご示現におたずねされたという記録が残っています。
その1は、19歳の時に太子の御廟である磯長(しなが)に参籠(さんろう)されたという記録です。2日目の夜に「親鸞よ、諦(あき)らかに聞きなさい。汝の寿命はあと十余歳です。命終わったら速やかに浄土に往生させましょう」というきびしいものでした。聖人はおどろいて、心を新にして再び比叡山に登って修行に励まれました。
その2は、29歳の時です。いよいよ修行に行き詰まって、太子の創建といわれる京都の六角堂に籠(こも)られて、太子のご示現に賭けられました。その95日のあかつきにようやく太子が観音菩薩の姿であらわれて、「後世(ごせ)のことは、法然上人を訪ねなさい」ということでした。
このように聖人は「和国の教主 聖徳王」(前項参照)、つまり聖徳太子は、日本のお釈迦さまですと尊崇(そんすう)されて、『皇太子聖徳奉讃』という和讃を百首程もお作りになっております。
そこで、真宗のお寺には、この聖人のお心をいただいて太子のお軸を掛けているのです。
註 ご示現とは、「仏・菩薩が衆生(しゅじょう)救済」のため、いろいろ姿をかえてこの世にあらわれること」
ひとくち法話No88 ―聖徳太子5― より

第89話 和を以て貴しとす 憲法十七条
聖徳太子ご生涯の数々の業績の中で、特筆すべきは我が国で初めて憲法を制定された事であります。
『親鸞聖人の皇太子聖徳奉賛』第57首に
太子の御とし三十三(たいしのおんとしさんじゅうさん)
なつ四月にはじめてぞ(なつしがつにはじめてぞ)
憲法製して十七条(けんぽうせいしてじゅうしちじょう)
御てにて書して奏せしむ(みてにてしょしてそうせしむ)
憲法とは国家のあるべき姿を成文化(せいぶんか)したものであり、われわれ衆生(しゅじょう)のために掲げられた規則です。
その第1条に、どなたでもご存じの
「和を以て貴しと為し、忤うこと無きを宗と為よ(わをもってとうとしとなし、さからうことなきをむねとせよ)」とあります。平和を最も大切にし、抗争しないことを規範とせよ、という意味であります。これは和国の実現を天下に示したものであり、憲法の根幹をなすものであります。
私たちがこの世で生きていく上で、和より大切なものはない。みんなが平和に生活することは、いつの世いかなる所であっても、願わずにはおれないことです。
しかし、現実には、地球のどこかで戦火の消えることがなく不安におびえている人々がいるのも事実です。内外をあげて困難な時局に際し、政治の大本を示された太子が、和を憲法の第1条に示されたことに注目したいものであります。
ひとくち法話No89 ―聖徳太子6― より

第90話 篤く三宝を敬え 憲法十七条
聖徳太子制定の憲法第二条は、これもよく知られた
「篤く三宝を敬え、三宝とは仏法僧なり」とお示しになりました。
親鸞聖人も『皇太子聖徳奉讃』の73首に
憲章の第二にのたまはく(けんしょうのだいににのたまはく)
三宝にあつく恭敬せよ(さんぽうにあつくくぎょうせよ)
四生のついのよりどころ(ししょうのついのよりどころ)
万国たすけの棟梁なり(まんごくたすけのとうりょうなり)
と述べられています。
四生〔胎生(たいしょう)、卵生(らんしょう)、湿生(しっしょう)、化生(けしょう)〕とは生きとし生けるものすべてという意味です。三宝の仏は法をさとり実証することのできた人、すなわち覚者のこと、法とは人のすべてが尊敬し信奉すべき真理の道をいい、僧とは僧伽(そうが)の略で仏と法を信奉する人々という意味です。
太子が第2条に掲げられたお心は生きとし生けるものの帰すべきところ、あらゆる国の依るべき心が示され、すべての人が我執(がしゅう)を離れての生き方を教えています。
「それ三宝に帰せずんば、何を以てか枉(まが)れるを直さむ」とこの条文の最後にお示しになっていますが、それは仏法僧(ぶっぽうそう)の三宝に帰依(きえ)し敬うことによって、己の枉った根性をまっすぐに正すことができると教えられているのです。
三宝に帰依し、三法を敬うことによって、和してゆく世界、そこに見いだされる世界を仏国土(ぶっこくど)というのです。
ひとくち法話No90 ―聖徳太子7― より

第91話 共にこれ凡夫のみ 憲法十七条
みんなが平和に生活することはいつの世でも、また誰でも願っていることです。
聖徳太子(しょうとくたいし)は幾多の国をまとめるための仕事をされましたが、その中でも私たちの生き方の支えになることを示さねば、国はおさまらないと考えられ、人間の和を重んじた心のバックボーンを『憲法十七条』としてお示しになりました。
その第10条には人間として一番の争いの元になる「怒り」や「腹立ち」などを戒められ
「十に曰(いわ)く、心の怒りを絶ち、面(おもて)の怒りを棄て、人の違(たが)うことを怒らざれ。人みな心あり。心おのおの執るところあり。彼是(ぜ)とするときは我は非(ひ)とす。我是とするときは、彼は非とす。我必ずしも聖(ひじり)にあらず。彼必ずしも愚(おろか)にあらず。共にこれ凡夫ならくのみ。」
ここには同じ大地に立つ凡夫であるという仏教の教えから考えられる平等思想が貫かれております。
そして人間がどこまでいっても凡夫であること、命終わるまで絶対に消えることはない。これに気づかない限り、国をまとめるような大事業はやれないとお考えになったのではないでしょうか。
親鸞聖人も「凡夫というは、欲も多く、怒り、腹立ち、そねみ、ねたむ心多く暇なくして、臨終(りんじゅう)の一念に至るまでとどまらず、消えず、絶えず」と教えられています。『一念多念文意』
ひとくち法話No91 ―聖徳太子8― より

第92話 聖徳太子と親鸞聖人は仏々想念
聖徳太子は、我が国の文化の創始者であり、その文化の中心には、常に仏教精神を据えて、国民の心をまとめていこうとされました。
憲法十七条の制定は、その精神の最たるものです。第1条の「和(わ)を以(もっ)て貴(とうと)しとなす」も、第2条の「篤(あつ)く三宝(さんぽう)を敬(うやま)え。三宝とは仏(ぶっ)・法(ぽう)・僧(そう)なり」も、そして第10条の「われ必ずしも聖(ひじり)にあらず、かれ必ずしも愚(おろか)にあらず、ともに是れ凡夫(ぼんぷ)ならくのみ」もすべて仏の教えに依っての平和思想であります。
こうした平和への願いは、1400年後の今日に至るまで、それぞれの時代の人々の心を潤してきました。
鎌倉時代初期に出られた親鸞聖人は、その日ぐらしをしている庶民こそが救われなければ、真のほとけの教えではないという立場でしたから、聖徳太子の教えがそのままほとけの教えであるといただかれたのであります。だから聖人は、太子を「日本のお釈迦さまである」と褒(ほ)め讃えられ、『皇太子聖徳奉讃(こうたいししょうとくほうさん)』というご和讃までおつくりになりました。
また聖人は、ご自分の求道遍歴(ぐどうへんれき)の中で、転機に立つたびに太子のご示現を仰がれた話は有名であります。そして、聖人は「太子のお導きがなかったら、真宗の教えもなかった」とまでおのべになっておられます。まさに仏々相念のお心であります。
私たち真宗のご縁にあうものは、この聖人の心を心として、太子を仰ぎ七高僧(しちこうそう)ともども御影(みえい)を掲げて、お慕い申し上げるばかりであります。
ひとくち法話No92 ―聖徳太子9― より

ひとくち法話 93~102話 諸法会
第93話 修正会
正月に修する法会なので修正会といいます。年のはじめに心を新たにして、仏前に座し合掌礼拝し、お念仏を申し上げます。高田本山では、元旦から3日間厳修(ごんしゅう)されます。
修正会には必ず「繙御書(ひもときのごしょ)」が拝読されます。ひもとくとは巻物のひもをとくという意味です。1年の始めに拝聴する御書のことです。この御書は、第18世の圓遵上人(えんじゅんしょうにん)がお書きになりました。大変な長文です。年のはじめにあたって忘れてはならない仏法の要をわかりやすく説かれており、克明(こくめい)に求道(ぐどう)のこころを諭してくださっています。
その要旨を箇条書きにすると以下のようになります。
1、生者必滅(しょうじゃひつめつ)の道理。寿命は老少不定(ろうしょうふじょう)の世の中だから、新年を迎えて喜んでもいつの間にか夏がきて秋暮れて、また1年が経ってしまう。1日1日を無駄に過ごさぬよう。
2、身にしてはならぬこと、口に言ってはならぬこと、心で思ってはならぬことがある。因果応報(いんがおうほう)の業道(ごうどう)は、秤のように必ず重い方に牽くから身(しん)・口(く)・意(い)の三業(さんごう)を常に慎むこと。
3、 煩悩(ぼんのう)いっぱいのわれらは、他力念仏(たりきねんぶつ)の法に依らねば浄土往生(じょうどおうじょう)は不可能です。この道を誓われた阿弥陀仏(あみだぶつ)、この教えを伝承されたお釈迦さまと七高僧(しちこうそう)の広大な恩徳(おんどく)に報謝(ほうしゃ)せよ。
4、先ずは父母孝養(ぶもきょうよう)の心を第1とし、父母存生(ぶもぞんしょう)の日は孝順(きょうじゅん)を先とし、没後は法事を怠ることなく報恩(ほうおん)につとめよ。そして、六親眷属(ろくしんけんぞく)むつまじく、互いに信心をみがきなさい。
ひとくち法話No93 ―諸法会1― より

第94話 涅槃会
お釈迦さまは、35歳の時、さとりを開いて仏陀となられました。それから45年間は、インド各地を行脚
ひとくち法話No94 ―諸法会2― より

第95話 讃佛会
「暑さ寒さも彼岸(ひがん)まで」と言います。春分の日を中心に1週間、秋分の日を中心に同じく1週間、この春秋二季の彼岸は、日本人の心に根付いている心温まる意識です。
彼岸は仏典に出てくる言葉で、パーラミターというインド語を訳したものです。彼岸とは到彼岸(とうひがん)の略で、迷いの世界(この世)から悟りの世界に到るということです。この迷いの世界を此岸(しがん)といい、如来の悟りの世界を彼岸と名付けています。
宗祖親鸞聖人(しゅうそしんらんしょうにん)は「人みなこの此岸、つまり人間世界から彼岸への途を歩まねばならない」と申されています。
此岸から彼岸へのこの道は阿弥陀如来ご回向(えこう)の道であります。浄土への道は実は浄土からの呼びかけの道であります。彼岸会はインド、中国にはなく日本独特の法会です。真宗では彼岸の1週間を仏徳(ぶっとく)を讃嘆(さんだん)する場として、また聞法(もんぼう)のご縁の場として大切にしています。
したがってわが高田派でも、彼岸会を讃仏会と称して、仏にお礼を申し、仏を称える法会を勤めているわけであります。ご和讃に
生死(しょうじ)の苦海(くかい)ほとりなし
ひさしくしずめるわれらをば
弥陀(みだ)の悲願(ひがん)のふねのみぞ
のせてかならずわたしける 『高僧和讃龍樹菩薩讃第7首』
と親鸞聖人がお述べになっておられるとおり、苦悩の世界(此岸)に沈んで久しい私達は、阿弥陀様の悲願によって救われる(彼岸)のであります。
ひとくち法話No95 ―諸法会3― より

第96話 十万人講法会
毎年4月6日より10日までの5日間、本山において桜が満開に咲く季節に厳修(ごんしゅう)されておりますのが、十万人講法会であります。
この法会は、真宗高田派十万人講財団が主催する法会ですが、十万人講財団とは、何時から、どんな目的で始められたのでしょう。それは、大正8年(1919)に専修寺(せんじゅじ)第22世の堯猷上人(ぎょうゆうしょうにん)が設立され、御法主を総裁に戴く高田派の護持財団であります。
財団は、檀信徒の皆様からいただいたご懇志(こんし)を基金として運営し、それによってこれまで80余年の歴史を経て今日に至っております。
その主なる事業は、
1、高田派の教学振興
1、布教活動の助成
1、慈善事業の援助
等でありますが、最近では本山における恭敬(くぎょう)研修費や出版物の費用、高田派福祉協会への補助金等にも助成をしております。
協賛いただいた方には、ご芳名を十万人講だよりに掲載されております。十万人講法会には、加入者全員に案内状が差し出され、如来堂において加入者の法名を敬置し盛大に勤行が営まれています。
ひとくち法話No96 ―諸法会4― より

第97話 戦没者追弔法会
如来堂(にょらいどう)西側の位牌堂(いはいどう)には、明治以後の大戦で戦死されたお同行の方々の位牌が安置されています。
この法会は、毎年4月11日ご法主殿・ご法嗣殿をはじめ、僧侶、遺族、一般参詣者で賑々しく厳修(ごんしゅう)され、戦死された方々の当時をおしのびすることであります。
親鸞聖人が真実の教えと仰がれた『仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう)』の一節に
佛所遊履(ぶっしょゆうり) 国邑丘聚(こくおうくじゅ) 靡不蒙化(みふむけ)
天下和順(てんげわじゅん) 日月清明(にちがつしょうみょう) 風雨以時(ふうういじ)
災厲不起(さいれいふき) 国豊民安(こくぶみんなん) 兵戈無用(ひょうかむゆう)
崇徳興仁(しゅとくこうにん) 務修礼譲(むしゅらいじょう) 『鎮国文(ちんこくもん)』
と、説かれています。この文を分かりやすく換言しますと、
「仏が行かれるところは国も町も村も、その教えにさからうようなことはない。そのため世の中は平和に治(おさ)まり、太陽も月も明るく輝(かがや)き、風もほどよく吹き、雨もよい時に降り、災害や疫病などもおこらず、国は豊かになり、民衆は安穏(あんのん)にくらし、軍隊や武器をもって争うこともなくなる。人々は徳をもって思いやりの心で、あつく礼儀を重んじお互いにゆずり合うのである。」とおおせられました。
このような尊い教えをいただきながら、悲惨な戦争が繰り返されているのは、全く悲しいことです。私たちの家庭や日常生活を反省してみますと、親鸞聖人の"世の中安穏なれ 仏法ひろまれ"と申されるおことばがお念仏とともに力強く私たちの心に響いてまいります。
ひとくち法話No97 ―諸法会5― より

第98話 千部法会
毎年4月12日から17日までの6日間厳修(ごんしゅう)されます。第16世堯圓(ぎょうえん)上人によって始められた法会です。千部という名称は、その昔親鸞聖人が関東に赴かれる途中、人々の生活の悲惨さを目の当たりに見られて、その人々の幸せのために『浄土三部経(じょうどさんぶきょう)』を回数多 く読誦(どくじゅ)しようと思いたたれたという故事にならってつけられました。今でいう永代経法会(えいたいきょうほうえ)のこころです。
一般に永代経法会というと、亡くなった先祖が少しでも早くお浄土へ往生してもらうための供養法事(くようほうじ)だと思いがちですが、そうではありません。この法会の主役は亡くなったご先祖です。あとに残った私たちに「仏法を聞きなさい」「お念仏を申しなさい」と呼びかけて下さった大事な法会なのです。私たちが先祖のためにではなく、すでに浄土に往生されたご先祖が、私たちのためにであります。
高田本山では、法会期間中、加入者の法名帳が中央卓に置かれて、法主(ほっしゅ)殿、法嗣(ほうし)殿のご親修(しんしゅう)のもと、多くの僧や一般参詣者で賑々しく厳修されています。江戸時代には、報恩講以上の賑わいを見せていたと伝えられています。
現在、本山の境内には俳人芭蕉の弟子の珍碩(ちんせき)が詠んだ
「千部読む 花の盛りの 一身田」
という句碑が立っています。
千部が始まった当時の賑わいが偲ばれます。(句碑の文字は、第23世堯祺上人の揮毫)
ひとくち法話No98 ―諸法会6― より

第99話 親鸞聖人降誕会
宗祖(しゅうそ)親鸞聖人は承安(しょうあん)3年(1173年)の5月21日に、京都の東南にあたる日野の里で誕生されました。幼にして両親と死別し、どんなにか悲しい、淋しい思いをされたことでしょう。9歳で得度(とくど)された時、
「明日ありと思う心のあだ桜、夜半(よわ)に嵐の吹かぬものかは」
と詠まれた話は有名です。
聖人は、その後20年間、比叡山で修業に専念し下山後、師の法然上人との出会いに縁(よ)って、遂に他力念仏の奥義を領解(りょうげ)されたのでした。換言すると、私たち凡夫が、ほとけに成るみちすじを明らかにして、これこそ真宗(真実の教え)であるとお示しくださったということです。
降誕会は、普通はお釈迦さまの誕生をお祝いする行事ですが、このように私たちの真宗では、「親鸞聖人は阿弥陀如来の応現(おうげん)である」といただくところから、特に聖人のご誕生を降誕会といって、お祝いの行事にしているのであります。
聖人は、法然上人との出遇いをよろこばれて『高僧和讃』に
曠却多生(こうごうたしょう)のあいだにも 出離(しゅつり)の強縁(ごんえん)しらざりき
本師源空(ほんじげんくう)いまさずば このたび空(むな)しくすぎなまし 『源空讃第4首』
とのべられています。
私たちにとってみれば「親鸞聖人がこの世に出て、お念仏の教えを説いて下さらなかったら、この度の人生も空しくすぎてしまったことよ」ということになりましょう。
降誕会には、聖人90歳のおとしを「祖師寿(そしじゅ)」といい、同い歳の男子のお同行をご本山に招待して、仏縁をともにお喜び申し上げています。
ひとくち法話No99 ―諸法会7― より

第100話 歓喜会
日本では、昔から正月と共に盆は年中行事として、遠く離れた人も故郷に帰りお墓やお寺へ参る習慣があります。これは亡き人への追慕が仏縁を通して深められる麗しい風習でありましょう。
お盆というと、亡くなった人がこの世に還ってくるとか、他宗では施餓鬼(せがき)といった法要が勤まりますが、高田本山では盆法会を歓喜会と称して、毎年8月14日から16日まで3日間厳修(ごんしゅう)されます。
お盆とは、正しくは盂蘭盆(うらぼん)と言い梵語(ぼんご)のウランバナが原語で救倒懸(きゅうとうけん)と訳します。倒懸とは逆さ吊りのことで、大変な苦しみですがその苦しみから救われるというのがお盆です。
『仏説盂蘭盆経』には目連尊者(もくれんそんじゃ)というお釈迦さまのお弟子が神通力で亡き母を尋ねたところ、餓鬼道に堕(お)ちていました。何とか助けようと努力しましたが、どうしても救いだすことが出来ず、お釈迦さまに助けを求めました。お釈迦さまは、7月16日は夏安居(げあんご)(夏季研修終了の休養日)だから僧侶を招いて、懇ろにお経をあげてもらいなさいとお諭しをされ、母が餓鬼道から救われたと述べられています。
これらのお話から、逆さ吊りの苦は、自己中心の生活、自らの苦を増大しているたとえであり、目連尊者については、我が子可愛いさのあまり、母が貪欲にはしったのは、自分に原因があるとの慚愧の思いからであると味わいたいものです。
真宗でお盆の法会を歓喜会というのは、自分を振り返って慚愧の中に仏恩報謝(ぶっとんほうしゃ)をさせていただき、信心歓喜(しんじんかんぎ)してお念仏申すからであります。
ひとくち法話No100 ―諸法会8― より

第101話 納骨堂法会
本山では毎年11月3日、4日に納骨堂法会が厳修(ごんしゅう)されます。
どこの家庭でも、家族が亡くなればご遺骨をお墓に納めてお参りをし、亡くなった方の遺徳をしのびながら、自分の生き方を見定めます。また、本山へも納骨(分骨)を致します。それは何故でしょうか。
仏教では、遺骨を大切にします。それは、亡くなった方々を通して後に残った人々が、阿弥陀さまの摂取(せっしゅ)してやまないご本願によって、必ず救って下さるという教えにあわせていただくからです。
お釈迦さまが亡くなられた時に、お釈迦さまの死を悲しみ、そのご遺徳をしのんで、弟子たちがお釈迦さまの遺骨〔舎利(しゃり)〕を分けておまつりした事が始まりだといわれています。
親鸞聖人のご遺骨は、顕智上人(けんちしょうにん)によって関東に運ばれ、聖人の墓所に納骨されました。
高田本山のご廟にも親鸞聖人のご遺骨が納められています。私たち高田派の同行は、それ以来、親鸞聖人のみもとでお浄土に生まれる幸せを共にしたいという想(おも)いから、本山に納骨する習慣ができて今日に至っています。
納骨堂法会は、法主殿、法嗣殿、僧侶の方々、納骨堂加入者の方々、一般の参詣者で盛大に営まれます。
参詣者一同、お同行の方々ともどもこの法会を機縁として、より一層、同じところで亡き肉親や先祖への感謝のおもいを確かめ、聖人のみもとで仏恩報謝(ぶっとんほうしゃ)のこころをもって聞法(もんぼう)の一時(ひととき)に遇(あ)わせていただきましょう。
ひとくち法話No101 ―諸法会9― より

第102話 御正忌報恩講
報恩講は、宗祖・親鸞聖人のご命日である1月16日をご縁にして厳修されます。1月9日から16日までの七昼夜にわたっての法会なので"お七夜さん"の名で親しまれています。
文字通り報恩講は、聖人にお礼を申し上げる法会です。それは煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)ですから、地獄・餓鬼・畜生の三悪道(さんなくどう)に堕(お)ちて当然の私たちが、お浄土に往生して、ほとけにならせていただくという想像もできない他力念仏の大道をお教え下さったからです。聖人は「この強縁(ごんえん)は多生(たしょう)にも値い難い(あいがたい)こと」として、和讃に
如来大悲の恩徳は 身を粉にしても報ずべし
師主知識の恩徳も 骨をくだきても謝すべし 『正像末法和讃58首』
と述べられました。私たちは、この和讃を特別に恩徳讃(おんどくさん)と申しております。阿弥陀仏(如来)が「わが名を称えるものは、必ずお浄土のに往生させます」という超世(ちょうせ)の願い〔大悲(だいひ)〕を成就され、お釈迦さま(師主)がこの世に出られて説法され、その道理を三国〔さんごく(インド、中国、日本)〕の七高僧(知識)が正しく伝承されて、ついに「南無阿弥陀仏」が私たちに届けられたのでありました。聖人は、この経緯を自らの喜びとして、くわしくお示しされたのが真宗の教えです。聖人は、このご縁は何ものにも代えることができない尊いことだから「身を粉にしても、骨をくだいても報謝すべし」と最大級のお言葉で申されたのであります。
お七夜さんには、全国から万余のお同行が参詣されて、お念仏の声が絶えません。
ひとくち法話No102 ―諸法会10― より

ひとくち法話 103~110話 四苦八苦
第103話 生苦
お釈迦さまは、「人生は苦なり」と仰せになっています。その「苦」には、例えば、二苦(内苦=自己の心身より起こる苦、外苦=外的作用により起こる苦)、三苦〔苦苦=不快なものから感じる苦、壊苦(えく)=好きなものが壊れることから感じる苦、行苦=ものごとが移り変わることを見て感じる苦〕などがあるといわれます。
これらの苦しみを、お釈迦さまは、まとめて生・老・病・死の四苦として大きく問題にされ、その解決のために出家されたのでありました。さらにこの四苦に愛別離苦(あいべつりく)・怨憎会苦(おんぞうえく)・求不得苦(ぐふとっく)・五蘊盛苦(ごうんじょうく)の四苦を加えたものを八苦と言われています。つまり前の四苦は、人間の生きものとして起こる苦しみであり、後の四苦は、人間が人間であるために味わう苦しみを言われたものです。
この苦しみは、人生において避けて通れない苦しみです。かけがえのないこの世の生き方を考えるとき、この四苦八苦に対する心構えが根源になければなりません。
生苦とは、人としての基盤、生まれ、生きるすべての苦しみのおおもととなるのです。まさに人として生まれることによって、すべての苦しみがつきまとっています。
親鸞聖人は、このような生苦を背負って生きているすべての人が救われなければならない、この生死(しょうじ)の苦海を渡る道は、阿弥陀仏の本願念仏の一道を信ずるほかないと、生涯を説法することに完全燃焼されたのでありました。
ひとくち法話No103 ―四苦八苦1― より

第104話 老苦
お釈迦様が、人生は苦なりと仰せになっていますが、その中には老いることの苦しみが含まれています。誰しも歳はとりたくない、老いたくはないと考えますが、避けて通ることが出来るでしょうか。
一般に歳をとると、体が自由に動かない、視覚や聴覚も衰える、バランスがとりにくい、動作がにぶくなる、物忘れが激しくなる等感ずることであります。医学の立場からも、骨折、失禁、認知症を老人の三大症候群と言っています。
老醜はありて老美は辞書になしと言われますように、老いた人、古くなったものは、くたびれたもの、間に合わないものという通念がありますが、そういう概念だけで処理は出来ない筈です。老苦という言葉が示すように、確かに老いは苦であります。しかし美しく老いた姿には、若者に見られない安らぎがあります。長い年月を通して風雪に耐え、人生の悲しみも喜びも味わってきた老人には、深く美しい年輪が刻まれて、そこはかとなく安らぎを感じさせるものがあります。常に前向きの心を崩さない老人には、強靭な力さえ感じることがあります。
肉体は衰えるが こころの眼がひらく 人間の晩年は面白い
今まで生きて いのちの深さが見えてきた
法悦の詩人 榎本栄一さんの詩です。いのちの尊厳に目覚め「こころの眼がひらく」ことによって、自由無碍の世界をゆったり歩むことが出来るのでありましょう。
ひとくち法話No104 ―四苦八苦2― より
※2004年から、痴呆は認知症ということばに変わりました。

第105話 病苦
お釈迦様は、人間には生・老・病・死の四つの苦しみがあることに気付かれ、その苦しみからどうすれば逃れるかという思いから出家されて苦行のすえ悟りを得られました。
病には病状の軽いものから不治の病まであります。現在ではガン、心疾患、脳卒中が三大生活習慣病として恐れられています。
健康の裏側には病苦がある。それは逃れたいと思っても逃れられない事実であって、誰でもさけて通れないものであります。
では、病苦をどう受けとめたらよいのでしょうか。それは病を得たことで病を肯定し、そこから生かされているわが身に気付かせてもらうことであります。
ガンを告知された知人が、
「元気な時は分からなかった親鸞聖人のみ教えが、自分が病気になって、初めてわが身にしみて伝わってくる。」
と話してくれました。
「病気になったあと、あれこれ悩み、迷信に走ったりしなくても、安心してまかせられる尊いみ教えを聖人は一生かけて、私達のために説いて下さった。それを信じて生きていけば、何も心配はいらない。」
というのです。
生死の苦海ほとりなし ひさしくしづめるわれらをば
弥陀の悲願のふねのみぞ のせてかならずわたしける 『龍樹菩薩第7首』
と和讃される聖人のおことばを信じて生きていくことこそ、苦しみをのりこえていくことだと思います。
ひとくち法話No105 ―四苦八苦3― より

第106話 死苦
生・老・病・死(しょう・ろう・びょう・し)という四苦(しく)は、身体面からみた代表的な苦です。この中でも死に対する苦は、その最たるものでしょう。ある人が、死苦の起因する問題点を3つに分けて発言していました。その1は、どんな死に方をするか。その2は、この息が止まる時の苦しみはどんなものか。その3は、死後はどうなるのかということです。これらはすべて未知、未経験のことばかりですから3点の思いが重なり合って、不安や恐れ怖さがこの上なく増すわけでしょう。
また或る大金持ちが主治医に「私は死ぬのが怖いです。お金ならどれだけでも出しますから、私を死から救って下さい。」と懇願したという話があります。どれほど地団駄踏んで泣き叫んでも、逃れることが出来ないと承知していながらも、このように頼む心が出てくる程「死苦」は根が深く重いということです。
『御書(ごしょ)』のいたるところに「後生(ごしょう)の一大事に心をかけて、仏法を聴聞(ちょうもん)せよ」と説かれています。これは即ち「死苦」に対する説法です。後生は、死後のことです。一大事は、これ以上の大事なことはないという意味です。
私のいのちは、この身体の生、死にかかわらず前世、現世、後世の三世を貫通して、しかも因果応報(いんがおうほう)の道理によって受け継がれていくものであると仏教は説いて下さっています。
だから、死後のことは、生きている間に仏法を聞いて、はっきりさせておくことが何よりも肝要であります。
ひとくち法話No106 ―四苦八苦4― より

第107話 愛別離苦
「愛別離苦」とは、原始経典によれば「愛しいものと離れることも苦である」とされます。これは、愛するものとか、いとしい人とかが愛であって、それと離別する苦しみということです。いかなる愛にも、別離のない愛はなく、いつかは必ず別れなければならないというのがこの世の真相であり、それが愛と別離する苦と呼ばれます。
私たちは人をいつくしみ、物を大切にしなければならないと考えて生きています。しかし、その愛情が大きければ大きい程、それを失った時の苦痛も増大することとなるのです。では、愛することをしなければ良いのかというと、愛なくして生きることの出来ないのが現実で、この矛盾の構造の中に生きているのが人間の姿であり、苦界であるということです。
また、仏教では「愛」を、他をいつくしむという意味よりも、愛執(あいしゅう)・渇愛(かつあい)・欲愛(よくあい)とされるように、人間の自己中心的な執着(しゅうちゃく)、すなわち煩悩の意で解されています。よって、この愛執の炎がさかんになることによって、苦悩に迷い続けなければならないとされるのです。まさに生死(しょうじ)の大苦海に浮き沈んでいる煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)の姿といえましょう。
その煩悩具足の凡夫が、そのままに、罪障を滅して、さとりの世界であるお浄土に往生させていただくのは、お念仏の他にないことを示してくださっているのが、親鸞聖人の次のご和讃です。
恩愛(おんない)はなはだたちがたく 生死はなはだつきがたし
念仏三昧(さんまい)行じてぞ 罪障(ざいしょう)を滅し度脱(どだつ)せし 『高僧和讃 龍樹讃第10首』
ひとくち法話No107 ―四苦八苦5― より

第108話 怨憎会苦
「怨憎会苦(おんぞうえく)」とは、私たちが生きる上で必ず出会わなければならない苦しみであるとされます。この苦しみは、前の「愛別離苦(あいべつりく)」と表裏となる真理であります。私たちは、好ましいものを近づけ、好ましくないものを遠ざけようとしてしまいます。しかし、そのようにならないのが現実で、これが苦の根源となるのです。
自分自身がこうしようと考えていても、その通りに行動できないことが多々あります。自分自身の場合だと、簡単にあきらめがつくのですが、他の人が相手の場合だと、簡単には了承しかねます。かといって、人間は独りぼっちでは生きられません。常に他の人との関わりの中にしか生きられないのです。
身近な例では、嫁と姑との対立があります。お互いが相手のことを思い、気に入られようとする思いが強いほど、それが相容れられない時に怨みや憎しみを抱くことになってしまうのです。それを避けて、別居してしまえば良いのかというと、それでは家族関係が崩壊してしまいます。やはりお互いに助け合い、支え合わないと生きてゆくことは出来ません。
私が憎いと思っている人こそが、自分にとっては大切な人であり、自分のことをしっかりと気に懸けてくれている人なのではないでしょうか。ちょっと相手の身になって考え直してみませんか。
愛する人との 別れもつらいけど 会いたくない人に
会うのも苦しみ なんだよ 怨憎会苦 というんだね 相田みつを
ひとくち法話No108 ―四苦八苦6― より

第109話 求不得苦
求めて得ざる苦しみを求不得苦と言い、四苦八苦の1つに数えられているものであります。「人生は苦なり」とは、すでにお釈迦様が教えておられることですが、思うことが思うようにならないのが苦の本質であります。
欲しいものがあれば、それを手に入れることに躍起(やっき)になり、無理を通し、他を押しのけ、自分の思うようにならなければ、腹を立て、ねたみ、心が静まることがありません。また、自分に直接かかわりがないとなると、つい無関心になってしまいます。
自分の思うようになる、自分の願望が満たされることが幸せだと思っているとすれば、それは例え一時的に実現したとしても、必ず崩れさってしまうのが常であります。
お釈迦さまが説いておられますように、この世の中は、すべて縁起(えんぎ)(因縁生起)の理に従って展開するのでありますから、必ずしも思うようにならないのであります。
他人の意志ではなく、自分自身の意思でさえも思うようにならないことを思えば、思うようにしようとすることさえ、むなしい事ではないでしょうか。しかし私達は常にすべてを自分の思うようにしよう、あれも欲しい、これも欲しいと考えて生きているからこそ、苦から逃げることが出来ないと思うのであります。
栃木県の人で、生活の中で仏法を味わい著書も多い相田みつをさんは、「損か得か、人間のものさし。うそかまことか、仏さまのものさし」と述べられています。
ひとくち法話No109 ―四苦八苦7― より

第110話 五蘊盛苦(ごおんじょうく)(ごうんじょうく)
「五蘊盛苦」は四苦八苦の最後に説かれる総括的な教えです。五蘊とは5つの集まりで、人間は肉体である色(しき)と精神である受(じゅ)(感受作用)・想(そう)〔表象(ひょうしょう)作用〕・行(ぎょう)(形成作用)・識(しき)(識別作用)とが和合して構成されています。まさに煩悩具足の私たちの在り方そのものを示しています。
家の中で寝ている時などには、トラブルに巻き込まれたり苦しみにさいなまれたりすることは少ないのですが、外で活発に活動すると、様々な軋轢(あつれき)を生じて苦しみに遭遇することが増してしまいます。
だからといって、何もしないでじっとしている訳にはいきません。より良いことを求めて努力しなければならないと考えて、頑張らざるを得ないのです。
だから、生きようとすればするほど四苦八苦の苦脳に陥ってしまうのです。その原因が私たちの自己中心的な欲望である煩悩(ぼんのう)の仕業だとお釈迦様は説かれています。その煩悩を自力の努力によって断(だん)じるのではなく、その煩悩にまみれた私を、何とか救い導いて悟りを得さしめようと願い求めて下さっているのが阿弥陀如来のご本願です。
人生には常に苦楽がつきまとうのです。生死無常(しょうじむじょう)の世にあって、極悪深重(ごくあくじんじゅう)ののがれがたい私たちをこそ救わんと働いてくださっているのが本願成就(ほんがんじょうじゅ)のお念仏なのです。このことを聖人は次のように和讃されています。
生死の苦海ほとりなし ひさしく沈める我らをば
弥陀の悲願の船のみぞ 乗せて必ず渡しける 『高僧和讃 龍樹讃第7首』
ひとくち法話No110 ―四苦八苦8― より

ひとくち法話 111~122話 こころ
第111話 もったいない
ごはんをこぼすと「もったいない」。まだ使えるものを捨てるのは「もったいない」。大事なものを失くして「もったいないことをした」などと言われてきま した。漢字では「勿体(もったい)ない」と書きます。本来そのものが持っている値打ちが生かされず、無駄になることが惜しいという意味です。
昨年、ノーベル平和賞を受賞されたケニアの環境大臣マータイさんが来日された時、「節約・再利用・再使用・修理という4種の意味を日本では"もったいない"という一言(ひとこと)で表現している。すばらしい」と感じて、国連の委員会で演説しました。このことが契機になって、死語になっていた「もったいない」の言葉を再認識しようという評論がふえてきました。
私たち仏教徒は、この「もったいない」心をどう受け取ればよいのでしょう。親鸞聖人の教えに尋ねてみると、次のようなご縁でいただけるのではないかと思います。
その第1は、人のいのちを賜ったことです。何はさておき、三悪道(さんあくどう 地獄・餓鬼・畜生 じこく・がき・ちくしょう)をはなれて、人間に生まれてきたことは、何にもかえがたい有り難いことであります。もったいないことです。
その第2は、真宗念仏の教えに遇えたことです。この因縁は、いくたび生を重ねても容易にあえるものではないから、遠く前世からの宿縁(しゅくえん)を慶(よろこ)びなさい。お念仏の教えだけが、お浄土に通入(つにゅう)するみちですからと説かれています。もったいないことであります。
ひとくち法話No111 ―こころ1― より

第112話 ご恩
「ご恩」という言葉を聞いて、なにを思い浮かべるでしょうか。一般には「恩人」とか「恩師」というように、自分をはぐくみ育ててくださった人へのご恩のことと考えることが多いでしょう。仏教でも「四恩」として、父母の恩・衆生(しゅじょう)(多くの人々)の恩・国王(国を安らかに治める為政者)の恩・三宝(さんぼう)〔仏法僧(ぶっぽうそう)〕の恩が挙げられ、特に父母の恩に報いる孝行こそが第1であることが強調して説かれています。その意味でも、恩は恵みと同義語で、君臣・父子・夫婦・師弟の間の恩寵愛顧(おんちょうあいこ)と解釈されるものであります。確かに、自分一人の力で生まれ育った人はいませんし、今日の自分が多くの人のおかげであることを感謝し、特に親に対して孝養(こうよう)の思いを忘れないことは大切なことであります。ともすれば現在社会においては、このことがないがしろにされ、様々な悲惨な事件を引き起こしています。
しかし、真宗の教えおいての「ご恩」という場合は「仏恩(ぶっとん)」の他はありません。他の恩もすべて「仏恩(ぶっとん)」に包摂(ほうしょう)されてしまうものであります。では「仏恩」とは何であるのかというと、煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)である私たちを必ず救い導いて仏になさしめんとされる「お念仏」に他ありません。知恩報徳(ちおんほうとく)のお念仏、報謝の称名こそが真宗の宗旨であります。親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、仏恩の深きことをよくよく思いはかるべしとして、このご和讃を説いてくださったのであります。
如来大悲の恩徳は 身を粉にしても報ずべし
師主知識の恩徳も 骨を砕きても謝すべし 『正像末法和讃(しょうぞうまっぽうわさん)第58首』
ひとくち法話No112 ―こころ2― より

第113話 聞く
平生(へいぜい)私たちは「聞く」という言葉を、音楽を聞く、話を聞くなど、音や声を耳で感じとるという意味で使いますが、他に尋ねるとか、聞いた内容を理解してそれに応じるという意味でも使います。
真宗では、聞法(もんぼう)第一と言って仏法を聞くことが最も大切なことであります。仏法の根本は本願であります。本願はお名号(みょうごう)(南無阿弥陀仏)で、「必ず救いとるからこの阿弥陀仏に任せなさい。」との呼び声であり、またそれに対する私の「ありがとうございます、阿弥陀様にお任せします。」という返事の念仏でもあるのです。心からのお念仏ができるためには、先ず呼び声を聞きとどけることが前提となります。
幼子(おさなご)がデパートで迷子になって必死にお母さんを捜しているとき、お母さんも、迷っている幼子の名を必死に呼びつづけます。それを聞いた幼子は、思わず「お母ちゃん!」と返事をしてお母さんの胸に飛び込み、お母さんは「よかったね」と言って幼子をしっかりと抱きしめます。このとき幼子は、お母さんのぬくもりを全身に受けて、至極の安心(あんしん)と安らかさの中で全てをお母さんに任せた姿となるのです。
ここで、この例えの中の迷える幼子を「私」に置き換え、呼び続けるお母さんを「阿弥陀様」と読み替えてみると、私と阿弥陀様との関係にぴたりとあてはまり、私が、阿弥陀様を信じて疑うことなく、全てをお任せした姿が、すなわち不退(ふたい)の位(くらい)を得た姿なのであります。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、「きくといふは、本願をききて疑ふこころなきを聞(もん)といふなり。またきくといふは、信心をあらはす御のりなり。」『一念多念文意(いちねんたねんもんい)』とおおせられております。
ひとくち法話No113 ―こころ3― より

第114話 よろこび
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、「歓喜(かんぎ)というは、歓は身をよろこばしむるなり、喜はこころによろこばしむるなり、うべきことをえてんずと、かねてさきよりよろこぶこころなり」『一念多念文意(いちねんたねんもんい)』と説かれています。この文の意味は、信心が具(そな)わることの「よろこび」を示されたものです。阿弥陀さまの本願(ほんがん)は、私たちを必ず浄土に往生せしめられるのであり、涅槃(ねはん)(さとり)を得(え)さしめられると同時に、歓喜(よろこび)をも得さしめてくださるとされるのです。信心が具わることの「よろこび」とは、身にも心にも満ちあふれるものであり、ともに阿弥陀さまのご本願の賜(たまもの)であって、私たちのはからえるものではありません。
現実問題として、社会現象はさまざまに身も心も悩まし悲しませることばかりで、なかなか素直によろこべることはありません。しかしそれは私欲が満たされないことによる悩みであって、私たちに信心のよろこびが得られなくなってしまったわけではないのです。それは迷い苦しんでいるものこそ救わんとされるのが阿弥陀さまのご本願であるからです。私に迷い苦しみの煩悩(ぼんのう)のあることに目覚め、その私こそ願われていることに気づくことによって、私の往生がまちがいのないものとなり、それが信心であると聖人はお説きになっています。
私たちは、不可思議なはたらきのおかげによって、今日が在ると思うと、やはりこれが聖人のいわれるご本願だと思います。それが私の今の「よろこび」であります。
阿弥陀仏の御名をきき 歓喜賛仰せしむれば (あみだぶつのみなをきき かんぎさんこうせしむれば)
功徳の宝を具足して 一念大利無上なり (くどくのほうをぐそくして いちねんだいりむじょうなり)
『讃阿弥陀仏偈和讃第28首』
ひとくち法話No114 ―こころ4― より

第115話 おかげさま
終戦から60年経ちました。経済の急激な復興により、あり余る物資や食料を目の前にして、着るものは「着捨て」食べるものは「食べ捨て」というふうに捨てる事が平気になり、とうとう当たり前という思想が常識になってきました。
毎日の食事にしても、植物や動物のいのちのおかげで健康を保ち、自然(しぜん)現象とはいうけれど、太陽や空気、水の恩恵(おんけい)がなければ、1日として生きていく事は不可能であります。真宗教団連合の法語(ほうご)カレンダーに「当たり前と思っていたことが、有り難いと気づかされる(平成18年6月)」と掲載されていました。当たり前が当たり前でなくなる。有ることが難しいと気づくことの大切さを、今更(いまさら)ながら思うことであります。
「おかげさま」という言葉は「お陰さま」の意で、見えないところの力の恵みに対する謝念(しゃねん)のあらわれであります。私達はとかく、目先のことや目に見えるものにとらわれがちで、不平や不満に明け暮れ「おかげさま」という思いを失ってはいないでしょうか。
煩悩(ぼんのう)にまなこさえられて
摂取の光明(せっしゅのこうみょう)見ざれども
大悲(だいひ)ものうきことなくて
つねにわが身をてらすなり(高僧和讃 源信讃第8首)
ご存じ、親鸞聖人(しんらんしょうにん)のご和讃であります。煩悩にさえぎられて眼(まなこ)には見えないけれど、阿弥陀様のお救いの光りは休むことなく照らしてくださることに思いを致す時、必ず仏にならさせていただく身の幸せを喜び、世のため人のために報謝(ほうしゃ)の生活をさせていただきたいものです。
ひとくち法話No115 ―こころ5― より

第116話 ありがとう
「ありがとう」という言葉は、漢字で「有り難う」と書きます。「有ることが難い(かたい)」。めったにないことへの感謝の気持ちが現れた言葉です。この世で「有ることが難い」こととは何でしょうか。
『礼讃文(らいさんもん)』に
人身受け難し、今已に受く。仏法聞き難し、今已に聞く。(にんじんうけがたし、いますでにうく。ぶっぽうききがたし、いますでにきく。)
此身今生において度せずんば、更に何れの生においてか、此身を度せん。(このみこんじょうにおいてどせずんば、さらにいずれのしょうにおいてか、このみをどせん。)
大衆もろともに至心に三宝に帰依したてまつるべし。(だいしゅもろともにししんにさんぽうにきえしたてまつるべし。)
と説かれています。意味は、この世に人間として生(しょう)を受けること、この人生の中で仏法に出遇う(であう)ということ、このことこそが「有り難い」ことだというのです。そのことに気づかされた今、今生においてこの身が救われていかねば、いつの世に救われることがあろうかというのです。
尊い仏法のみ教えは、南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)となって私に呼びかけて下さっています。どうしようもない自己中心的な考えしか持ち合わせない私を救わずにはおかないという願いをかけておって下さいます。それが仏の本願であります。
「聞其名号 信心歓喜(もんごみょうごう しんじんかんぎ)」仏法を聞くご縁に遇えた(あえた)喜びは何にも勝るものであり、私の生きる意味をはっきり教えて下さるものであります。
このことを教え示して下さったお釈迦(しゃか)さまをはじめ、七高僧(しちこうそう)、親鸞聖人(しんらんしょうにん)、歴代ご法主(ほっしゅ)のご恩に感謝し報恩謝徳(ほうおんしゃとく)のお念佛を称えることが、私たち聞法者(もんぼうしゃ)の「ありがとう」の姿なのです。
ひとくち法話No116 ―こころ6― より

第117話 ひかり
和訳正信偈(わやくしょうしんげ)は「ひかりといのちきわみなき 阿弥陀(あみだ)ほとけを仰(あお)がなん」で始まります。これは、阿弥陀ほとけのおこころが、ひかりといのちだからです。
普通私たちは、ひかりというと、太陽のひかりを第一に挙げますが、ほとけのひかりは、ただ明るいというだけではありません。正信偈には、そのひかりの特徴を十二に分けて書かれています。それには量(はか)ることのできない、限りのない、遮(さ)えられない、比べるもののない、最上の、清らかな、喜びや智慧(ちえ)を与える、絶(た)えることのない、思い尽くすことができない、説き尽くせない、そして最後には日にも月にも超えたひかりですとのべられています。しかもこの阿弥陀ほとけにひかりに遇(あ)うと、久しく生死(しょうじ)の苦海(くかい)に没して出離(しゅつり)の縁がなかった煩悩具足(ぼんのうぐそく)の私たちがお浄土に往生(おうじょう)するという全く想像もできない不可思議(ふかしぎ)なひかりですと説かれています。このことを親鸞聖人(しんらんしょうにん)は和讃(わさん)で
煩悩(ぼんのう)にまなこさえられて
摂取(せっしゅ)の光明(こうみょう)みざれども
大悲(だいひ)ものうきことなくて
つねにわが身をてらすなり 『高僧和讃(こうそうわさん)源信讃(げんじんさん)第8首』
と詠(うた)われています。
だから、ひかりという表現は、単に明るさの代名詞ではなく、ほとけのおこころをのべられたものであり、この私たちをお浄土(じょうど)に往生(おうじょう)させるという、堅く力強いはたらきを持つ約束の言葉であります。
ひとくち法話No117 ―こころ7― より

第118話 あう
「あう」という言葉は、「遇う・会う・逢う・遭う・合う」などの多くの漢字が思いうかびます。人や事件に遭遇することや、動作を同時にすること、ときには結婚する意味までもが想定されるようです。
しかし、仏教で「あう」といえば、「あいがたきご縁に出遇(であ)う」ことです。真実の法との出遇いによって、人生が大きく転換し、真実の信心を得ることであります。また、法は人や書籍などを通しても知らしめられますが、私に真実の教えである法を伝えて下さった方を善知識(ぜんじしき)と申します。善知識に出遇って受け止めさせて頂いた信心は、また他の人にも伝えられていくことでしょう。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、法然上人(ほうねんしょうにん)との出遇いによって浄土のお念仏の真実信心を頂かれました。この信心は生涯揺(しょうらいゆ)るがぬものとなったのです。
その心を『高僧和讃(こうそうわさん)』の源空(げんくう)(法然)讃には
曠劫多少(こうごうたしょう)のあいだにも 出離(しゅつり)の強縁(ごうえん)しらざりき
本師源空(ほんじげんくう)いまさずは このたびむなしくすぎなまし
とされて、何度生まれかわっても出遇うことの難しい、迷いを抜け出す確かなご縁であるお念仏。もし法然上人に出遇わなかったら、今生(こんじょう)もむなしく過ぎ去ってしまっていたであろうと、阿弥陀さまのお念仏のご縁に出遇われた慶びを説いておられます。
また私たちも、この親鸞聖人から現代にまで連なるご法縁によって、お念仏のご縁に恵まれています。まさに750年の御遠忌(ごおんき)をむかえさせて頂くにあたり、わたしたちも、聞法(もんぼう)というご縁によって、真実信心に遇わせて頂きたいものであります。
ひとくち法話No118 ―こころ8― より

第119話 ほほえみ
わるさをした幼子(おさなご)が上目遣(うわめづか)いに母の顔を見つめ、母も無言で子の顔を見つめます。しばしの時が過ぎて、幼子がワッと泣き出し「ごめんなさい!」、母はニッコリほほえんで、子の手を優(やさ)しく握って頷(うなず)きます。母の限りない慈悲心(じひしん)が感じられる話であります。
観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)には「即便微笑(そくべんみしょう)」という言葉が出てきます。王子阿闍世(あじゃせ)が提婆達多(だいばだった)にそそのかされて、父の頻婆娑羅(びんばしゃら)王を殺し、母の韋提希(いだいけ)も宮殿(きゅうでん)の奥深く閉じ込めてしまいます。韋提希(いだいけ)は、苦悶(くもん)してブッダに「なぜ私は阿闍世(あじゃせ)のような子どもを生んでしまったのですか。なぜブッダは提婆達多(だいばだった)のような人と親戚なのですか。」と訴えます。しかしブッダは何もおっしゃらずただ金色(こんじき)の光の中に無量(むりょう)の諸仏(しょぶつ)の国土(こくど)をお示しになります。それを見た韋提希は、自分中心のあさましい我が身に気づいて、「浄土往生(じょうどおうじょう)の道を説いてください」と号泣(ごうきゅう)しながらブッダに懇願(こんがん)すると、ブッダは、浄土を願う心のおこった韋提希(いだいけ)にニッコリ微笑みかけながら、懇々(こんこん)とその道をお説きになりました。その時、韋提希(いだいけ)はさぞかしブッダのお顔に安心し、お話にこころから頷いたことでしょう。
わるさをしながらすなおに謝ることができない幼子(おさなご)や、自分の不幸をブッダに愚痴(ぐち)る韋提希(いだいけ)は、煩悩(ぼんのう)のままに生きていながらそのことにさえ気づかずにいる私自身の姿であります。お寺の本堂(ほんどう)やお仏壇(ぶつだん)には、なんとも言えない優(やさ)しさをたたえた阿弥陀(あみだ)さまのお姿があります。この阿弥陀(あみだ)さまは、自己を中心に生きる私たちにより添って「自分のはからいによらずこの阿弥陀仏(あみだぶつ)に任せなさい 南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)」と呼びかけて、その呼び声を聞き届ける私をずっと待っておられるのでしょう。
ひとくち法話No119 ―こころ9― より

第120話 道
「道(みち)」という語からは、「この道は、いつか来た道、ああそうだよ、お母さまと・・・」という歌と共に、子供の頃の懐(なつ)かしい情景(じょうけい)が想われることでしょう。
さて、仏教で「道」とは、仏道(ぶつどう)であり、仏となるための教え、悟(さと)りに至るべき道として説かれています。これは自己の心の奥底にある真実に目覚めることを説いています。そこには自力(じりき)と他力(たりき)〔念仏(ねんぶつ)〕の道があります。自力ではとうてい悟りに至れない、自力を捨てて他力に専修専念(せんじゅせんねん)すべきであるとされます。ご和讃(わさん)に
万行諸善(まんぎょうしょぜん)の小路(しょうろ)より 本願一実(ほんがんいちじつ)の大道(だいどう)に
帰入(きにゅう)しぬれば涅槃(ねはん)の さとりはすなわちひらくなり 『高僧和讃(こうそうわさん) 曇鸞(どんらん)讃33首』
と親鸞聖人(しんらんしょうにん)は説かれています。
このご和讃の意は、聖道自力(しょうどうじりき)の教えでは覚りに至ることのできないのを小路(しょうろ)といい、本願一実(ほんがんいちじつ)の大道(だいどう)であるお念仏によってのみ、すべての迷い苦しむ者が涅槃(ねはん)(悟りの世界、仏の世界)に至らしめられるのであるから大道といい、本願一実の念仏の大道と、阿弥陀仏によって私たちを浄土への道を歩ましめんがために、呼び求めくださっているのです。そして、この大道に帰入(きにゅう)するには、仏の願い(本願)に目覚めることが信心であって、そこには涅槃の覚りが開かれているのです。
念仏とはすべての者が必ずお浄土へ往き、大涅槃(だいねはん)(悟り)を得さしめられる大きな道なのです。その大道が、私たちに開かれているのですから、ご本願を信じお念仏を称(とな)えることが、無上涅槃(むじょうねはん)の悟りが得られるのです。
ひとくち法話No120 ―こころ10― より

第121話 合掌
「合わせた手と手の向こうには
光の園(その)が見えるでしょう
慈愛(じあい)に抱(いだ)かれ安らかに
ほほえむ私が見えるでしょう」
ご存じ「高田山讃歌(たかださんさんか)」の一節です。ほのぼのした気持ちが伝わってまいります。手と手を合わせることを、合掌(がっしょう)と申します。この合掌について、親鸞聖人(しんらんしょうにん)が七高僧(しちこうそう)の第一祖(だいいっそ)にあげられていますインドの龍樹菩薩(りゅうじゅぼさつ)は、この世の中で、一番美しい人間の姿とは何かというと、「合掌の姿」であると述べられています。
私達は、食事の時、仏壇の前、お墓や葬式の時等に合掌しますが、手を合わす行為や意味を考えてみましょう。
・手を合わせるのですから、相手に対し身も心も感謝や敬(うやま)いの心を表します。
・病気や怪我の治療を「手当て」と言います。手を当てるだけで、痛みが和らぐ気がします。手の平をピタッと合わせて合掌しますと、自然と心が穏やかになってきます。
・合掌すると喧嘩(けんか)になりません。争い、損得、憎しみの心も消えてしまうから不思議です。つまり、合掌すると自然と「仏の心」に近づいていくのではないでしょうか。
インドでは、右手は仏の手、左手は凡夫(ぼんぶ)(私達)の手と言われ、手を合わすことにより、仏さまと私が一つになる、つまり、仏凡一体(ぶつぼんいったい)となるのです。
「手を合わす心そのまま仏なり」であります。
今の世の中殺伐(さつばつ)とした様相を呈しています。この合掌の心でもって毎日の生活を送ったならば、どれだけ明るく住みよい社会になることでしょう。
ひとくち法話No121 ―こころ11より―

第122話 まなこ
私たちは、毎日の暮らしの中で、自分の眼(まなこ)に映るものを頼りにしています。仕事や家事、人間関係、その他諸々(もろもろ)のことを、自分の判断で、これが一番正しいのだと思う自己中心的な生活をしています。それが、ひとたび崩れてしまうと、あわてふためいてしまいます。たとえば、病気になったとき、自分の力でどうすることもできない不甲斐なさを思い知らされます。何事も頭を打たれないと気づかないのが私たちです。煩悩具足(ぼんのうぐそく)の私たちは、自分の損得をもとにして考え、本当の自分を忘れてしまっています。本当のことを本当のものとして見る眼(まなこ)を持っていないのです。本当のものとして見るには、心の眼(まなこ)が開かれなければいけません。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、
煩悩(ぼんのう)にまなこさえられて
摂取(せっしゅ)の光明(こうみょう)見ざれども
大悲(だいひ)ものうきことなくて
つねにわが身をてらすなり 『高僧和讃(こうそうわさん)源信讃(げんじんさん)第8首』
と和讃(わさん)に説かれています。
煩悩(ぼんのう)に眼(まなこ)がさえぎられている状態では阿弥陀仏の救いの光を見ることはできません。それにもかかわらず、如来の大慈大悲(だいじだいひ)はその私を救いとろうと照らし、私の眼(まなこ)を開いてくださるのです。そして、私のありのままの姿をありのまま示して下さるのです。なんとありがたいことでしょうか。仏の光明に包まれて、このことに気づかされるとき、自(おの)ずと南無阿弥陀仏の報恩感謝(ほうおんかんしゃ)の念仏を頂くことができるのです。
ひとくち法話No122 ―こころ12より―

ひとくち法話 123~137話 真宗のことば
第123話 聞其名号
この語は『大無量寿経(だいむりょうじゅきょう)』(下巻)に出ています。「その名号(みょうごう)を聞く」と読みます。「その名号」とは、「南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)」というご本尊のお名前です。このお名号には、どんな意味や働きや願いが誓われているのでしょう。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は『一念多念文意(いちねんたねんもんい)』という書物の中で、
「聞其名号(もんごみょうごう)」というのは、本願(ほんがん)の名号をきくとのたまえるなり。
きくというのは、本願をききて、疑うこころなきを「聞」というなり。
また、きくというのは、信心をあらわす御(み)のりなり。
と解説されています。
私たちにも名前があります。親がつけてくれました。自分たちの子どもとして"ようこそ、この世に生まれてきてくれました。ありがとう"というよろこびと、わが子の生涯への期待を名前の中に封じ込めて、名付けてくださったにちがいありません。一度、自分の名前が、どのような理由でつけてくださったのであるか。意味はどうかなどを親にお尋ねしておきましょう。
幼児の頃、家に帰ってまっさきにいうことばは「お母さんただいま」でした。待ってましたとばかり、家の中からお母さんの「おかえり」の声が聞こえてきます。その声でいっぺんに安心したものでした。「きくというのは、信心をあらわす御のりなり」は、このお母さんの一声のように、私たちに往生まちがいなしという大安堵をさせていただくほとけのお声であります。
ひとくち法話No123 ―真宗のことば1― より

第124話 現生正定聚
「現生正定聚(げんしょうしょうじょうじゅ)」とは、死後に浄土に往生してからではなく、現生(この世で生きているあいだ)に正定聚(しょうじょうじゅ)(成仏することの決定した集まり)の数に入るということであります。煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)が、現生において信心を得た時に往生と成仏が決定(けつじょう)するということで、親鸞聖人(しんらんしょうにん)によって開顕(かいけん)された真宗の教えの特質であります。
この「正定聚」という語は『無量寿経(むりょうじゅきょう)』の中で、極楽浄土(ごくらくじょうど)に往生したものは必ず無上涅槃(むじょうねはん)を証(しょう)して成仏(じょうぶつ)するということであります。しかし聖人は、死んで浄土に往生してからではなく、現生において信(しん)を得た時に正定聚の数に入り、次に必ず成仏される弥勒菩薩(みろくぼさつ)と同じ不退転(ふたいてん)(迷いに戻ることがない)の位(くらい)に定まるとされ、等正覚(とうしょうがく)とも如来に等しいとも説き示されるのであります。
また聖人の教えでは、第十八願〔念仏往生(ねんぶつおうじょう)の願〕による真実信心(しんじつしんじん)を得たものが正定聚であり、自力のはからいを捨て去ったものの往生で、真実報土(しんじつほうど)(阿弥陀仏の本願が成就した真実の浄土)の往生とされるのであります。
『正信偈(しょうしんげ)』には、「憶念弥陀仏本願(おくねんみだぶつほんがん) 自然即時入必定(じねんそくじにゅうひつじょう)」
(弥陀仏の本願を憶念すれば、自然に即のとき必定に入る)
と示され、阿弥陀仏の本願を信じ念仏を称える、その時に仏の働きによって、必ず浄土に往生し成仏することが定まる「必定(ひつじょう)の菩薩(ぼさつ)」の中に入ると説かれています。
また、『浄土高僧和讃(じょうどこうそうわさん)』龍樹讃(りゅうじゅさん)には、
不退(ふたい)のくらいすみやかに 得んとおもわん人はみな
恭敬(くぎょう)の心に執持(しゅうじ)して 弥陀(みだ)の名号称(みょうごうしょう)すべし
と詠(うた)われています。
死後に浄土に生まれてからの悟りではなく、今すでに仏に願われ、仏になるべき身として生かされていることに目覚め気づき、お念仏の日暮らしをさせていただくことのありがたさを示されたものであります。
ひとくち法話No124 ―真宗のことば2― より

第125話 煩悩成就
釈迦(しゃか)の教法(きょうほう)おほけれど 天親菩薩(てんじんぼさつ)はねむごろに
煩悩成就(ぼんのうじょうじゅ)のわれらには 弥陀(みだ)の弘誓(ぐぜい)をすすめしむ 『高僧和讃(こうそうわさん)〔天親菩薩(てんじんぼさつ)第1首〕』
聖人(しょうにん)は天親菩薩(てんじんぼさつ)のご和讃の中で、釈迦の教法は多いけれど、煩悩成就(ぼんのうじょうじゅ)のわれらには阿弥陀如来の本願(ほんがん)(一切の衆生を救おうという誓い)を、お勧めになっておられます。
煩悩とは悪い心の働き、心身を悩まし、煩(わずら)わすものですが、中でも特に「三毒(さんどく)の煩悩(ぼんのう)」と言って、「貪欲(とんよく)」「瞋恚(しんに)」「愚痴(ぐち)」があります。第一に「貪欲」とは、自分の欲するものを貪(むさぼ)り、自分の情にかなうものを受け入れて、あきることを知らない、非常に欲の深いことです。第二に「瞋恚」とは、怒り憎むことです。第三に「愚痴」とは、愚かなこと。特に真理(しんり)に対する無知で、一切の道理に通じる智慧に欠け、それが誤った行いの原因となって迷うことです。これら三つの煩悩が完全にそなわっていることを煩悩成就といいます。どうにもならなく心を悩んでいる私たちをごらんになって、如来さまはこのような私たちを救わなければならないと願をたてられました。その本願のお心に気づかなければ私たちは救われません。その信心をいただくには、み仏を思い、聖人が和讃されましたように「弥陀大悲(みだだいひ)の誓願(せいがん)を 深く信ぜん人はみな ねてもさめてもへだてなく 南無(なも)阿弥陀仏ととなうべし」と、絶えず心にお念仏を申すことを忘れてはなりません。お念仏こそ私たちの生きる 命であります。
ひとくち法話No125 ―真宗のことば3― より

第126話 現世利益
現世(げんぜ)とはこの世のこと。利益は一般には「りえき」と読みますが、仏教では「りやく」と言い、現世に息災(そくさい)、延命(えんめい)などの利益を得ることと辞典にあります。そのため願いごとや欲望を叶(かな)えるため、神や仏に願ったり祈ったりしていないでしょうか。ご開山の高僧和讃につぎのような1首が述べられています。
仏号(ぶつごう)むねと修(しゅ)すれども 現世(げんぜ)をいのる行者(ぎょうじゃ)をば
これも雑修(ざっしゅ)となづけてぞ 千中無一(せんじゅうむいつ)ときらはるる 『善導(ぜんどう)讃第6首』
南無阿弥陀仏ともっぱら称えていても、家内安全、商売繁盛、息災延命(そくさいえんめい)など現世利益を得ようと祈る人は、千人に一人も浄土に往生していないと嫌われている。と厳しく戒めておられます。しかし現実は、日の良し悪し、占い、呪(まじな)い、祈願祈祷(きがんきとう)等に走っている人があるのではないでしょうか。
これに対して真宗の教えでは、右で述べたような現世の利益を祈ることは致しません。専修念仏(せんじゅねんぶつ)の行者には、念仏の徳として、親鸞聖人(しんらんしょうにん)ははっきり『現世利益和讃(げんぜりやくわさん)』(15首)にお示しくださっています。そのご和讃の中に
南無阿弥陀仏をとなふれば この世の利益きはもなし
流転輪廻(るてんりんね)のつみきえて 定業中夭(じょうごうちゅうよう)のぞこりぬ (第4首)
如来の本願を信ずる念仏者は、この世で受ける利益は際限もありません。六道輪廻(ろくどうりんね)といって、迷いの世界を巡らねばならぬ罪も消え、この世で受けるべきかぎりある寿命も中折れすることはありません。と聖人はおっしゃってみえます。
また、親鸞聖人のライフワークともいえる『教行証文類(きょうぎょうしょうもんるい)』には信心を得た人は、現生に十種の利益を得ると宣言されており、第十の「入正定聚(にゅうしょうじょうじゅ)の益(やく)」を総益(そうやく)として「ただしく成仏することの定まった仲間に入る」と述べられ、まさに念仏者は「この世の利益きわもなし」と言えるのであります。
ひとくち法話No126 ―真宗のことば4― より

第127話 無慚無愧
「無慚無愧(むざんむぎ)」とは、自己に対して恥じることなく、他に恥じることを知らないことをあらわす言葉です。『涅槃経(ねはんぎょう)』に、「慚愧(ざんぎ)なきものは名づけて人と為(な)さず、名づけて畜生(ちくしょう)と為す」と示されています。表向きは人の姿・形をしていても、自他に恥じることを知らない人は畜生と同じであるということです。心が欲望に支配され、「欲しい、欲しい」の姿がむき出しになったとき、人は自他に恥じることを忘れ、畜生や餓鬼(がき)と同等の存在になってしまうと言うのです。このことは、私たちが自分を振り返ったとき深くうなづかされるところです。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は『正像末法和讃(しょうぞうまっぽうわさん)愚禿悲嘆述懐(ぐとくひたんじゅっかい)』第4首に
無慚無愧(むざんむぎ)のこの身にて まことのこころはなけれども
弥陀(みだ)の回向(えこう)の御名(みな)なれば 功徳は十方にみちたまふ
と示されています。
聖人が八十六才のころの和讃ですが、自身を無慚無愧の身と述べておられます。恥じることを忘れたどうしようもないこの身に阿弥陀仏が差し伸べてくださった念仏こそが、無慚無愧の身であると気付かせてくださる。それが弥陀の回向であると述べられているのです。
無慚無愧の私が、お念仏をいただく身にさせていただくことのありがたさに思いを致しながら、日暮しをさせていただきたいものです。
ひとくち法話No127 ―真宗のことば5― より

第128話 信心獲得
どんな宗教でも、信心(信仰心)は、ご利益(りやく)に関係するので、最も大事な課題です。これに次のようなものがあります。
その一は、俗信(ぞくしん)です。自分の欲望が叶(かな)いますようにと、祈願(きがん)する信心です。一般的にいえば、大抵の宗教はこのためにあるようです。願いが叶えば、祈願する対象はなんでもよいのです。神・仏から天神地祇(てんじんじぎ)、魔王(まおう)、鬼神(きじん)、偉人(いじん)、きつね、いわしの頭(あたま)まであるといわれています。祈願する内容は、病気平癒(びょうきへいゆ)、交通安全、合格祈願、商売繁盛、無病息災(むびょうそくさい)などが代表的でしょうか。その願いが叶わないと、まだ信心が足らないのだと自分を責(せ)めて、どこまでも祈り続けていこうとする信心です。だからこれは信心獲得とは無縁の宗教です。
その二は、仏教の信心です。これには、(1)、(2)の二種があります。
(1)は、自力(じりき)の信心です。自分の帰依(きえ)する経典(きょうてん)の教えに従って修行し、心を磨(みが)いて、この世で転迷開悟(てんめいかいご)していく仏道(ぶつどう)です。
(2)は、他力(たりき)の信心です。(1)のように、自分の力ではほとけに成(な)れない凡夫(ぼんぶ)に対して、阿弥陀仏(あみだぶつ)が、すでに浄土往生(じょうどおうじょう)の道筋を成就(じょうじゅ)して下さってあるという仏道です。その道筋とは、親鸞聖人(しんらんしょうにん)が私たちに「弥陀(みだ)の本願(ほんがん)を信じ、念仏申せばほとけになる」と説かれました。
不退(ふたい)の位(くらい)(他力信心)すみやかに
得(え)ん(獲得)とおもわん人はみな
恭敬(くぎょう)の心(しん)に執持(しゅうじ)して〔ほとけの誓(ちかい)にうなずいて〕
弥陀(みだ)の名号称(みょうごうしょう)すべし〔南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)と称(とな)えましょう〕
ひとくち法話No128 ―真宗のことば6― より

第129話 往還廻向
阿弥陀(あみだ)さまのお働きを大きく二つに分けて往相(おうそう)と還相(げんそう)の二種廻向(にしゅえこう)と申します。これは親鸞聖人(しんらんしょうにん)によって開顕(かいけん)された真宗の教えの特質であります。
往相というのは、迷いの世界から悟りの浄土に生まれて往くすがたということで、還相というのは、浄土に往生し迷い苦しむ衆生(しゅじょう)を救い導くために、浄土からこの迷い苦しみの世界に還りきたるすがたということであります。阿弥陀さまが、永い修行によって成就(じょうじゅ)された本願功徳(ほんがんくどく)の全てを南無阿弥陀仏のお名号として私たち衆生に与えてくださっている他力廻向ということであります。
親鸞聖人は『正信偈(しょうしんげ)』の中に「往還廻向由他力(おうげんえこうゆたりき)」〔往還(おうげん)の廻向(えこう)は本願(ほんがん)に由(よ)る〕と示され、煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)である私が浄土に往生して大きな悟りを得させていただくのも、煩悩(ぼんのう)の娑婆世界(しゃばせかい)に還(かえ)りきたるのも、阿弥陀さまの他力本願の働きであって、そこに私のはからいが微塵(みじん)もまじることがないと説かれています。
これらのことから考えますと、親鸞聖人は私たちをお念仏の道に導くために、お浄土から還帰された還相の菩薩であるといただくこともできます。
また、ご和讃(わさん)には、
弥陀(みだ)の廻向成就(えこうじょうじゅ)して 往相還相(おうそうげんそう)ふたつなり
これらの廻向(えこう)によりてこそ 心行(しんぎょう)ともにえしむなれ
(阿弥陀仏が私共に恵まれる働きはすっかり完成していて、浄土へ向かわしめる働きと、再びこの世へ帰らしめる働きと二つである。これらの本願のお恵みによってこそ、信心も念仏も得させて下さるのである。)浄土高僧和讃〔曇鸞(どんらん)讃第14首〕
と示されています。
ひとくち法話No129 ―真宗のことば7― より

第130話 摂取不捨
摂取不捨(せっしゅふしゃ)とは何を摂取して捨てないのでしょうか。
十方微塵世界(じっぽうみじんせかい)の 念仏(ねんぶつ)の衆生(しゅじょう)をみそなわし
摂取(せっしゅ)して捨(す)てざれば 阿弥陀(あみだ)と名づけたてまつる (弥陀経意 第1首)
この和讃(わさん)は、あらゆる世界にたくさんの念仏者がいますが、この教えを信じて念仏する人をごらんになって、光明(こうみょう)の中にとり込んで、決してお捨てにならずに、お浄土に往生成仏(おうじょうじょうぶつ)させてくださる如来さまを阿弥陀仏とお呼びしましょうという意味です。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、「摂取して捨てざれば」の左横に、《ひとたび取りて永く捨てず、ものの逃ぐるを追わえとるなり。摂はおさめとる、取は迎えとる》と意味を詳しく書いておられます。
讃岐(さぬき)の庄松(しょうま)さんという妙好人(みょうこうにん)は、「摂取不捨とはどういう意味か」と問いかけたお坊さんに、両手を広げて掴み掛かりました。びっくりしたお坊さんは逃げ出しましたが、とうとう追いつめられて捕まってしまいました。庄松さんは「摂取不捨とはこれだ」と言ったそうです。
煩悩に眼をさえぎられている私たち衆生には、仏さまから逃げているという感じはよくわかりませんが、阿弥陀仏からみれば背き逃げているありさまがあわれなのです。私たち衆生を、逃げるから追わないのではなく、逃げるから追っかけて、ついに抱きしめられるのです。
煩悩(ぼんのう)に眼障(まなこさ)えられて 摂取(せっしゅ)の光明(こうみょう)みざれども
大悲(だいひ)ものうきことなくて 常(つね)に我(わ)が身(み)を照(て)らすなり (高僧和讃 源信讃 第8首)
ひとくち法話No130 ―真宗のことば8― より

第131話 往生安楽国
お勤(つと)めの最後に称(とな)えるので、どなたもご存じの言葉です。
願以此功徳(がんにしくどく) 平等施一切(びょうどうせいっさい)
同発菩提心(どうほつぼだいしん) 往生安楽国(おうじょうあんらくこく)
という回向文(えこうもん)の一節であります。回向文(えこうもん)とか回向偈(えこうげ)と申しておりますが回向(えこう)とは、自分が積んだ善徳を他人に振り向け仏果(ぶっか)を得ようという解釈もありますが、真宗では全く反対で、阿弥陀さまが私共にお慈悲(じひ)を手回し下さることを回向と申します。そういう観点に立って、往生安楽国をいただいてまいりましょう。
この一節は、中国の善導大師(ぜんどうだいし)が著(あらわ)された『観経四帖疏(かんぎょうしじょうしょ)』というお書物の中の『勧衆偈(かんしゅうげ)』の一番最後に述べられている言葉であります。
意味は、「安楽国(あんらくこく)に往生する」です。安楽国とはお浄土のことで、そこに往生させてもらう、ということであります。平素何気なく称えていますが、大変なことなんです。自分が菩提心(ぼだいしん)(仏になりたい心)を発(ほっ)してお浄土に生まれるのではありません。前文にありますように、阿弥陀如来の功徳(くどく)によって、平等に一切に回向されていますから、如来のお働きによって、お浄土に生まれて仏にさせてもらうと頂きたいものであります。
また、往生という言葉は、一般に困った時に「おうじょうした」とよく言いますが、間違って使われていることを認識したいものであります。
ひとくち法話No131 ―真宗のことば9― より

第132話 三悪道
三悪道(さんなくどう)とは、自らのなした悪行(あくぎょう)の結果として、死後にたどる苦しい迷いの世界のことで、地獄(じごく)・餓鬼(がき)・畜生(ちくしょう)の三つの世界をいいます。この迷いの世界の様子は、七高僧(しちこうそう)のお一人である源信大師(げんじんだいし)の『往生要集(おうじょうようしゅう)』に詳しく説かれています。まず地獄では悪業(あくごう)を積んだ者が落ち、種々の責め苦を受ける地下世界として無間地獄(むけんじごく)までの様子が述べられています。また餓鬼道(がきどう)は生前に嫉妬深かったり、物惜しみやむさぼる行為をした人間が死後赴(おもむ)く場所で、飲食物が与えられず飢えと渇きに苦しむ世界として語られています。盆踊りや送り火でご存知のお盆は、目蓮尊者(もくれんそんじゃ)(お釈迦さまの弟子)が、餓鬼道に落ちたお母さんを救う為に、施餓鬼(せがき)を行ったことが始まりとなっています。畜生道(ちくしょうどう)は、人間に殺害され、お互いに殺傷しあう苦しみに満ちた動物の世界とされています。
また、源信大師が書かれた『横川法語(よかわほうご)』によりますと、「まず、三悪道をはなれて人間に生まるること、おおきなるよろこびなり。身はいやしくとも畜生におとらんや。家はまずしくとも餓鬼にまさるべし。心におもうことかなわずとも地獄の苦にくらぶべからず。このゆえに人間に生まれたことをよろこぶべし」と説かれています。
では、私たちの日常生活はどうでしょうか。地獄・餓鬼・畜生の三悪道は、決して他人ごととして説かれたものではありません。むさぼり、いかり、愚痴(ぐち)の三毒(さんどく)の煩悩(ぼんのう)に満ちた、この私たちの生き方を述べられたものであります。それなのに大師が「三悪道をはなれて人間に生まれたることをよろこぶべし」と申されていることに、私たちは深いよろこびを感ぜずにはおれません。それはお念仏を申せる命だからであります。
ひとくち法話No132 ―真宗のことば10― より

第133話 聖浄二門
仏教には成仏(じょうぶつ)する道に二種あると説かれています。一つは、自分の力を頼んで、厳しい修業を行い、さとりを開いていく道です。これは聖者(しょうじゃ)の道なので聖道門(しょうどうもん)といいます。もう一つは、自分の努力ではさとりが開けない者が、阿弥陀(あみだ)ほとけの本願力(ほんがんりき)に助けられて、浄土(じょうど)に往生していく道で浄土門(じょうどもん)といいます。この両門あわせて「聖浄二門(しょうじょうにもん)」といいます。
この聖浄二門を教えて下さったのは、七高僧(しちこうそう)の第四祖である中国の道綽禅師(どうしゃくぜんじ)です。四十八歳のある時、石壁(せきへき)の玄忠寺(げんちゅうじ)に参詣されました。そこに第三祖の曇鸞大師(どんらんだいし)の徳を讃えた碑文(ひぶん)が立っていて、大師が深く阿弥陀ほとけに帰依(きえ)されたことが記されていました。これを読んだ道綽禅師は大変な感動を覚えて、「大師のような知徳のすぐれたお方でさえ、浄土門に入られたのだ。自分のような魯鈍(ろどん)なものが、どうして自力修行の聖道門にとどまることができようか」と翻意(ほんい)されて、浄土の教えに帰依されたのでありました。
それから禅師は、自分が念仏を申すだけでなく、広く民衆にも他力浄土門をすすめられたので、都では念仏の声が天地にあふれる盛況であったと伝えています。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、和讃で道綽禅師をたたえて
本師道綽禅師(ほんじどうしゃくぜんじ)は 聖道万行(しょうどうまんぎょう)さしおきて
唯有浄土一門(ゆいうじょうどいちもん)を 通入(つにゅう)すべきみちととく 『高僧和讃 道綽讃第1首』
とのべられています。
ひとくち法話No133 ―真宗のことば11― より

第134話 他力本願
「他力」という言葉は、世間では、他人の力に頼って生きていこうとする消極的な意味で使われていますが、信仰問題で使われると、一筋縄ではいかない複雑な意味が加味されてきて、正しく理解することがむつかしいのです。
それは「転迷開悟(てんめいかいご)」(迷いを転じて、悟りを開く)という仏道に関係してくるからです。
まず自力道(じりきどう)とは、自分の努力修行を通して精神統一を行い、心の中の迷い心を断ち切って、清浄(しょうじょう)な仏心(ぶっしん)に変えていくという悟りへの道程(どうてい)をいいます。
次に他力道とは、自力道に徹底してみたが、なお悟りへの境地にいたることのできない人々が、遂に阿弥陀ほとけの"煩悩を断(た)たなくてもよい"という教えに助けられて成仏していく道をいうのです。だからここでいわれる「他力」とは、単なる他人の力に助けられるという安易なものではなく「仏力」(ほとけの力)をいうのであります。
親鸞聖人は
「他力」というは、如来の本願力なり 『教行証文類(きょうぎょうしょうもんるい)』
と、簡潔に申されました。
「本願力」とは、阿弥陀ほとけが私たち凡夫(ぼんぶ)に「南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)」というわが名を称うるものは、必ず浄土に往生させると約束された誓願です。この働きを「他力本願」というのです。だから、この文言(もんごん)は、私たちの 真宗の教えの大事な要(かなめ)の言葉です。正しく領解(りょうげ)して使いましょう。
ひとくち法話No134 ―真宗のことば12― より

第135話 二種深信
これは真宗の教えの要(かなめ)である信心について、中国の善導大師(ぜんどうだいし)が二種深信(にしゅじんしん)〔機(き)の深信(じんしん)と法(ほう)の深信(じんしん)〕として、私の阿弥陀如来の真実のすがたとして明確に説き示されたものであります。大師の著書の言葉を引用します。
一には決定(けつじょう)して深く、自身は現にこれ罪悪生死(ざいあくしょうじ)の凡夫(ぼんぶ)、曠却(こうごう)よりこのかた常に没(もっ)し常に流転(るてん)して、出離(しゅつり)の縁あることなしと信ず。〔機の深信〕
二には決定して深く、かの阿弥陀仏の四十八願(がん)は衆生(しゅじょう)を摂受(しょうじゅ)いたまふこと、疑なく慮(おもんぱか)りなくかの願力に乗じてさだめて往生を得(う)と信ず。〔法の深信〕 『観経疏(かんぎょうしょ)』
<大意>
一つには、私という人間は本当に罪深く、迷い続けるものであり、到底自力の修行によって悟りを開くことの出来ない身であると深く信じる。
二つには、お救いいただく阿弥陀仏の本願に疑いや分別を捨てておまかせし、迷い苦しむ私を必ず救い導いて浄土に往生させてくださることを深く信じる。
この心が一つとなって、目覚め気づかせていただくのが真実信心の獲得(ぎゃくとく)であり、往生の決定であると親鸞聖人も説き示しておられます。
煩悩具足(ぼんのうぐそく)と信知して 本願力(ほんがんりき)に乗(じょう)ずれば
すなはち穢身(えしん)すてはてて 法性常楽證(ほっしょうじょうらくしょう)せしむ
『浄土高僧和讃』(善導讃第12首)
<意味>
自己があらゆる欲望を悉くそなえた凡夫であると深く感じ知って、弥陀の本願のお力にお任せすると、即座にこのけがれた肉体を捨てきって、涅槃(ねはん)のさとりに至らしめられる。
ひとくち法話No135 ―真宗のことば13― より

第136話 自然法爾
親鸞聖人(しんらんしょうにん)の晩年、86歳の御書(ごしょ)に、
自然(じねん)というは、自(じ)はおのずからという、行者(ぎょうじゃ)のはからいにあらず、
しからしむという言葉なり。然(ねん)というは、しからしむという言葉、
行者のはからいにあらず、如来(にょらい)の誓(ちか)いにてあるがゆえに。
と言われ、さらに『高僧和讃(こうそうわさん)〔善導讃(ぜんどうさん)〕』には
自然はすなわち報土(ほうど)なり
と説かれました。現在私たちは、「自然」という言葉を「しぜん」と読むことが多いですが、仏教では「じねん」と読みます。聖人は、他力すなわち本願力を、自然と申されています。
「法爾(ほうに)の道理(どうり)」という語があります。炎は空にのぼり、水はくだり流がると説かれています。これを仏教では法爾の道理と言います。
人間はこの世に生まれた以上は、必ず死ぬ。法が天然自然の道理にかなっていることを法爾の道理というのです。阿弥陀仏(あみだぶつ)は、名号(みょうごう)をもって我々を救おうと誓われました。私たちが、お念仏によって往生成仏(おうじょうじょうぶつ)の定まるのも、阿弥陀仏の法爾の道理であるからです。
念仏を称える人が悟りを得られるのではなく、自然すなわち他力(仏の願力)という、人知を越えた働きを知らしめられるのです。聖人は、このように法爾の道理を自然の働きとして、法身(ほっしん)が報身(ほうじん)として現われられたのが阿弥陀仏で、「弥陀仏は自然のようを知らせん料(りょう)(手だて)」として示して下さっています。
念仏によって往生成仏が定まることは、仏の願力自然であります。あるがままの相でありますから、自然の道理です。心から阿弥陀仏のご本願を信じ、念仏を称えて、目覚めさせていただきたいものです。
ひとくち法話No136 ―真宗のことば14― より

第137話 専修念仏
高田本山(たかだほんざん)専修寺は"せんしゅうじ"ではなく、正しくは"せんじゅじ"と読みます。親鸞聖人(しんらんしょうにん)は54歳(1226年)の時、下野国高田(しもつけのくにたかだ)(現在の栃木県真岡市高田)にお寺を建立されて、専修念仏(せんじゅねんぶつ)の根本道場とされました。このため後に、専修寺と名づけられました。
専修念仏とは、専(もっぱ)ら念仏ひとすじを行じ、それ以外のさまざまな行をまじえないという意味です。
法然上人(ほうねんしょうにん)は、仏教の目ざす救済の原理を行のあり方に求め、実践を優先する宗教を目ざされました。一切経(いっさいきょう)を何度も読破されたなかで、上人は善導大師(ぜんどうだいし)の「観経疏(かんぎょうしょ)」の次の文に出遇われて、阿弥陀仏の浄土に往生するのにふさわしい行は、専修念仏〔称名正行(しょうみょうしょうぎょう)〕であると説かれました。
一心専念弥陀名號 行住坐臥不問時節久近念念不捨者
是名正定之業順彼佛願故
一心(いっしん)に阿弥陀仏(あみだぶつ)に名号(みょうごう)をとなえ、行動しているときも、坐(すわ)っているときも、臥(ふ)しているときも、時間の長短を問わず念仏することをつづけると、まさしく往生することが定まる。なぜなら、それは仏の本願にもとづくからである。(現代語訳)
親鸞聖人も和讃(わさん)などで、専修念仏の教えこそが、迷いの世界からさとりの境地へと導かれていくことであると説いておられます。
ひとくち法話No137 ―真宗のことば15― より

ひとくち法話 138~141話 迷信
第138話 迷信を考える
「いわしの頭も信心から」という諺(ことわざ)があります。節分の夜に、いわしの頭を柊の枝にさして、門前に置くと、悪鬼(あっき)が退散するという風習があったことから、言われた諺です。鰯の頭のようにつまらぬものでも、信仰する人には、霊験(れいけん)を感ずるようになるというのです。これは、自分の心が迷っていることに気づかぬのが原因です。最近では、テレビで某女が「遺影は、家にかざるべからず」とか「墓石に家紋を掘ると、家運が傾く」とか言ったので、多くの人から真実はどうかという相談がありました。こちらに確かな判断力がないと、このようなくだらない話にも迷ってしまうものです。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、当時の人々が、多くの迷信にしばられて生活しているのをなげかれて、1首の和讃で、それをズバリと切って捨てられました。
かなしきかなや道俗(どうぞく)の 良時吉日(りょうじきちにち)えらばしめ
天神地祇(てんじんじぎ)をあがめつつ 卜占祭祀(ぼくぜいさいし)をつとめとす
『愚禿悲歎述懐和讃(ぐとくひたんじっかいわさん)第8首』
という和讃です。
聖人が亡くなってからすでに750年が経ちますが、これらの迷信は、科学の時代といわれる今日でも根強く、生活の中に残っています。私たち真宗の念仏者は、自らの生活を振り返って、このような迷信にこだわらない人生道を歩みたいものです。
次号から三回に分けて、実例を挙げて、具体的に説明します。
ひとくち法話No138 ―迷信1― より

第139話 良時吉日えらばしめ
この見出しの言葉は、親鸞聖人(しんらんしょうにん)が晩年厳しく自己告白されました『愚禿悲歎述懐和讃(ぐとくひたんじっかいわさん)』の1首に依るものです。
悲しきかなや道俗(どうぞく)の 良時吉日(りょうじきちにち)えらばしめ
天神地祇(てんじんじぎ)をあがめつつ 卜占祭祀(ぼくぜいさいし)をつとめとす (第8首)
ほんとうに悲しいことだ。僧侶(そうりょ)も俗人(ぞくじん)も良時吉日を選んでいる。良時吉日に支配されているではないか。という聖人の悲痛な受け止めの言葉です。
私達は毎日が好日でありたいと願っています。もちろん雨や嵐の日もありますが、これは自然現象なので致し方ありません。
ここで言う良時吉日とは、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口という六曜思想(ろくようしそう)にもとづくものです。多くの人々が日のよしあしにこだわって生きていることに対する、聖人のお歎きであります。
六曜思想は元来中国の陰陽道(おんみょうどう)からきたもので、戦いや賭博などで吉凶を占った俗信であります。大安は良い日だから結婚式や退院に選んだり、友引は友を引くから葬儀を避ける、仏滅も嫌われているという現実がありはしないか。友引は「共引き」引き分けるということであったのを後で「友引」に替えたということで、単なる語呂合わせに過ぎません。
仏法とは関係のない日のよしあしを言い合っているのは、悲しいことです。このご和讃は700年も前のことですが、現代でも変わりがないのは誠になげかわしいかぎりです。
私共は、迷信・俗信に振り回されることがないよう自他共に心掛けましょう。
ひとくち法話No139 ―迷信2― より

第140話 天神地祇をあがめつつ
聖人の『愚禿悲歎述懐和讃(ぐとくひたんじっかいわさん)』の中の「天神地祇(てんじんじぎ)をあがめつつ」という句について考えてみました。
天神地祇とは、天の神と地の神をあわせて、あらゆる神々のことを言います。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)の時代にも、仏教を信じながら病気の時は神を頼りに命乞(いのちご)いの祈祷(きとう)をしてもらったり、干ばつの時は雨乞いをしたり、種々の祈祷が行なわれておりました。
今の時代も、神社への初詣(はつもうで)や、合格祈願(ごうかくきがん)、交通安全の祈願、厄年の厄除け、家を建てる時の地鎮祭(じちんさい)など、天地の神々をあがめて、その霊験(れいげん)を頼りにする場合が数多くあります。
よく考えてみますと、自分の欲望を満たすためであったり、不幸からのがれたいという自分勝手な都合から神々を頼ることが多いのではないでしょうか。このような人々の心理は、800年前も現在も変わりはありません。
かなしきかなやこのごろの 和国(わこく)の道俗(どうぞく)みなともに
仏教(ぶっきょう)の威儀(いぎ)をこととして 天地(てんち)の鬼神(きじん)を尊敬(そんきょう)す
『愚禿悲歎述懐和讃(ぐとくひたんじっかいわさん)第11首』
親鸞聖人は、仏教徒でありながらこのような行いをして心の安堵(あんど)を求めようとする人々をこの上なく悲しまれて、もっと内面的な真実の教えを信じて生きてほしいと望まれました。天神地祇に頼らず、お念仏を通じて真実の自分に目覚める生き方を忘れずに毎日を過ごしたいものです。
ひとくち法話No140 ―迷信3― より

第141話 卜占祭祀をつとめとす
今回は、
かなしきかなや道俗(どうぞく)の 良時吉日(りょうじつきちにち)えらばしめ
天神地祇(てんじんじぎ)をあがめつつ 卜占祭祀(ぼくぜいさいし)をつとめとす
『愚禿悲歎述懐和讃(ぐとくひたんじっかいわさん)第8首』
親鸞聖人は、この「卜占祭祀」の左訓(さくん)に「うらない・はらひ・まつり」とされています。卜は筮竹(ぜいちく)などでうらなうこと。占とは、家相や人相をうらなうことで、ものの吉凶(きっきょう)をうらなうことを卜占といいます。祭も祀もまつりということで、天神を祀り地祇を祭って福をもとめ災いを除こうとすることです。聖人の頃、社寺の僧や神官がこのような除災求福(じょさいぐふく)の祓(はら)いを専(もっぱ)らの勤めとして、人々の本当の悟りや救いをおざなりにしていたことへの嘆きのお言葉であります。
しかし、これは昔の問題ではなくて、現代においても嘆かわしい現実であります。テレビや週刊誌・新聞に至るまで、今日の運勢とか何々占いとかをもてはやし、結婚や引っ越しまでもを占いに頼る人も多いようです。
何か目に見えない力によって自分が支えられ護られていると考えることは大切なのですが、自己責任から逃避して、全てを運命のように考えることは大きな間違いです。
今の自分に賜(たまわ)っている命の大切さ有り難さに目覚め気づいて、今の私を精一杯に生きる他に近道も逃げ道もありません。そこにはすでに阿弥陀さまの願いが私を護って下さっているのです。お念仏の日暮しに心を定めることが真実の幸せであると聖人は示されています。
弥陀大悲(みだだいひ)の誓願(せいがん)を ふかく信ぜんひとはみな
ねてもさめてもへだてなく 南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)をとなふべし
『正像末法和讃(しょうぞうまっぽうわさん)第53首』
ひとくち法話No141 ―迷信4― より

ひとくち法話 142~147話 感動
第142話 往生
「往生(おうじょう)」とは、阿弥陀(あみだ)様の本願力(ほんがんりき)に乗(じょう)じて、凡夫(ぼんぶ)である私が極楽浄土(ごくらくじょうど)に生まれて往(ゆ)くことであります。昔からお説教などで「死ぬと思うな生まれると思え」と説かれてきました。お浄土に生まれるというのは、阿弥陀様と同じ大きな悟(さと)りを得て仏となることです。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、阿弥陀様の誓(ちか)われた念仏往生(ねんぶつおうじょう)の願(がん)(第十八願)によって往生することを真宗(しんしゅう)とされています。それも、死んだ後に往生が決まるのではなく、煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫が阿弥陀様のご本願に目覚め気づかせていただいた時に、即ち真実信心(しんじつしんじん)をいただいた時、煩悩のままの私の往生成仏(おうじょうじょうぶつ)が決定(けつじょう)すると説かれています。それを「不退(ふたい)の位(くらい)」とも「等正覚(とうしょうがく)」とも説かれて、弥勒菩薩(みろくぼさつ)が必ず成仏するのが定まっているのと同じく、この世において必ず成仏することが決定すると説かれています。これを「現生入正定聚(げんしょうにゅうしょうじょうじゅ)」(この世で正しく成仏の定まった集まりに入る)として、親鸞聖人の教えの要となっています。
ただ一般には「往生」を困って動きのとれないこととして使われています。これは「平家(へいけ)物語」や歌舞伎で有名な弁慶(べんけい)の最後の場面で、弁慶が全身に矢を受けて、眼を見開いて立ったまま往生し、敵がその姿に一歩も動くことが出来なかったことから来ています。往生が死んで浄土に生まれることから、弁慶の死を意味するのですが、動きがとれないとか、困惑(こんわく)するというのは派生(はせい)的な意味で、「往生」の正しい意味ではありません。
この煩悩のままの私が、浄土に生まれて仏となるというのは、これにまさる大きな感動はありません。
念仏往生の願により 等正覚にいたる人
すなわち弥勒(みろく)におなじくて 大般涅槃(だいはつねはん)をさとるべし
『正像末法和讃(しょうぞうまっぽうわさん)第26首』
ひとくち法話No142 ―感動1― より

第143話 回心
回心(えしん)とは、これまでの生き方、生きるよりどころをガラッと転換(てんかん)することです。
ご自分のことについてはあまり語られなかった親鸞聖人(しんらんしょうにん)が『顕浄土真実教行証文類(けんじょうどしんじつきょうぎょうしょうもんるい)』の後序(ごじょ)で、
「然(しか)るに愚禿釈(ぐとくしゃく)の鸞(らん)、建仁辛酉(けんにんかのとり)の暦(れき)、雑行(ぞうぎょう)を棄てて、本願(ほんがん)に帰(き)す」と告白されています。
「雑行を棄てて、本願に帰す」とは、「あれやこれやと自己(じこ)のはからいによる修行(しゅぎょう)を棄(す)てさって、弥陀(みだ)の本願(ほんがん)に帰命(きみょう)する」という意味です。
9歳で得度(とくど)をされた親鸞聖人は、20年の間、比叡山(ひえいざん)で日々厳しい修業を行われました。しかし煩悩(ぼんのう)を棄てて悟りを開くという自力(じりき)修行では聖人はさとることができず、悩まれた聖人は、聖徳太子(しょうとくたいし)ゆかりの六角堂(ろっかくどう)に100日の参籠(さんろう)をされます。その95日目の明け方に、夢の中に救世観音(くぜかんのん)の声を聞かれたのです。その声にみちびかれて聖人は、京の町で念仏の教えを説いておられる法然上人(ほうねんしょうにん)を訪ねられました。それからまた100日の間、雨の日も風の日もどんなことが起ころうとも欠かすことなく、上人の教えを聞かれました。そして、阿弥陀如来(あみだにょらい)の本願によって、煩悩を断たずに往生(おうじょう)を得(う)ることのできる他力(たりき)の教えにみちびかれたのです。
このことはいままでの、自力の修行によって煩悩を断ち切って、悟りの境地(きょうち)にいたる仏道(ぶつどう)から、ひたすら弥陀の本願を信じ、お念仏を申すという他力の仏道への大転換(だいてんかん)がなされたということです。これを回心(えしん)といいます。
この他力の仏道こそ、真宗念仏(しんしゅうねんぶつ)の教えであります。
ひとくち法話No143 ―感動2― より

第144話 「お迎え」ってあるの?
仏教には、「来迎(らいこう)」という言葉があります。
来迎とは、自分の力を頼みとし、自分のはからいによって往生(おうじょう)しようと念仏に励(はげ)む人にとって、その人の命がまさに終わろうとするとき〔臨終(りんじゅう)〕に、阿弥陀(あみだ)様が極楽浄土(ごくらくじょうど)へ連れて行ってくださるというもので、よくいう「お迎え」であります。
このお迎えを頼む人は、臨終(りんじゅう)のときまで往生が定まらないため、それまでは不安と苦悩の日々が続くのです。そのため、古(いにしえ)には臨終を迎えると枕元に阿弥陀様を安置して、その手から五色(ごしき)の糸を引き、その端を自分が握って、確かに浄土へ連れて行ってもらおうとする儀式さえ行われていました。
ところが、親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、阿弥陀経の中にあるおことばを、「お念仏をよろこぶ人は、其(そ)の人の命が終ろうとする時まで、阿弥陀様が諸々(もろもろ)の仏様とともにその人をお護(まも)りくださる。」と読み解(と)かれ、さらに「真実信心を得た人は、阿弥陀様のはたらきにより、その信心が定まるときに必ず浄土に往生する身となる。よって臨終を待つこともなければ来迎を頼むこともない。」と仰せられました。
つまり、お念仏をよろこぶ人は、そのご信心をいただいたときに必ず浄土に往生させていただく身となり、命が終る時まで、つねに阿弥陀様の大悲(だいひ)のはたらきに護られているので、すでにお迎えがあるとか無いとかの問題を離れているのであると親鸞聖人はお示しいただきました。
ひとくち法話No144 ―感動3― より

第145話 成仏〔念仏成仏これ真宗〕
一般には、人が亡くなることを成仏(じょうぶつ)したといいますが、この成仏を他人のことと捉えている限り、感動とは無縁の成仏であります。いまここで、成仏を感動のできごとと受けとるには、"この私が"確かにほとけになると実感することが必要です。
その求道(ぐどう)のみちを親鸞聖人(しんらんしょうにん)にたずねてみることにしましょう。聖人は、この"ほとけになる(成仏する)こと"を目標にして、比叡山(ひえいざん)で20年という長い間『法華経(ほけきょう)』の教えに従って自力修行に励まれました。しかし修行すればするほど「凡夫(ぼんぶ)というは、無明煩悩(むみょうぼんのう)われらが身にみちみちて、欲もおおく、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおおくひまなくして、臨終(りんじゅう)の一念(いちねん)にいたるまで、とどまらず、きえず、たえず」という煩悩具足(ぼんのうぐそく)のわが身を知らされるばかりでありました。
そこで聖人は、山を降りて六角堂(ろっかくどう)に籠(こも)り、遂に聖徳太子の夢告(むこく)をうけて、法然上人(ほうねんしょうにん)に出遇われ、『浄土三部経(じょうどさんぶきょう)』の阿弥陀如来の誓願(せいがん)に帰依(きえ)されたのでありました。これが真宗他力の教えであり、教えの要(かなめ)は
「本願を信じ 念仏申さば 成仏する」
というのであります。
聖人は、このご縁を「いし、瓦、つぶての如(ごと)きわれらが、こがねにかえなさしめられる」ような教えですと喜ばれました。どんなに努力、修行しても、自力では絶対に成仏できない"この私"が、他力念仏の因縁(いんねん)を獲(う)れば、成仏するというのであります。「仏法不思議(ぶっぽうふしぎ)ということは、弥陀の弘誓(ぐぜい)になづけたり」と。なんという不思議なことでありましょう。ただ感動して慶喜(きょうき)するほかありません。
ひとくち法話No145 ―感動4― より

第146話 出遇いのよろこび
人生を振り返ってみますと、オギャーと生まれたとき、最初に出会うのは、十月十日(とつきとうか)お腹で育てて下さった母であります。まだ目の見えない私にお乳を含ませ、それからずっと成長を見守ってもらったのです。成長と共に、周囲の方々との出合い、恩師や友達との心の出遇いもあり、私共は支えられ合って生きることによって、自分が完成されてくるのです。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)のご生涯の中で感動という言葉が浮かぶ場面は、法然上人(ほうねんしょうにん)との出遇いによって阿弥陀さまのお誓いに目覚められたことです。
29歳まで比叡山(ひえいざん)で厳しい修業をされていた親鸞聖人は、ご自身の心の迷いを解決することができず山を降りられ、吉水(よしみず)の法然上人(ほうねんしょうにん)のもとに通い仏法(ぶっぽう)を聴聞(ちょうもん)して、あらゆる衆生(しゅじょう)を救うことができなければ仏にならぬと誓われた阿弥陀さまのご本願に目覚められました。法然上人との出遇いがなければ、決して生死(しょうじ)の迷いの世界から救われることはなかったでしょう。そのときの感動を『教行証(きょうぎょうしょう)』のなかで、「遇(あ)い難(がた)くして今遇(いまあ)うことを得(え)たり」(ご縁がなければお念仏のみ教えと決して出遇うことはありませんでした)と述べられております。
親鸞聖人の感動は、さかのぼれば、お釈迦(しゃか)さまのお説法(せっぽう)に始まり、七高僧(しちこうそう)の方々によって受け継がれ、法然上人から親鸞聖人のもとへ届けられたものです。さらに平成の今日にいたっても、正しく親鸞聖人のみ教えをそのままにお伝えしておりますのが高田の法灯(ほうとう)でございます。そのみ教えを今、この世に生を受けて出遇わせていただけることを深く受けとめて、常に感謝の心をもって、お念仏の日暮(ひぐ)らしをさせてもらいたいものです。阿弥陀さまのみ教えによって目覚め、お念仏のお育てにあずからせていただくことこそが、正に感動の人生であります。
ひとくち法話No146 ―感動5― より

第147話 踊躍歓喜
先日、あるお寺の掲示板(けいじばん)に、「死は必然(ひつぜん)であり、生は驚愕(きょうがく)である。」と書かれていました。生まれた者が死ななければならないことは必然でありましょう。では何故「生は驚愕である」のでしょうか。これは「人身(にんじん)うけがたし、今すでにうく」という教えからも分かりますように、私が無数の生き物の中から人としての生をうけ生きているということは、大変稀有(たいへんけう)なことであって、驚くべき事実であり、大変に有り難い感謝すべきことであるということでしょう。
さらに、この「生」をこの世に生をうけ生きているというだけでなく、浄土に生まれて仏になるという意味で味わってみますと、これは信心を得て往生成仏(おうじょうじょうぶつ)の決定(けつじょう)することでありますから、単なる驚きではなく、天にも地にも跳び上がってしまうほどの喜びであるとして「踊躍歓喜(ゆやくかんぎ)」とお経に説かれています。
仏教では、この真実信心(しんじつしんじん)に目覚め気付かせていただいた境地(きょうち)を「歓喜地(かんぎじ)」と申します。また本山では、8月の盂蘭盆会(うらぼんえ)のことを「歓喜会(かんぎえ)」と言い習わしています。これらは共に、阿弥陀如来の本願力や光明に触れて真実信心に目覚め気付かせていただき、仏になるべき身として今を生かせていただいていることを現(あらわ)しています。これに勝る喜びがないことを「踊躍歓喜」と示しているのであります。
また、お釈迦さまの十大弟子のお一人である目蓮尊者(もくれんそんじゃ)は天眼通(てんげんつう)という神通力を得た時、亡くなった母を見ると、餓鬼道(がきどう)でもがき苦しむ姿しか見えないことに悩み、お釈迦様に相談したところ、多くの弟子の世話をすることを教えられ、熱心に母の供養の為に弟子達の世話をして母の救われる姿を見る事が出来たそうです。その時に、多くの弟子達が目蓮尊者の母が救われたことを喜び踊ったことが盆踊りの起源(きげん)であるとされています。
尽十方(じんじっぽう)の無碍光(むげこう)は 無明(むみょう)のやみをてらしつつ
一念歓喜(いちねんかんぎ)する人を かならず滅度(めつど)にいたらしむ
ひとくち法話No147 ―感動6― より

ひとくち法話 148~152話 おまいりの心
第148話 お荘厳
お荘厳(しょうごん)とは、お仏壇(ぶつだん)を心を込めて美しくお飾りすることで、きれいにお掃除してお灯明(とうみょう)を点け、美しい花を献(ささ)げてお香をたきます。
お仏壇は、私たちが見ることの出来ない真実の世界、私たちのはからいを超えた阿弥陀様やお浄土の姿を形に表したもので、お灯明は、闇の世界をさまよう私の心を照らして、真実に目覚めさせてくださる阿弥陀様の智慧の光であり、花は、お浄土に美しく咲き誇る花で、私に注がれる阿弥陀様の限りない慈悲のおこころを表しております。また、線香やお香は、お浄土に薫る清々しい香りであり、その芳しい香りに私のこころは浄化され、お浄土へと導かれるのであります。
このような意味から、お荘厳にはせめて燭台(しょくだい)には蝋燭(ろうそく)を用い、花は造花ではなく、お香はなるべく上質のものを使いたいものです。
また、お仏壇をお荘厳することは、お浄土の建立(こんりゅう)であると言われ、私の手でお浄土のたたずまいを現させていただき、そのお浄土を私が拝見し拝ませていただくのであります。
美しくお荘厳された仏前に家族そろって南無阿弥陀佛(なもあみだぶつ)とお念仏申すとき、一家共々阿弥陀様の光明(ひかり)に照らされて、深い慈悲のおこころに触れて煩悩(ぼんのう)に満ちた我が姿に気付かせていただき、救いようのないこの身を、必ずお浄土に迎え取ろうと私に掛けられた阿弥陀様の限りない願いに遇わせていただくのであります。
また、すでに佛(ほとけ)となられた大勢のご先祖も、阿弥陀様とともに、そんな私を幾重にも取り囲んで喜び護ってくださるのであります。
南無阿弥陀佛をとなふれば 十方無量の諸仏は (なもあみだぶつをとなふれば じっぽうむりょうのしょぶつは)
百重千重囲繞して よろこびまもりたまふなり (ひゃくじゅうせんじゅういにょうして よろこびまもりたまふなり)
『現世利益和讃(げんぜりやくわさん) 第15首』
ひとくち法話No148 ―おまいりの心1― より

第149話 お参りのこころ
お墓やお寺にお参りする時のこころを問われたことがありました。私たちは、お参りする時には口で「南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)」と申すのが普通です。これを称名念仏(しょうみょうねんぶつ)といいます。親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、ご和讃(わさん)で、
南無阿弥陀仏をとなうれば この世の利益きわもなし (なもあみだぶつをとなうれば このよのりやくきわもなし)
流転輪廻の罪きえて 定業中夭のぞこりぬ (るてんりんねのつみきえて じょうごうちゅうようのぞこりぬ)
『浄土和讃(じょうどわさん)』〔現世利益和讃(げんぜりやくわさん)〕
とうたわれました。私は、問われた方にこの和讃を紹介して、真宗(念仏者)のお参りする時のこころを考えてみました。
称名念仏(しょうみょうねんぶつ)には、不思議な大きなお働きがあるのですね。南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)と称えていると、この世における最高のよろこびがえられます。その最(さい)たるものは、生来(せいらい)持ってきた煩悩(ぼんのう)がわざわいして、今までどれほど生まれかわり死にかわりして迷いの世界を経巡(へめぐ)ってきたことか。その私がこの娑婆(しゃば)のまよいの縁が尽きて、お浄土に生まれる(ほとけになる)身にさせていただくという。しかも、いつ、どんなことで生命(いのち)が終わっても、称名念仏(しょうみょうねんぶつ)のご利益で、浄土往生(じょうどおうじょう)はまちがいありませんと、この和讃(わさん)は約束しておられるのであります。
したがって、一般的に世間でいわれている、その時々の自分の願いごとをこころに入れて、その願いがかないますようにとお祈りするのは、真宗の教えではありません。私たちは、ご利益(りやく)のある声明念仏(しょうみょうねんぶつ)を必ず申して、ただ、"ありがとうございます"のこころでお参りするばかりであります。
ひとくち法話No149 ―おまいりの心2― より

第150話 わたしの称えるお念仏、みなご恩報謝
煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)であるわたしは、あらゆる自己中心的な欲望に塗(まみ)れて生きています。しかし、その煩悩だらけのわたしを、そのままに浄土に摂取(せっしゅ)してさとりを得さしめようと照らし護って下さっているのが阿弥陀様です。
高田中興(たかだちゅうこう)の真慧上人(しんねしょうにん)の御書に、親鸞聖人のお言葉を引かれて、次のように示しておられます。
「無碍光仏(むげこうぶつ)(阿弥陀仏)の心光(しんこう)つねにてらしまもりたもうゆえに、
無明(むみょう)のやみはれ、生死(しょうじ)のながき夜すでにあかつきになりぬ」とあそばされ候(そうろう)。
信心だにも得(う)れば、あかつきになりぬと、みえて候。
この上は、報恩謝徳(ほうおんしゃとく)の称名(しょうみょう)、いよいよはげみたもうべく候。
親鸞聖人は、印度(いんど)・中国・日本の高僧の教えを開顕(かいけん)されて、この煩悩具足の凡夫のわたしが成仏するのは、死んで浄土に生まれてからではなく阿弥陀様の御本願に目覚め気付かせていただいて(信心を得る)お念仏を申す身となった時、往生成仏が定まると説かれました。これが「無明(むみょう)のやみはれ、生死(しょうじ)のながき夜すでにあかつきになりぬ」ということです。
ですから、わたしの称えるお念仏は、浄土に往生するために称えるものではなく、往生の定まった身であることを深くよろこび、賜った命のご恩を感謝するものであるということです。
如来大悲の恩徳は 身を粉にしても報ずべし (にょらいだいひのおんどくは みをこにしてもほうずべし)
師主知識の恩徳も 骨を砕きても謝すべし (ししゅちしきのおんどくも ほねをくだきてもしゃすべし)
『正像末法和讃(しょうぞうまっぽうわさん)第58首』
ひとくち法話No150 ―おまいりの心3― より

第151話 拝んでいるものに拝まれている
日曜学校の歌の中に「ほとけの子ども」という歌があります。
「われらはほとけの子どもなり うれしいときもかなしいときも みおやのそでにすがりなん われらはほとけの子どもなり おさないときも老いたるときも みおやにかわらずつかえなん」
幼い子どもが声をあわせてうたう姿をみていると、ほのぼのとした気持ちになり、この歌から大事なことを教えられているような気がします。
「み親(おや)」とは、阿弥陀仏(あみだぶつ)のことです。わたしが生老病死(しょうろうびょうし)の苦しみ、喜怒哀楽(きどあいらく)の心を抱いて生きている中で、阿弥陀仏は、常にわたしに寄り添って下さっています。わたしはそのことに気が付かないのです。そのようなわたしをあわれんで、お名号(みょうごう)(南無阿弥陀仏)を与えて下さり、何ごとも疑うことなく、自力のはからいを捨てて、お念仏を申しなさいとおっしゃられるのです。わたしは、仏様の心を信じてお念仏を申すのみです。
わたしが南無阿弥陀仏を申すよりも前に、阿弥陀仏の方からわたしは拝まれているのです。なんという有り難いことでしょうか。親が子を思うように、仏様はいつもわたしを思っていて下さっているのです。そのことに気付かされて、初めて「われらはほとけの子どもなり」というこの歌の深いあじわいが身にしみてまいります。
報恩感謝の心でお念仏を申す生活を送っていきたいものです。
ひとくち法話No151 ―おまいりの心4― より

第152話 後世をいのる
「山を出(い)でて、六角堂(ろっかくどう)に百日こもらせ給(たま)いて、後世(ごせ)(いのちを終えたのちのこと)を祈らせ給いけるに」と親鸞聖人(しんらんしょうにん)がご往生を遂げられたのち、内室(ないしつ)(奥方)の恵信尼公(えしんにこう)は末娘に宛てたお手紙で当時のことを振り返っておられます。
聖人が29歳の時、修業しておられた比叡(ひえい)の「山」から毎晩下山し京都の街中にある六角堂へ参籠(さんろう)されたことがございました。人生を終えてのちのことがどのようになるかはっきりと知りたいという、心の底からの不安を問うために聖徳太子(しょうとくたいし)の化身である救世観音(くぜかんのん)に託されたのでした。
そうしたところ、95日目の早朝、夢のなかで救世観音がお出ましになり、仏法を求める新たな道筋をお示し下さったのです。
そのご縁に導かれて法然上人(ほうねんしょうにん)を訪ねられ、阿弥陀様(あみださま)のご本願のいわれをお聞きしたところ、救われる道筋はお念仏のみであると知らされました。「生死(しょうじ)出(い)づべきみち(まよいの人生をこえる教え)」がここにあったとよろこばれました。
聖人の見られた夢のお告げは、幻想的に思えるかも知れません。しかしながら、後世をいのる気持ちは昔も今も切実な願いであることに変わりはございません。この世とのご縁が尽きることはとても心細く思えますが、お浄土へ参らせていただくご縁に出遇える阿弥陀様の前で、ただお念仏を申させていただくばかりでございます。
弥陀の本願信ずべし 本願信ずる人はみな (みだのほんがんしんずべし ほんがんしんずるひとはみな)
摂取不捨の利益にて 無上覚をばさとるなり (せっしゅふしゃのりやくにて むじょうかくをばさとるなり)
『正像末法和讃(しょうぞうまっぽうわさん) 夢告讃(むこくさん)』
ひとくち法話No152 ―おまいりの心5― より

ひとくち法話 153~174話 聖人のおことば
第153話 愚禿が心は、内は愚にして外は賢なり
表題のおことばは、親鸞聖人(しんらんしょうにん)がその著書『愚禿鈔(ぐとくしょう)』の上下それぞれの冒頭で述べておられるもので、愚禿(ぐとく)とは、聖人ご自称のお名前であります。
平生(へいぜい)私たちは、名号(みょうごう)〔南無阿弥陀佛(なもあみだぶつ)〕のいわれを聞かせていただきますが、「聞く」ということは、名号のいわれを聞いて疑う心のないことをいい、それがすなわち信心であると聖人はお示しになっています。
ところが、私たちはなかなか「聞く」ことができません。それは、自分の知識や体験から得た力に執着しているからです。ときとして自分の愚かな執着心を垣間見ることはあっても、あえて眼(まなこ)を閉じて自分の本当の姿を認めようとしないのであります。口では「私は愚者(おろかもの)です。」と言いながら、心の中では「自分のほうが賢い。」と思っていて、「内は愚(ぐ)」であることに気付いていないのであります。
自分を真摯(しんし)に省(かえり)みて、貪りや怒りの心に満ち、名誉や地位に執着している自分の内なる愚かさを自覚したとき、名号のいわれを自然に聞き届けることができるのであります。
聖人は、「内は愚にして外は賢なり。」と厳しく自己の姿を見つめて、愚かさ非力さを自覚され、自分のこころの様を「恥ずべし痛むべし」と告白し慚愧(ざんぎ)されているのです。そのおこころが、『正像末法和讃(しょうぞうまっぽうわさん)〔愚禿悲歎述懐(ぐとくひたんじゅっかい)〕』にも次のように詠(よ)まれています。
(ご和讃)
外儀(げぎ)のすがたはひとごとに
賢善精進(げんぜんしょうじん)現ぜしむ
貧瞋邪偽(とんじんじゃぎ)おおきゆえ
奸詐(かんさ)ももはしみにみてり
(意訳)
人は誰でも 外向きの姿は
賢こぶり善人ぶって精進らしく見せているが
内心は貪り・怒り・偽りに満ちていて
人を欺(あざ)きだましてばかりいる
ひとくち法話No153 ―聖人のおことば1― より

第154話 凡夫はすなわちわれらなり
これは、親鸞聖人(しんらんしょうにん)著の『一念多念証文(いちねんたねんしょうもん)』の中に書かれている言葉です。いいかえれば、「凡夫は、私のことです」とのべられているところです。では、「凡夫」とは、どういう意味でしょう。私たちは、”普通一般の人々”というくらいの感覚で使っていますが、聖人はちがいました。「凡夫は、私のことです」といって、自分自身のこころを、しかもほとけさまの光に照らし出された正真正銘(しょうしんしょうめい)のこころを、包みかくさず、あるがままにお示しくださって、次のようにのべられました。
「凡夫」というは、無明煩悩(むみょうぼんのう)われらが身にみちみちて、欲もおおく、
いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおおくひまなくして、臨終(りんじゅう)の一念(いちねん)にいたるまで、
とどまらず、きえず、たえずと、水火二河(すいかにが)のたとえにあらわれたり。
私たち真宗念佛者は、仏縁に遇(あ)うたびに「煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫」、「罪悪生死(ざいあくしょうじ)の凡夫」などと教えられて育ってきました。それなのに、人ごとのように聞いて、これが自分のこころの本性であることに気付かず、うぬぼれいっぱいのこころで生きてきました。
聖人は、阿弥陀仏の願いが、このような私をお目当てにして、浄土へ迎えようと約束されていることを説き明かされ、自らも安心して、自分のこころのすべてを仏前に告白されたのが『愚禿悲歎述懐和讃(ぐとくひたんじゅっかいわさん)』です。私たちは、この聖人のおこころを深く味わうべきであります。
(和讃)
蛇蝎奸妰(じゃかつかんさ)のこころにて
自力の修善はかなうまじ
如来の廻向(えこう)をたのまでは
無慚無愧(むざんむぎ)にてはてぞせむ
(意訳)
へび・さそりのような雑毒心(ぞうどくしん)で
修業しても無駄なこと
ほとけのみなをきくほかに
お浄土行(じょうどゆき)の道はない
ひとくち法話No154 ―聖人のおことば2― より

第155話 生死の苦海ほとりなし
生死の苦海ほとりなし ひさしくしずめるわれらをば
弥陀の悲願のふねのみぞ のせてかならずわたしける
『浄土高僧和讃 龍樹菩薩(じょうどこうそうわさん りゅうじゅぼさつ) 第七首』
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、人生を「生死の苦海」と言われます。苦しみや悩みが絶えない海であり、「難度海(なんどかい)」とも言われます。その苦海に「ひさしくしずめる」私たちは、目の前に浮かぶお金や財産、また家庭、会社、地位、健康、愛情といった丸太や板切れを次から次へ見つけ出しそれにすがって浮き沈みしているのでしょう。
しかし、すがってしばらくの間は安心できても、やがて新たな波が来れば投げ出され、海中でもがき苦しむことになります。そして、より大きな丸太や板切れを求めてすがりつくことになります。この繰り返しが人生の姿なのです。この生死の苦海に沈んでいる私達を救って下さるものは、その様な私達を救わずにはおれないという阿弥陀如来の願いだけです。阿弥陀如来は、われを信じ、わが名を称えるものをかならず往生させると誓われ、その誓いを成就(じょうじゅ)されました。
この阿弥陀如来のはたらきという舟に身をまかせていくことしか苦海をわたることができません。煩悩にまみれ、いかなる行(ぎょう)も修(しゅう)しがたい私達は、ただ一心に仏のお誓いを信じて生きていくことが生死出(しょうじい)ずべき道なのであります。
人間はどうして苦しむのか、原因をつきとめれば、こうでなければならないという我執(がしゅう)があるからで、そのことに目覚め、苦悩を乗り越える力を与えられるのが真宗の救いなのです。
ひとくち法話No155 ―聖人のおことば3― より

第156話 雑行を棄てて 本願に帰す
これは、親鸞聖人(しんらんしょうにん)の主著(しゅちょ)である『教行証文類(きょうぎょうしょうもんるい)』の終わりの部分に述べられている言葉です。
「雑行(ぞうぎょう)」とは、阿弥陀仏の浄土に生まれたいと願いながら、阿弥陀仏以外の諸仏を礼拝したり、その名を唱え、讃歎(さんだん)するなど、自分のはからいにより、いろいろ修業することです。
聖人も比叡山で20年間苦しい修業を重ねられました。その結果得られたものは、煩悩(ぼんのう)にさいなまれ、さとることのできない凡夫(ぼんぶ)のわが身の発見でありました。そして、これまでの修業が、雑行にほかならなかったという認識でありました。
そこで、聖人は、末法濁世(まっぽうじょくせ)に生きる凡夫にとって救われる道は「本願に帰す」ことだとさとられました。「本願に帰す」とは、弥陀のすべての人々を救おうとする願いを信じるということであります。弥陀の願いを信じて、ただ念仏することによって、浄土への道が開かれてくるというのであります。
そういうことで、「自分のはからいによるいろいろな修業をさしおいて、凡夫を救わずにはおけないという弥陀の願いを信じる身となります」と告白されたのでありました。
弥陀の本願信ずべし 本願信ずる人はみな(みだのほんがんしんずべし ほんがんしんずるひとはみな)
摂取不捨の利益にて 無上覚をばさとるなり(せっしゅふしゃのりやくにて むじょうかくをばさとるなり)
『正像末法和讃(しょうぞうまっぽうわさん)』
ひとくち法話No156 ―聖人のおことば4― より

第157話 本願力にあいぬればむなしくすぐる人ぞなき
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は天親菩薩(てんじんぼさつ)のご和讃の中で
本願力にあいぬれば むなしすぐる人ぞなき
功徳(くどく)の宝海(ほうかい)みちみちて 煩悩(ぼんのう)の濁水(じょくしい)へだてなし
と讃えられておられます。
おおよその意味は、阿弥陀さまのご本願に遇われた人は、むなしい時間を過ごすことはありません。なぜならば、お念仏を称(とな)える人には、阿弥陀さまのおはたらきが満ちているからという内容です。
本願力に遇うということは、私が遇おうと思わなかったのに、阿弥陀さまの方から出遇って下さったということです。私は思いもかけず遇えたと思っていますが、決してそうではなく、阿弥陀さまはなんとかしてつかまえようと思いつめて下さっているのです。しかも、私が生まれるはるか昔からなんとかして救おうとはたらき続けて下さっておられるのです。
これについて念仏者、浅原才市(あさはらさいち)さんは「私は、どう考えてみても自分に腑(ふ)に落ちないことが一つだけある。何が腑に落ちないかと言うと、お念仏に出遇ったということだ」と喜んで言われるのです。
そして、本願力に遇えたことの不思議さを生き生きとした感覚で語っておられます。「私はお念仏に当ててもらった」「本願力に出遇ったら、もう私には思い残すことは何もない。阿弥陀さまのお慈悲の中に生かされているのだから。どんな人生でもお念仏で完結です。この人生は本当にありがたい人生であった。仏さまの永遠の命の中に生かされた一生であった。」と語っておられます。
ひとくち法話No157 ―聖人のおことば5― より

第158話 モノノニクルヲオワエトルナリ
聖人は、『浄土和讃(じょうどわさん)〔弥陀経意(みだきょうい)〕』の最初に
十方微塵世界(じっぽうみじんせかい)の 念佛の衆生(しゅじょう)をみそなわし
摂取(せっしゅ)して捨てざれば 阿弥陀となづけたてまつる
と詠まれて、お念佛もうす人をおさめとって捨てない摂取不捨(せっしゅふしゃ)という阿弥陀様の具体的なはたらきを讃歎(さんだん)されました。聖人はさらに、この和讃の中の「摂取(せっしゅ)」の左側に、「オサメトル ヒトタヒトリテナカクステヌナリ セフハモノノニクルヲオワエトルナリ・・・」〔おさめとる ひと度とりて長く捨てぬなり 摂(せふ)はものの逃ぐるを追わえ取るなり・・・〕と小さく記(しる)され(左訓)、「摂取」の意味を明らかにお示しくださいました。
阿弥陀様の摂取不捨のはたらきは、お念佛を悦ぶ人をひとたび救いとられたら決してお捨てになることがないばかりか、真実に背を向けて苦海(くかい)をさまよい、なお自分に執着して仏縁から遠ざかる者をこそ追わえ取って救わずにはいられないとはたらき続けていてくださるのです。それは、あたかも母の手を振りほどいて、あらぬ方向に走り出す我が子を懸命に追わえて引き留め、しっかりと抱き取る母の如くであります。そして、その母こそまさしく阿弥陀様であり、その子こそ紛れもない私そのものであります。
標題の「モノノニクルヲオワエトルナリ」とのお言葉は、阿弥陀様があらゆる世界の念佛もうす人々をご覧になるとき、その人々は勿論、お念佛を疑い仏縁から逃げる者も当然ご覧になられて、その者をも追わえ取り、ひとり残らずおさめとって捨てないという摂取不捨の大いなるはたらきをお教えくださったものであります。
ひとくち法話No158 ―聖人のおことば6― より

第159話 まづ善信(親鸞)が身には 臨終の善悪をば申さず
臨終(りんじゅう)とは、いままさに、いのち終ろうとする時です。死に際を「臨終」といいます。この臨終の善・悪とは、どんなことをいうのでしょう。
普通世間で話し合っている善い臨終とは「苦しまずに息絶える」ことでしょう。悪い臨終とは、「思わぬ事故や、難病に罹(かか)り長期に亘(わた)っての苦しみの末に亡くなる」ことをいうのでしょう。これらは、いずれも他人さまの臨終の様子を聞いて、善い往生やった。気の毒な往生やったなどと話題にする時の言い方であります。
しかし聖人のおっしゃられる「臨終の善悪をば申さず」は、教えの内容が違うのです。真宗では、本願を信じ念仏申す一念で、必ず浄土に往生することが定まるのだから、「臨終待つことなし、来迎(らいごう)たのむことなし。信心定まるとき、往生また定まるなり」と教えて下さっています。すなわち、真宗念仏者の往生は、臨終を待っての往生や、来迎をたのんでの往生ではないのです。もっといいかえれば、臨終のさまの善し悪しを問題にしたり、来迎のあるなしを問題にする往生ではないということです。
そこで聖人は、この往生のちがいをはっきり区別しておくために、「まず善信(ぜんしん)〔親鸞聖人(しんらんしょうにん)自身のお名前〕が身には」と、自らのお名前を出して、信心(往生)が定まっている私としては、いまさら臨終の善悪を申すまでもないと表白(ひょうびゃく)されたのでありました。
ひとくち法話No159 ―聖人のおことば7― より

第160話 如来大悲の恩徳は身を粉にしても報ずべし
如来大悲の恩徳は 身を粉にしても報ずべし(にょらいだいひのおんどくは みをこにしてもほうずべし)
師主知識の恩徳も 骨を砕きても謝すべし(ししゅちしきのおんどくも ほねをくだきてもしゃすべし)
『正像末法和讃(しょうぞうまっぽうわさん)』第五十八首
このご和讃(わさん)は恩徳讃(おんどくさん)ともいわれ親しみ深いおことばです。
阿弥陀如来は、計れぬ程の永い時間をかけて思いをめぐらせ、この世の迷いの中に苦しむ人々を救おうと深甚(じんじん)な願いを建て、この願いが成就(じょうじゅ)しなければ私は仏にならないと誓われました。この誓いを弥陀の本願といいます。汚れた心を持った者でもそのまま救おうと、阿弥陀如来の方から手をさしのべ私の名を呼べとお念仏を与えてくださいました。これが如来の大悲で、このご恩は尽くしても尽くしきれないものであります。
師主とはお釈迦様のことです。お釈迦様がこの世に出られたのは、阿弥陀如来の大悲のお心を人々に説くためでありました。知識とは、印度(いんど)、中国、日本へと永い歳月を経て阿弥陀如来のお心を伝えて下さった7人の高僧(こうそう)方であり、そのおかげで、今日の私たちに尊いお念仏がとどけられたのであります。親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、このご恩は骨を砕いても感謝し尽くせないといわれています。
この様な尊いみ教えに生かされ、救われていくということは何と有り難いことでありましょうか。
このみ教えを信じ、お念仏の日々を送らせていただくことが、まことの報恩感謝の心であることをお示し下さったものであります。
ひとくち法話No160 ―聖人のおことば8― より

第161話 僧に非ず俗に非ず
これは、親鸞聖人(しんらんしょうにん)の主著である『教行証文類(きょうぎょうしょうもんるい)』の終わりの部分に述べられている言葉です。
「僧に非ず俗に非ず」という相矛盾(あいむじゅん)するような述べ方ですが、そこに聖人の強い気持ちが表現されています。
聖人は「承元の法難(じょうげんのほうなん)」(承元元年・1207)で越後(えちご)へ流罪(るざい)となったことに関して「・・・門徒数輩(もんとすはい)、罪科を考えず猥(みだ)りがわしく死罪に坐(つみ)す。あるいは僧儀(そうぎ)を改めて姓名(しょうみょう)を賜(たも)うて遠流(おんる)に処す。予はその一なり。しかればすでに僧に非ず俗に非ず。・・・」と述べられています。
無実の罪にもかかわらず、朝廷の怒りをかい、僧として公認されていた僧籍(そうせき)をはく奪され、藤井善信(ふじいよしざね)という俗名を与えられて流罪に処せられました。それで、もはや「国家によって公認された僧侶ではない」と一方的な弾圧に対する批判をこめたような強い言い方になっています。だから、俗に非ず(世俗の生活に終始するような俗人でもない)というのです。普通に読めば、僧でなければ、俗人であるはずです。僧でなくても、俗人でもないということはありません。
つまり、「僧に非ず俗に非ず」ということは、凡夫に広く救いの道を明らかにするという仏道を貫くために、僧俗という立場をのり超えた人間親鸞の仏者(ぶっしゃ)としてのきびしい姿勢がうかがえるのです。
ひとくち法話No161 ―聖人のおことば9― より

第162話 摂取不捨の利益
弥陀の本願信ずべし 本願信ずる人はみな (みだのほんがんしんずべし ほんがんしんずるひとはみな)
摂取不捨の利益にて 無上覚をばさとるなり (せっしゅふしゃのりやくにて むじょうかくをばさとるなり)
このご和讃は、親鸞聖人(しんらんしょうにん)が85歳の時、夢のお告げによって書きつけたところから「夢告讃(むこくさん)」と言われています。和讃の大意は「あなた方よ、弥陀の誓願を信じなさい。信ずる者は皆『必ず浄土に往生させます』と言うご利益を得て、さとりの位につかせていただくのである」ということです。
『観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)』に阿弥陀さまの光明は、あまねく十方世界(じっぽうせかい)を照らし、念仏の衆生を摂取して、捨てたまわずとあります。それが阿弥陀さまの本願他力のはたらきであると聖人は味わっておられます。他力とは本願を信じ、念仏を申す者を、大悲の光明の中に摂(おさ)め取って、決して捨てたもうことなく、浄土へ迎えて下さる阿弥陀さまのおはたらきを言うのです。
私達が、本願を信じ念仏を申すことは、阿弥陀さまが私達の内面にまではたらいてくださって、呼び覚まし、新しい生き方を与えて下さった姿であるのです。
親鸞聖人は、阿弥陀さまこそ真実であるとお示しくださいました。
ひとくち法話No162 ―聖人のおことば10― より

第163話 恥づべし傷むべし
平成23年が静かに幕を開けました。親鸞聖人の750回遠忌報恩大法会もあと1年と少々になり、「聖人のみもとに帰ろう」の標語が日1日とその重みを増して迫ってまいります。
標題のお言葉は、親鸞聖人が主著『教行証文類(きょうぎょうしょうもんるい)』のなかで、ご自身の本当のこころの内を自省なさって、ご自分を深く慚愧(ざんぎ)なさったお言葉であります。その部分を意訳すると次のとおりであります。
「まことに知ることができました。悲しいことにこの私〔愚禿親鸞(ぐとくしんらん)〕は、むさぼりのはてしない海におぼれ、地位や名誉や財産の深い山をさまよって、不退のくらいを得て必ず佛(ほとけ)になるべき身と定まることを嬉しいとも思わず、真実のさとりに近づくことをも楽しいと思わない、まことに恥ずかしく嘆かわしいことであります(恥づべし傷むべし)。」
聖人にして海におぼれ山に迷うと仰せなら、この私の有り様は、今すでにおぼれ迷っている自分であることにさえ全く気付いていないのであります。
例えば、この私の姿はデパートのオモチャ売り場で、自分が迷子になっていることにも気付かず、またお母さんの呼び声にも気付かず、1人でオモチャに夢中になっている幼子の姿と全く同じであります。この子が無事お母さんの胸に抱かれるためには、自分が迷っていることに気付いてお母さんの名を呼び、自分を呼んでくださるお母さんの呼び声を聞き届けることであります。私たちにとって、この場合のお母さんは阿弥陀様でその呼び声は南無阿弥陀佛のお名号であり、またその南無阿弥陀佛は私の阿弥陀様に対する返事のお念仏でもあるのです。
今年も私を名指しで呼んでくださる呼び声を聞いて、南無阿弥陀佛とお返事させていただける安らかな日々を送りたいものであります。
ひとくち法話No163 ―聖人のおことば11― より

第164話 信心ありとも、名号を称えざらんは詮なく候
この文言は、信心と念仏についての弟子からの質問に、聖人が答えられたお便りの一節です。「たとい信心があるからといっても、み名を称えなければなんの甲斐(かい)もありません」とのべられているところです。
どの宗教も信心とか信仰心を説きます。そして熱心な人を「信心深い人」とか「信仰心の篤い人」などといいます。この場合の深い、篤いという判定は誰がするのでしょう。神・仏からの声はないから、信者自身が勝手に自分の努力や結果を評価して、あるとかないとか、深いとか篤いとかというのでしょうか。または他人からのうわさを聞いて本人がそのように思い込むのでしょうか。このような信仰を自力の信心と言います。
さて、聖人がお返事の中で「信心ありとも」と申されている対象の方が誰であるかは判然としませんが、聖人はその方に「真宗は他力の教えです。弥陀大悲の誓願を深く信ぜん人はみな、ねてもさめてもへだてなく南無阿弥陀仏と称うべし」と教えて下さっているのです。だから、たとえ信心があるからといっても、自然にお念仏がでてこないような信心は、自力の信心と同じで何の甲斐もありません、とのべられたのです。
そして聖人はこの文言に続いて「また一向名号を称うとも、信心あさくば往生しがたく候(そうろう)」とさとされ、どこまでも真宗の他力信心は、称名(しょうみょう)とワンセットであることを強調しておられるところです。
お互いに自分の信心を吟味(ぎんみ)する時の大事な要素でありましょう。
ひとくち法話No164 ―聖人のおことば12― より

第165話 如来の廻向をたのまでは 無慚無愧にてはてぞせむ
自力で人生を生きぬいていこうと考えていた頃を振り返ってみると、われこそは、人となりの知識を深め、善行(ぜんぎょう)につとめ、人格を高めていこう。仕事には精一杯努力して、まじめに生きていこう。そして身・口・意(しん・く・い)の三業(さんごう)にも気をつけていけば、いつかは心に仏種(ほとけだね)が芽生えてくるにちがいない。などと大まじめに決意したものでありました。
そんな時は自分ながらひそかに、こんな心意気(こころいき)を自画自賛(じがじさん)して、優越感(ゆうえつかん)をもったものでした。
その私が、このような自力のとりくみに行き詰ってしまい、ほとけ(阿弥陀仏)の光に照らされてみたら、今までの心意気や自負心(じふしん)はどこへやら、自分の心でありながら自己中心のなんとはずかしい根深い心であることかと驚くばかりでありました。その心とは、「無明煩悩(むみょうぼんのう)われらが身にみちみちて、欲も多く、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおおくひまなくして、臨終の一念にいたるまでとどまらず、きえず、絶えず」という煩悩具足の凡夫そのものだったのです。
だから、どれほど自力の道に精進しても、煩悩にまなこさえられて修善(しゅぜん)は雑毒(ぞうどく)の善となり、修行は虚仮(こけ)の行と化すばかりでした。
もうこの上は、私のすくいは本願を信じ念仏申すという真宗他力の教えによるほかないと知るのでありました。
蛇蝎奸妰のこころにて 自力の修善はかなうまじ(じゃかつかんさのこころにて じりきのしゅぜんはかなうまじ)
如来の廻向をたのまでは 無慚無愧にてはてぞせむ(にょらいのえこうをたのまでは むざんむぎにてはてぞせむ)
『正像末法和讃(しょうぞうまっぽうわさん)愚禿悲歎述懐(ぐとくひたんじゅっかい)第六首』
ひとくち法話No165 ―聖人のおことば13― より

第166話 愚禿釋親鸞
親鸞聖人(しんらんしょうにん)には、いろいろのお名前があります。
幼い時のお名まえから順にあげていきますと「松若丸(まつわかまる)」、出家して「範宴(はんねん)」、法然上人(ほうねんしょうにん)の門下に入って「綽空(しゃっくう)」、承元(じょうげん)の法難(ほうなん)の時につけられた罪名(ざいめい)〔俗名(ぞくみょう)〕を「藤井善信(ふじいよしざね)」、非僧非俗(ひそうひぞく)を宣言して「愚禿釋親鸞(ぐとくしゃくしんらん)」と名のられました。そして「親鸞(しんらん)」「善信(ぜんしん)」と呼ばれることもありました。
聖人が29歳の時、専修念仏の停止(ちょうじ)という院宣(いんぜん)がくだされ、僧籍をはく奪され、「藤井善信」という俗名を罪名としてつけられました。赦免(しゃめん)されたのち、聖人はもはや、「僧に非(あら)ず、俗に非ず」と宣言して、自ら「愚禿釋親鸞」と名のられました。
「愚」とは「おろか」ということですが、仏の光に照らし出され自己の愚かさに気づかされるということです。「禿」とは「禿(は)げ」という意味ではありません。六角堂の夢告により法然上人と出遇われたのちは、お念仏以外のもろもろの修行を棄てさったということを表しています。「釋」はお釈迦さまの弟子〔仏弟子(ぶつでし)〕、そして「親鸞」とは七高僧(しちこうそう)のうちの天親菩薩(てんじんぼさつ)と曇鸞和尚(どんらんかしょう)から一文字づついただかれたお名前です。
国家から任命された、上流階級のための僧侶ではなく、お念仏以外のもろもろの修行を棄てて本願に帰す身となって、広く一般民衆に開かれた真の念仏者でありたいという強い決意にあふれたお名前なのです。
ひとくち法話No166 ―聖人のおことば14― より

第167話 南無の言は帰命なり
ある遊園地で母親が、迷ってしまった我が子の名を呼び続けています。その子は、迷子になっているとも知らずあちらこちらと楽しく歩き回っているうちに、ふと自分が迷子になったことに気付いて「お母ちゃん!」と母を呼びます。そのとき、それまでは聞くことができなかった母親の不安気(ふあんげ)な呼び声が一段と大きくなって安心の呼び声となり、親子が名を呼び合いながら、子は母の胸に飛び込んですべてを母に任せるのです。このときの子の姿は、まさに阿弥陀様にすべてをゆだねた私の姿なのであります。
「南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)」、これは私たちが日常称えるお念仏であります。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、このお念仏について「南無の言は帰命なり」と仰せになり、「帰命というのは、必ず汝(なんじ)を救い摂(と)るぞと私を呼び続けてくださる阿弥陀様の呼び声を聞いて、そのお心にしたがって自分のはからいを捨ててすべてを阿弥陀様のおはからいに任せることである。」と示されました。
ところが私たちは、自分の地位や名誉や学識などに執着(しゅうじゃく)して、なかなか自己のはからいを捨てることが出来ずにさまよい続けているのです。
このような私たちは、仏法を聞き、お念仏を糧(かて)とした日々を送ることで徐々に執着を離れ、やがて、罪悪深重(ざいあくじんじゅう)の自分でありながらとっくから阿弥陀様の願いの中に生かされていたことに気付かされるのです。それにつれて、称えるお念仏がだんだんとこころの深いところからわき上がる喜びの南無阿弥陀佛となり、いよいよ、聞こえた!阿弥陀さんの呼び声が聞こえた!と踊躍(ゆやく)し、遇えた!遇えた!阿弥陀さんに遇えた!と歓喜(かんぎ)のお念仏へと深められてゆくのです。
十方諸有の衆生は 阿弥陀至徳のみなをきき (じっぽうしょうのしゅじょうは あみだしとくのみなをきき)
真実信心いたりなば おほきの所聞を慶喜せん (しんじつしんじんいたりなば おほきにしょもんをきょうきせん )
『浄土和讃(じょうどわさん)〔讃阿弥陀仏偈和讃(さんあみだぶつげわさん)〕第二十三首目』
ひとくち法話No167 ―聖人のおことば15― より

第168話 弥陀ノ本願信ズベシ
このことばは、有名な夢告和讃(むこくわさん)のはじめの句です。「阿弥陀仏の本願を信ぜよ」という命令調の力強いことばとして、私どもに迫ってきます。
このことばに続いて「本願信ズルヒトハミナ 摂取不捨(せっしゅふしゃ)ノ利益(りやく)ニテ 無上覚(むじょうかく)ヲバサトルナリ」〔「本願を信ずる人は皆ことごとく救いとって捨て給(たま)わぬ弥陀の誓願(せいがん)の功徳(くどく)によって、この上ないさとりを得(う)るのである」法主殿著『註解国宝三帖和讃(ちゅうかいこくほうさんじょうわさん)』より〕ということばのある和讃です。
この和讃には、はじめとおわりに詞書(ことばが)きがつけられています。はじめには、康元(こうげん)2年(1257)2月9日の午前4時ごろ、夢のお告げにより感得(かんとく)されたということばがあります。そして、おわりには、夢の中でお言葉を賜(たまわ)って、うれしさのあまり書きとめ申しあげたと述べられています。さらに、聖人85歳の時にこれを書いたと記されています。
この「夢のお告げにより」ということと「85歳の時にこれを書いた」ということには、たいへん意味深いものがあります。「夢のお告げ」は、これまで何度も経験されていますが、単なる夢見心地(ゆめみごこち)ではなく深い瞑想(めいそう)から生まれてくる三昧(さんまい)の境地(きょうち)であります。また「85歳」は、長男善鸞(ぜんらん)を義絶(ぎぜつ)した直後の年であり、わが息子を義絶してまで真実を貫こうとしたなみなみならぬ決意がその背景にあるのです。
まさに、本願念仏の真実が述べられている深い重みのあることばであることがわかります。
ひとくち法話No168 ―聖人のおことば16― より

第169話 真実の信心は必ず名号を具す
標題のお言葉は、親鸞聖人(しんらんしょうにん)が『教行証文類(きょうぎょうしょうもんるい)』のなかで述べられているもので、本当の信心には必ず名号(みょうごう)〔称名念佛(しょうみょうねんぶつ)〕が具わっていると示されたお言葉であります。
その意味は、真実の信心とは、本願(ほんがん)〔南無阿弥陀佛(なもあみだぶつ)〕のいわれを聞き届けて疑うこころがないことであり、その信心をいただいた人の口には自然と報恩感謝(ほうおんかんしゃ)のお念仏がこぼれるというものであります。
例えば、卒業以来会ったことがなかったあなたの旧友が、あるときひょっこりと海外旅行の土産話と好物の土産物を届けにきてくれました。その彼は、学生時代にはお互いに心から信頼し合っていた無二の親友であります。彼は、ひとしきりの土産話の中で、「素晴らしい景色を眺めるたびに君を思い出し、今度は是非君と来ようと思った。」と言って大好物の土産物をくれました。その時あなたは、彼がこんなに自分のことを気に掛けていてくれたことの嬉しさに、思わず知らず有難う有難うと何度も繰り返すことでしょう。そしてもう一つ大事なことは、その嬉しさと感謝の気持ちがあらわれる裏には、長い間彼のことを思い出すこともなかった自分の姿に気付かされ、その姿を恥じ懺悔(さんげ)するこころが無意識のうちにも働いているということであります。
この場合の旧友は阿弥陀様で、そのはたらきがあなたに届いたときあなたには真実の信心が決定(けつじょう)し、沸き上がる喜びと感謝の思いがお念仏となって思わず口からこぼれ出るのであります。
聖人は、このことを御書(ごしょ)の中で「信(しん)をはなれたる行(お念仏)もなし行(ぎょう)の一念をはなれたる信の一念もなし。」とも、「信心ありとも名号をとなえざらんは詮(せん)なく候(そうろう)」とも述べられて、真実の信心は必ずお念仏と一体であることをお示しくださったのであります。
ひとくち法話No169 ―聖人のおことば17― より

第170話 薬あり 毒を好めと候うらんことは あるべくも候わず
聖人(しょうにん)が京都へ帰られたのち、関東から聖人のもとへ色々な便りが届きました。そのお返事を読むと、弟子の中には、次のような理由を掲(かか)げて、真宗の教えを曲げて人々に宣伝していることがわかります。
一、この世では、みな自分の都合のよいように、ほとけの教えまでいいかえて、自分も迷い人をも惑わして、不安がっている者がいます。
二、ほとけの教えをまともに聞かず、自分の考えこそ正しいと人々に言い触(ふ)らして、念仏者を批判する者がいます。
三、弥陀のお誓いを聞き始めた頃は、無明(むみょう)の酒に酔って、貪欲(とんよく)・瞋恚(しんに)・愚痴(ぐち)の三毒(さんどく)の煩悩(ぼんのう)に生きる自分に目覚めるのだが、臨終の一念にいたるまで煩悩はわが身から消えないことが知れてくると、急に求道心(ぐどうしん)にブレーキがかかって、ここまでわかればもう十分だ。このような私たちを救わねばと誓われたのが、阿弥陀仏(あみだぶつ)の他力の教えであると聞いている。もうこれで助かっている。この上は、心のままに身を許し、口にも言ってはならないことを許し、心にも思ってならないことを許してよいと申し合っている者がいます。
これらは大変不憫(ふびん)なことです、と聖人は申され『浄土論(じょうどろん)』に「このような人は、仏法(ぶっぽう)を信ずる心がないから、こうした心をおこすのです。ここに薬があります。さあ、毒を好きになりなさい。というようなことは、とんでもないことです。」となげかれました。
『親鸞聖人 御消息(しんらんしょうにん ごしょうそく)』
ひとくち法話No170 ―聖人のおことば18― より

第171話 賢者の信は、内は賢にして外は愚なり
このことばは、親鸞聖人(しんらんしょうにん)がその著書『愚禿鈔(ぐとくしょう)』の冒頭に述べられているものです。
法然上人(ほうねんしょうにん)などの賢者は内心に深く仏法を信じ、外に賢者善人らしい相を表わされないという意味です。このことばのあとに「愚禿が心は、内は愚にして外は賢なり(ぐとくがしんは、うちはぐにしてそとはけんなり)」という対句的表現(ついくてきひょうげん)として述べられています。「愚禿」とは、僧でありながら、その戒律(かいりつ)も守れないおろか者という意味で、聖人みずからがえらばれた名のりであります。くわしくは『教行証文類(きょうぎょうしょうもんるい)』の後序の部分に述べられています。
その句の意味は、そのような愚か者の心(しん)は、智者ぶって、賢者のすがたを外にあらわし、名誉や利益のためにうきみをやつしているということです。
これらのことばは、聖人の深い自己反省から生まれたもので、罪悪深重(ざいあくじんじゅう)の凡夫(ぼんぶ)としての自覚が強くにじみ出ています。
そのおこころが『正像末法和讃(しょうぞうまっぽうわさん)』に、次のように詠まれています。
是非しらず邪正もわからぬ (ぜひしらずじゃしょうもわからぬ)
このみなり
小慈小悲もなけれども (しょうじひょうひもなけれども)
名利に人師をこのむなり (みょうりににんしをこのむなり)
《口語訳》
物事の是非も知らず、邪・正の判断もできない私です。人間としての小さな慈悲さえも持っていないこのような身ですのに、世間から名誉や利益のために人の先生と呼ばれることを好んでいるこの私なのです。
ひとくち法話No171 ―聖人のおことば19― より

第172話 「信心」というは すなわち本願力廻向の信心なり
聖人が京都東山吉水の法然上人(ほうねんしょうにん)のもとで勉学中のあるとき、「師法然上人のご信心と私の信心はいささかもかわりありません。」と申されると、先輩のお弟子さんたちが、お師匠さんとわれわれ弟子の信心が同じとは大変恐れ多いことであると、口々に聖人を咎(とが)められました。そこで聖人が、「お師匠さんの信心も私の信心も阿弥陀様から給(たま)わった他力の信心ゆえ、何らかわりはありません。」と言われると、それを聞いておられた法然上人は、「他力の信心に深い浅いなどの違いはなく、みな同じである。」と他のお弟子さんを諭(さと)されました。この出来事は『信心同異の諍論(しんじんどういのじょうろん)』として伝えられているものであります。
標題の「信心というは、すなわち本願力廻向の信心なり。」というお言葉は、聖人がその主著である『教行証文類(きょうぎょうしょうもんるい)』のなかに示されたもので、そのお意は、阿弥陀様が「汝(なんじ)を必ず救う」との誓い(本願)とそのはたらき(本願力)を南無阿弥陀佛のお名号にして、かねてから私に与え〔廻向(えこう)〕てくださっており、私がそのお名号(みょうごう)のいわれをしっかりといただく(聞き届ける、感じ取る)ことが、真実の信心であると教えられたものであります。
これはまさに先の諍論にある「阿弥陀様から給わった他力の信心」とのおこころを示されたものであります。
阿弥陀様は、私を救い摂ってくださるはたらきを南無阿弥陀佛の名号にして、今すでに私に与えてはたらきつづけていてくださるのであります。
このうえは、聞法とお念仏の日々を送る中で、そのはたらきに気付かせていただくことが本願力廻向の信心をいただくことであり、これこそが聖人のみもとに帰らせていただくことになるのであります。
ひとくち法話No172 ―聖人のおことば20― より

第173話 自身を深信する
聖人の『愚禿鈔(ぐとくしょう)』に述べられていることばです。
「自身を深信する」とは、わが身を深く信じるということです。「深く信じる」ということは、物ごとをよく見定めることです。私達はなかなか自分の本当の姿を見定めることができません。自分にとって都合よく見えるものに目が移ろっていきます。煩悩(ぼんのう)のまなこで物を見、自分を見つめているからです。
私達は教えに出遇うことによって、はじめて自分自身のほんとうの姿を知らされ、いろいろなかかわりの中で生きている自分自身が見えてくるのです。そのようなかかわりから解き放たれて、問題のない人生を生きることができると思っていたのは、自分勝手に思い描いたむなしい夢であったことに気付かされるのです。自分勝手なむなしい夢に自らも迷い、他をも傷つけていたことをはじめて知らされるのです。
そこに自分自身のあり方が見出されて、真実の世の中が開かれてくるのです。
『浄土高僧和讃(じょうどこうそうわさん)〔善導禅師(ぜんどうぜんじ)〕』
煩悩具足ト信知シテ(ぼんのうぐそくとしんちして)
本願力ニ乗ズレバ(ほんがんりきにじょうずれば)
スナハチ穢身ステハテテ(すなはちえしんすてはてて)
法性常楽證ゼシム(ほっしょうじょうらくしょうぜしむ)
〈口語訳〉
煩悩まみれであると感じ知って
本願の救いにまかせるならば
迷いの身からさめて
真実の世界にめざめさせていただく
ひとくち法話No173 ―聖人のおことば21― より

第174話 雑行を棄てて本願に帰す
この聖人のお言葉は、平成23年10月の真宗カレンダーの法語になっています。その頃私は、病院に入院中で、枕元にこのカレンダーを掛けていました。担当の若い看護師研修生から、「これはうちにもあります。言葉のわけを教えて下さい。」といわれたので、わかるようにと色々問答しながら、次のような話しをしました。
私たち真宗の特色は、他力の教えです。他力とは、ご本尊の阿弥陀仏の本願力のことです。阿弥陀仏は私たちを煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)と見抜かれて自力では悟りの開けない人々だから、ほとけさまの方から私たちの救いの道理を建立され、この道を歩めと呼びかけてくださったほとけさまなのです。この道とは「本願を信じ 念仏申せばほとけになる」という道です。聖人は長い間歩まれていた自力修行の仏道に行き詰っていた時、ちょうど師法然上人(ほうねんしょうにん)からこの阿弥陀仏の他力の救済の道を教えられ、わが身が凡夫であることに気付き、即座に自力修行は「雑行(ぞうぎょう)」であったと翻意(ほんい)して、本願に帰されたのでありました。このところを聖人は和讃の『愚禿悲歎述懐(ぐとくひたんじゅっかい)』で「他力の光に照らされてみると、私に真実の心なし虚仮不実(こけふじつ)のこの身には清浄(しょうじょう)の心も更になし」と反省し、また「浄土の行にあらぬをば ひとえに雑行と名づけたり」『善導讃(ぜんどうさん)第七首』とのべられています。
人間社会の生活なら、自力の努力で生涯通すことが当然でありましょうが、事ひとたび、浄土往生という後生(ごしょう)の一大事を尋ねる心が出てきたら、それは他力の教えを聞くほかないと教えてくださるのが真宗です。雑行を棄てるとは、自己否定に立つことです。そこに他力の白道(びゃくどう)が開かれます。自己否定のない、本願に帰す道はありません。
ひとくち法話No174 ―聖人のおことば22― より